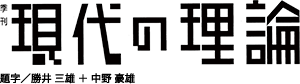編集委員会から
編集後記(第42号・2025年夏号)
―――天下大乱の元凶はトランプ。ノーベル平和賞は無理でも歴史には名を残す
▶世界・日本、後世の歴史に刻まれる天下大乱が進行しているのだろうか? やはりそうだろうとの想いが深まる昨今である。雪崩を打つかのような欧州諸国の右傾化、あのドイツでも極右が伸張。先の日本の参院選挙結果もそのことをものがったているのか。それにしても参政党とは何だ、どう考えても自民党の悪しき別動隊であり、それは自民党の退化という冷徹な現実の反面でもある。ただ、それなりの党費を負担しての党員数には注視する必要あり。国民民主党も自公の別動隊と言われないことが肝心だ。立憲民主党はここが踏ん張りどころだ。それぞれの持ち場での地道な努力に尽きる。
▶“天下大乱”の元凶はかなりの確率でトランプであろう。この男、我らの感性や知力では理解しがたい。その男の感性や知力が国の半分を支配しているアメリカという国はどういう国や、である。そのトランプ、日本ではメディアの報道が少ないが、例の「性的スキャンダル」がアメリカでは連日連夜、大きく報道されている。トランプの命取りになるとの指摘もあるが、さてどうなるか。
本号巻頭で有田芳生さんは、「参院選の結果-日本は新しい冬の時代に」を語る。また「本誌」への注文もいただく。時代への発信で本誌橘川俊忠さんは、「戦後八十年、何を忘れてはならないかー単なるリセットは破壊しかもたらさない」と論じる。金子敦郎さんには「漂流始めた米国」を分析願った。愁眉の課題となっているが、保守派の抵抗だけではなく、認識が深化しない「選択的夫婦別姓」、本誌の池田祥子さんは、「選択的夫婦別姓が問うもの」を分析する。
▶それにしても日々の報道をみるのが憂鬱になる昨今ですがへこたれてはいれません。本号、多彩な論考を収録しました。ゆっくりご覧ください。(矢代 俊三)
▶有田さんの言われる「冬の時代」、深く歴史的に考えたことがなかったので、重く受け止めた。確かに1960,70年代からバブル崩壊まで、おそらく今とは全く違う社会だったのだと思う。新自由主義が浸透して、今の45歳くらいまでの中堅の人たちは皆新自由主義を当たり前に身につけているのだとは思っていたが、それが排外主義につながり、ファシズムの入り口になりそうだとは思わなかった。情けないが、今からでもよく考えたい。
▶最低賃金が63円上がる。最賃近傍(時給で+100円までの範囲)には全労働者の3割がいる。すると、この最賃改定で1000万人ほどの賃金が上がることになる。要するに貧乏人が圧倒的に多くなっているのに、そのことが大きな問題にならない。皆自己責任だと考えているのだろうか。労働組合でも、仲間を集めて(団結して)集団的に経営と対峙しようという相談は、ほぼ皆無だ。8月3日の横浜市長選挙でも、参政党はいなかったが、6人の候補のうち3人が「横浜市民ファースト」「横浜市民第一主義」「ヨコハマ、アゲイン」と言っていた。仲間を作れないから外に「敵」を作り、周りを疑似的仲間と想像するのだろうか。確かに「冬の時代」だ。(大野 隆)
▶今回の参議院選挙の結果を考えてみる。自民党の安倍派に巣くっていた極右といっていい連中が落選したことはよかったといえるだろう。他方では、欧米のメディアが極右とよぶ参政党が大きく議席を増やした。しかし、自民党の右翼の票が参政党に流れたのかというと、ことはそんなに単純ではないようだ。琉球新報によれば、革新票の票田だった読谷や北谷などで参政党が票を伸ばしているという。あるいは、いままで政治に無関心だった層を掘りおこしたともいわれる。有田さんのインタビューでも、かつて瀬長亀次郎を支持していた高齢者が今回は参政党に投票すると新聞記者の取材に答えていたという話が登場する。よく言われることだが、参政党の話がわかりやすいという声が多い。そういえば、かつてのドイツの極右ナチスも宣伝がうまかった。参政党が重視する政策、「日本人ファースト」、オーガニック食材の普及促進などは、とどのつまり、「血と土地」政策といえるだろう。この2つはナチスも重視した。欧米のメディアが極右と呼ぶのはそれなりの理由があるといえるだろう。日本にも登場した極右政党の今後の動向を見定めていかねばならないだろう。(黒田 貴史)
季刊『現代の理論』 [vol.42]2025年夏号
(デジタル42号―通刊71号<第3次『現代の理論』2004年10月創刊>)
2025年8月10日(日)発行
編集人/代表編集委員 住沢博紀/千本秀樹
発行人/現代の理論編集委員会
〒171-0021東京都豊島区西池袋5-24-12 西池袋ローヤルコーポ602
URL https://gendainoriron.jp/
e-mail editor@gendainoriron.jo
郵便振替口座番号/00120-3-743529 現代の理論編集委員会