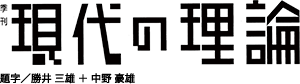連載●池明観日記─第31回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
》幻想《
人生の終わりに浮かんでくる幻想といおうか。昨日北方遠くレイク・シュピリオ(Lake Superior)まで行ってきて疲れたせいであろうか。久しぶりに深い寝りに落ちたかと思うと朝早く目が覚めて目が覚めてあれこれと考えにふけざるをえなかった。この歳でなんという執念でこのようにあえぐのであろうか。これからのことを考えると沈黙と死と諦念にかられ、過ぎ去ったことを考えると悔恨のにじむ幻想であり痛みであるといおうか。一つには日本人と彼らの詩歌ということそして彼らが引き起こした戦争、彼らの東洋制覇というはかない夢のことが思い出された。『変わらない空』を読んだせいであろう。

ほんとうに海のようなレイク・シュピリオは例年は凍らないが、今年は95パーセントも凍っているという。数十年来の寒さであったという。ミネソタ側のみがかなり広く凍結を免れていたが、静かな湖水全面が雪に覆われて美しい風景であった。どこまでも太古の静寂の世界というべきであった。
この朝はまず日本の詩歌について考える。戦争に協力しなかったという詩歌について考えながら、芭蕉を思い浮かべざるをえなかった。いかにしてあの短い17文字の俳句の世界を確立しえたのであろうか。芭蕉とともに私が『叙情と愛国』という日本の近代詩歌を戦争との関連で考えた本を書きながら読んできた荻原朔太郎のことが頭に浮かんできた。彼は戦争が終わる前にその生を閉じたためであろうか、戦争詩には動員されず、日本の近代詩の正しい道を歩むことができた。それはほんとうに近代的な美しい叙情と苦悩に溢れた世界であった。芭蕉とか荻原のように戦争に動員されなかった日本の詩歌の世界、叙事詩ではなく抒情詩に没入しながら、和歌とか俳句のように短い抒情によって沈黙の中に人生の情緒を盛ろうとした韻文を考えざるをえない。天皇制の讃歌または戦争へと動員されることを避けることができた芭蕉とか荻原の多幸であったといおうか、限りなく淋しい日々を思い浮かべながら彼らにおける日本文学の伝統をたどりたいものだ。
そのような美しい抒情がどうして日本の戦争という狂気に動員されたのかを考えざるをえない。彼らはそのような狂気、残忍な日常を抒情で美化していたのではないか。人間はそのような残忍性も美化せずにはいられず、政治はそれを巧妙に利用するものであるといおうか。やはり日本人の心性というのはこのように多情多感な抒情と血なまぐさい狂気との間を往来しながら、ひややかな叙事の歌は排撃してきたのではなかろうかという思いを打ち消すことができない。これが日本の武士社会をいろどってきた思想的伝統であったであろう。それが日本の武士社会を生きて行く抒情優位の生き方であったと思うのである。
今日は恐るべき戦争に動員されたまま忠誠を尽くす。しかし明日はそのような思想からは退いて美しい抒情に没入する。このような極端に両立した生き方に対して別に疑問を持たずに、それを運命として諦念を持って受け入れたのであった。
こういう考えにひたる一方で、どうしてか今朝は李光洙について再び想いをめぐらすようになる。私は彼が日本人少年を描いた初期作品に見られるごとく、彼は男色的傾向を持っていたのではなかろうかと書いたことを思い返す。彼は私と同郷であるということが作用したのであろうか。またはとても幼い時、故郷の教会に彼がやって来て訥弁で講演をした時の姿が忘れられないためであろうか。そして彼の本を読み始めながら彼の小説に大きく感動したせいであろうか。いずれにせよ、多分これらのことが一つになって私は彼を親日反逆者として簡単に片づけることができなくて苦しんできたのではなかろうか。終戦後南出身の作家たちが彼をたやすく断罪することには同調できないという心情があった。
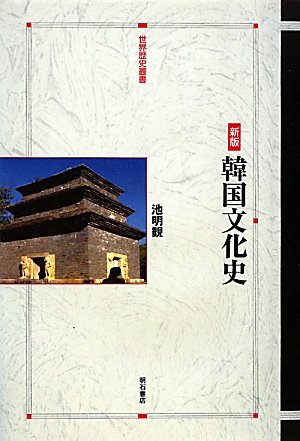
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
実際彼はその親日的姿勢のまま終戦を迎えた時にどのような気持ちであったのだろうか。われわれは彼が彼自身の心情を明らかにした文章のことをよく知っている。そして彼が朝鮮戦争の時代に拉致されて北の政権に協力しながら生き残ることを拒否して人生を終えたのもよく知っている。彼の一生こそ韓国人の近代史として誰かが映画化して照らし出してくれればという思いを捨て切れないでいる。いまは彼をそのように照らして見ることができるほど時間がたっているではないか。
自らのことを告白的に語るならば私が日本統治下で生きてきた20年間もちょうど彼の一生のようなものであったといえよう。中学生のときは李光洙などの韓国の文学者の作品を読みながら自ら民族主義者たらんとした。その頃忘れたかのように韓国語の本を遠ざけていた友人たちは私を民族的であるといっては笑っていた。そのためといおうか私は日本統治下5カ月間小学校教師として悩みながら心から日本に協力しようとした。そのために終戦後は転向者の苦悩のようなものを感じて子どもたちの前で自己告白をしなければならないと考えた。だから終戦後、戦争中の愛国者李承晩、金九をたたえていた私は、1946年の初め共産主義体制の下で彼らを非難することを強要された時、辞任を思い、38度以南に南下することを考えざるをえなかった。
与えられた日々を、それらがどのような日々であろうと、どのような姿勢で生きて行くべきかと苦しまないでは生きて行くことなどできないのであろう。政治的状況に対決して自己規定せずには生きてこられなかった。どうしてそのように生きてこなければならなかったのか。風の吹くままにその時その時の時勢に従って生きて行くことはできなかったのだろうかと今も過ぎ去った日々を回想するようになる。多くの人が与えられた時代を肯定して疑いを持たないかのように生きて来たのにという思いを打ち消すことができない。李光洙の場合はどうしてそのように時が来れば自己決断をし自らの人生を規定しようとしたのであろうか。するすると避けながら生きて行くということはできなかったのであろうか。時代に従って、指示に従って、今日はこの旗に向かって万歳を叫び明日はあの旗に向かって万歳を叫べばいいのではなかっただろうか。それは苛酷な時代に生きる人びとにとって不可避的な人生であり、責めることのできない人生のように思えるのだが。それに対して時には拒否し抵抗したといってもついには暴力の前に屈服せざるをえなかった。するすると避けて行けばいいのになぜ今度は転向を宣言してその手先となると言っては、それを正当化する論拠までも編み出そうとしたのか。私にとってもこのような生き方というのはほとんど宿命的であった。キリスト教的な生き方の影響であっただろうか。
人生の終わりに近づくと私もそのようなことまで考えるのであろうが、ドイツの場合は戦争犯罪という自覚から罪悪告白までしなければならなかったのだが、日本の場合にはほとんどそういう姿勢をさがし求めることができなかったではないか。そこには文化と伝統の相違があるというべきなのか。このような遅まきの考えが今朝は私の頭を抑えてくる。どうしてか、すべてが幻想のように頭に浮かんでくる。フランス人のジークフリートの『成人になったアメリカ』(Andrè Siegfried, America comes of Age, 1927)を読み出したためであろうか。生きてきた歴史とその地の人間たちの心情と考えは引き離すことのできない運命ではなかろうかと思われる。(2014年4月3日)
ジャン・リュック・ゴダール(Jean-lue Gedard)の『シネマの歴史』(Histoires du Cinema、邦題「ゴダールの映画史」)という作品をビデオで見た。フランス語の映画で266分間も続くかなり長い作品であった。映画史をモンタージュした映画である。この映画をよく理解できないまま私の考えを展開してみたい。今韓国と中国と日本の間で日本の戦争犯罪という過去のことが問題になっている。一方日本の若い世代にとっては、そんなことはよく伝えられていないので関心はあまりないのであり、それをいいことにして日本の極右勢力がこれ見よがしに躍っているようである。そのためにアジアとの関係において戦後最大の危機を呼び起こしているように見える。このような時にゴダールの映画のようにモンタージュして過去のことを思い起こしてくれる映画があればと思うのである。日本の過去のニュース映画や一般の映画または新聞記事など事実そのままを見せて、反日的に取り扱うというよりはアジアの痛ましい過去として彼我の心に訴えることが必要ではなかろうか。ゴダールの作品はその当時の悲劇を思い返しながら歴史とは何かとその当時の作家、芸術家に問い返している。日本の罪を問い返し日本を問いつめるというよりは、こんな歴史の意味をみんなでいっしょに考えて見ればどうであろうかと思うのである。
資料を集める段階から日本でも映画人が心を一つにする。日本の誤ちを糾弾し中国とか韓国の行いを讃えるというのではない。われわれが愚かしいほど協力しあったことも描き出すのである。その時代の無明の歴史をモンタージュして提示しながらともに嘆きつつ思いにふけってみようというのである。1990年代の終り頃中国の盧溝橋抗日博物館を訪ねたことを忘れることができない。1937年7月7日、日中が本格的な戦争を始める契機となる盧溝橋事件が起きた地でありその時の川べりの砂原であった。その多くの展示物、その生々しい記録はわれわれが再び目にして考えなければならないものであった。それは日本の軍閥の思い上がった考えの結果であり、日本の国民はそれに熱狂したではないか。悲劇は中国人の数え切れない死のみではなく日本人のあの多くの死でもあったではないか。
ほんとうに歴史にはどのような意味があるのだろうか。そこに関連した人びとの考えを超えた超越的意味があるとすれば、はるか後日になってわれわれ人間はようやくそれをぼんやりと目の前に浮かべることができるというのであろうか。そうであるとすればそのような歴史に人間は人間を超えた力によって翻弄されるとでもいおうか。それが人間が背負う、人間の力ではどうにもならない宿命というのであろうか。ほんとうに歴史とは何か? と考えざるをえない。(2014年4月10日)
昨日教会で洪思勲(ホン・サフン)教授にあうと、私がしばらく前に移民教育学もありうるではなかろうかといったらそうだと答えてくれたのだが、今度自分は移民教育学というべきことを主題として研究費を申請したというのであった。アメリカ軍は彼らが軍事活動をしてきた東南アジア地域からかなり多くの人びとを移民としてアメリカに連れてきた。この移民の子弟はややもすればアメリカの教育において落伍してついにはアメリカの社会問題になるのであるが、彼らに対する特別な教育的配慮がなくてはならない。そのためにそれを研究対象にした教育学を考えねばならないというのであった。
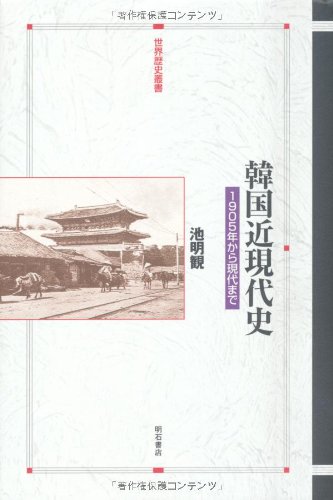
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
実際そういう問題というのはアメリカだけの問題ではなく、全世界的な問題であるといわねばなるまい。韓国においても東南アジアの女性と結婚した場合の子どもたちの問題があるかと思うと、北朝鮮を脱出して南に来た家族の子弟たちの問題もある。彼らはややもすれば南の学校に適応できなくて落伍しがちである。アメリカの社会はこのような問題に世界に先立って直面してきたわけである。アメリカは建国以来移民の国としてそのような教育問題をかかえてきたではないか。私はアメリカはそのような問題に対しても前向きに対応できる姿勢を持っているのではなかろうかといった。教育学も新しく起こってくる社会的問題とともに発展して行くものではなかろうか。
この課題にたいしてもアメリカは先駆的にそのモデルを提示しなければなるまい。そしてそれは直ちに失われた一匹の羊をさがして行くという聖書的姿勢とも直接関係するのではなかろうか。ここに一般教育学とキリスト教における宣教学との接点があるといえるであろう。このような教育学を宣教学的基礎の上に打ち建てて行くことができるといえるかもしれない。教育学とキリスト教宣教学との対話が成立しなければならない。このような面でも移民教会は実際にそれ自身の神学を樹立しなければならない。自分の神学を樹立することなしには自立した教会は成り立たない。このような宣教学的神学が成立するならば、それをもって祖国の教会そしてアメリカ内の韓国人教会、進んでは世界教会と対話を分かちあえるようになるのではなかろうかと思われる。
このように考えながら家に帰り、夕方にはアメリカに留学してきた若い人たちの問題を考え始めた。以前のようにアメリカに留学できたら帰国して優位を占めることができるという時代はもう過ぎ去っている。私自身のための勉強というよりは奉仕のできる学問という考えから、今は祖国に対してはもちろん、世界に対して宣教的意味を持った学問を考えるべきではなかろうか。このような意味においては北東アジア三国の中でもっともキリスト教的な背景を持っているといえる韓国の留学生たちが新しいビジョンを持たなければならない。それでこそ祖国に帰ってから国内一般の人材とは異なった役割をなしうるのではなかろうか。そのようなキリスト教的使命感または宣教的な役割を考えていかねばなるまい。
私は日本にいた時とは違った考えをここではしなければならなくなってきたのかもしれない。私自身の宣教的役割がまだ残っているのではなかろうかと何度も考えた。日本にいた時とは違った形で老後が進み人生が終わるのではなかろうか。このように導かれて行くのだと考えながら寝つけない夜を送らねばならなかった。ふと使徒パウロの20年を超える宣教活動のことを思い出しながら、彼の思想の色合いが老年になりながらどのように変わって行ったかをたどって見たくなった。パウロは一層柔軟になりながらも権威をおびるようになり、献身的になって「力から力へと」(from strength to strength)に前進したと注釈書には記録されているが、私ももっと聖書学的に追求できないものかと思った。私自身の日記には「燃えていた若い頃とは違って、いまはすべてがもの哀しいだけである」と記されている。若い時の情熱的思索というよりは、私の場合はゆっくりとこのような考えをくり返すことにして、私の人生がいつまでもまだ意味づけられていることに感謝しなければならないのではなかろうか。今日も軽い頭痛が続いているのであるが。(2014年4月14日)
キリスト教の影響のせいであっただろうか、私は幼い時からたとえ今日の状況がいかに暗くても比較的楽観的であったような気がする。神が歴史を支配するという漠然とした考えが心の一角にあったためであろうか。この人生に対する執念などそれほど強くなかったともいえるかもしれない。それはその日その日の貧しい生活が苦しかったせいかもしれない。歴史に対しては個々の歴史的事件よりも歴史の流れに興味を持っていた。そのために歴史というよりは歴史哲学に対して関心を持っていた。それで朝鮮戦争の時は死を恐れる同僚たちには「10人の中少なくとも、7、8人は生き残れる。なぜ自分をその2、3人の中に入れて考えるのか。確率的にいえば生き残る可能性がずっと高いではないか。また死んでもいいではないか。この絶望的な国に生き残って悩むことがいっそう怖いような気もする」といって彼らを慰めようとした。あまり深く考えないで偶然そういったに過ぎなかった。すべての状況と条件の中で私は常に希望的なことに心を寄せようとしたし、その一方で死んでもよかろうと諦めようとしたようである。その底にはやはりキリスト教的信仰が横たわっていたし、困難な人生の中で死んでも憾みなしという諦念があったようである。常に今日死ぬかもしれないという一種の実存的な考えにとらわれていたとでもいおうか。
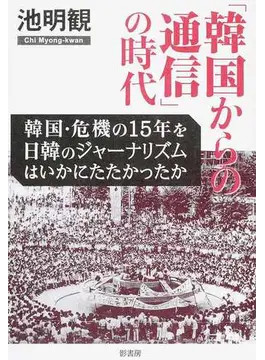
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
歴史、それは奇異なものである。目に見えない手によって導かれるとでもいおうか。急にこのような考えが浮かんでくる。人間本来の征服欲のためか、人間は常に他者を征服しようとしてきた。世界史を一度振り返ってみよう。共産主義が敗北した今日の歴史の中において、アジアにおいては蒙古の世界征服、そして近代史における日本の征服欲。日本はヒトラーの征服欲に参加しようとした。ヨーロッパではポルトガル、スペインとオランダの野望についでイギリスの野望、ヒトラーとムッソリーニの野望とソ連の共産主義という名における世界征服の野心、それからアメリカの世界支配。すべてが歴史的性格を異にするのではないか。親米的だと攻撃を受けるかもしれないが、私はアメリカの世界支配は単純な征服的なものの道ではなく、世界統合の道であると考える。
ここで私はいままでの世界史の一種の終結を考える。世俗的な人間史の完成ともいえる。そのつぎは神が支配する人間協同体とでもいおうか。旧約聖書で見られるように人間のもだえは続くであろう。その世界は今いくら考えても具体的に描き出すことはできない。今までの世界史の流れも人間が想像しえたものではなかった。これからの世界史はどのようなものであろうか。はるかに高度な人間性をたずねる世界。でなければ人間史の終末であるか。人類史の終末は誰も予期していない日に突然臨んでくるのかもしれない。その兆しはあっても、われわれはその日が来るまでそれを弁えることができないというのが聖書の教えではないか。地球にその始まりがあったとすれば、その終わりもあるはずではないか。そのためにアウグスティヌスは『神国論』をものしたと考えるのである。(2014年4月25日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。