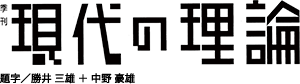特集 ● いよいよ日本も多極化か
ポピュリズムとは何か 欧州にみる
政権与党となった右派ポピュリストたち
龍谷大学法学部教授 松尾 秀哉
衰えぬポピュリズムの勢い
2025年になってもヨーロッパにおけるポピュリズムの勢いに衰えは見られない。前号で記したように、年明けには早々にベルギーでポピュリスト的な政党と位置づけられてきた新フランデレン同盟が、ムッソリーニを敬愛するイタリアの「イタリアの同胞」のジョルジャ・メローニ以来、政権を獲得した。新フランデレン同盟は、2007年以降長期の連立交渉を通じて政権から――連立政権の一角を担うことはあったが――排除してきたベルギーであったが、いよいよ党首バルト・デ・ウェーバーが首相になったことは、従来のベルギーの政治のあり方が変わってきたことを予感させられる。
同様に「妥協の政治」の伝統を有するオランダでは前回選挙で第一党となったポピュリズム政党(自由党)を率いるヘルト・ウィルダースが自らは首相に就かないまでも自ら首相を指名したスホーフ連立政権を6月に離脱し政治的影響力を見せつけた。ドイツでは2月に総選挙が行われた結果、キリスト教民主同盟が第一党は維持したものの、やはり右派ポピュリストであるドイツのための選択肢が第2党になるまで支持層を拡大した。同様のことは2024年に右派ポピュリストが第二党に躍進したルーマニアでも生じており、右派ポピュリスト政党のルーマニア人統一党をかろうじて抑え込んで6月に新政権が発足した。
こうして多くの国でポピュリスト政党は政権を担うか、そこに従来よりも強い影響力をもつことになった。思えば過去「ポピュリスト政党の台頭」が騒がれたのは、例えばわが国でも水島治郎の『ポピュリズムとは何か- 民主主義の敵か、改革の希望か』(中公新書)が刊行されたように、2015-16年であった。それから10年後、「再び」といっても間違いではないだろうが、そして以前よりも強力にポピュリズム政党は支持されるようになり、より影響力を有するようになった。
従来こうした傾向、つまり既成政党や規制の政治を敵視し、単一の争点を掲げて支持を集める政党が一定の成功をおさめて連立政権に加わることになると、「成功のゆえの失敗」のため支持を落とすことが多かった。すなわち政権に就くと、他の政策で手いっぱいで当該争点を十分に扱うことができず支持者に失望されたり、一定の成果を出した場合でも、「役割を果たした」とみなされたり「いや、まだ足りぬ」という急進派が内部分裂するなどして勢力を落とすことが多い。しかしこの10年の間、ポピュリズム政党、特に急進的な右派ポピュリズム政党は一定の支持を維持しつつある。もちろんまだこれから「成功のゆえの失敗」がこれらの政党を襲う可能性が十分にあるが、本稿では、改めて「定着しつつある『ポピュリズム』とは何か」という問題を、いくつかの論考を手掛かりに考えてみたい。
1.ポピュリズムの定義をめぐる議論
ポピュリズム、特に右派ポピュリストや近年の極右と呼ばれる勢力の定義は一定していない。以下、言い古された感はあるが、ここまでのポピュリズムの定義にまつわる議論を Matilde Rosina(2025)らによる議論を参考に整理したい(ただし、2025年のこの議論自体かなりの程度Cas Muddeの議論にもとづいている)。
19世紀後半のアメリカにおけるポピュリスト党(the Populist Party)の場合、ポピュリズムとは単に人びとが政治に活発に関与していくことを意図していた。同様にErnsto Laclauは、ポピュリズムを、リベラル・デモクラシーの限界を是正しようとして、人民が政治に直接的に参加していくことを強調するラディカル・デモクラシーの一形態とみなす。いずれも特定の右派/左派といったイデオロギーに関する含意を欠いており、右派ポピュリスト政党の位置付けについても配慮されていない。
Rosinaらは次に経済的側面あるいは政治的戦略的側面に注目した議論を類型化する。たとえば、やはりMuddeが示しているように、選挙に勝つことを目的とした財政的無責任主義としてポピュリズムを定義する。逆にポピュリズムは時に「強くカリスマ的な」リーダーが人民の意思に直接にもとづいて支配する政治的な戦略だとする見方もある。同様に、大衆の活動の活性化を可能にする政治スタイルとして描く場合がある。
こうした定義において最も成功したものとして評価されているのが、Muddeによるポピュリズムの概念化である。すなわち、ポピュリストのイデオロギーをアイデアのセットとしてとらえ、「腐敗したエリート」と「純粋な人民」を対置し、そして後者の一般意思を実現しようとする。特にミュッデのポピュリズムのイデオロギー理解で重要なのは、ここでもまた右派や左派に対する言及がないことであり、よって曖昧で、政治課題に対してわかりよい解答を与えることができことを意味する、有名な「薄っぺらい(thin)イデオロギー」としてポピュリズムを定義している点であろう。逆にこのために、ポピュリストはあらゆる環境の変化に対応し、自らを他の「分厚い(thick)」イデオロギーと結びつけることができ、その結果「右派ポピュリズム」、「左派ポピュリズム」のようなサブカテゴリーが出来上がることになる。
またMuddeによれば、ポピュリズムは権威主義とも親和性がある。Pippa NorrisとRonald Inglehartによれば、ポピュリズムの言説は、自由民主主義体制において選出された代表からなる既成権力に対する攻撃と、民主主義体制においては「人民」が唯一の正統性の源泉であるという考えを特徴としている。他方で権威主義の側からみれば、ポピュリストの言説の中心にある人民とは外国人や移民、テロリストなどの「他者」から保護されなければならない。それ以上に外部の攻撃に対するこの集団やその価値観の防御は、しばしば保守主義と相通じており、社会・文化的な変化に抵抗する。最後に、権威主義的傾向において、ポピュリストのリーダーはその集団と価値観の守護者として台頭する。人民の多数派が正統性の源泉としてみなされるとき、多数派の意思を代弁すると主張するこうしたリーダーたちはいかなる反対意見や不和を抑え込むことができる。すなわち、ポピュリズムとは本来的に法と秩序を強固に強要する一方で、あらゆるポピュリズムが権威主義というわけでもない。
排外主義はまたMuddeによるよく知られた右派ポピュリズム政党の定義の一部である。
排外主義とは、「ネイティブではない(non-native)」人びとと考えは、基本的に同質的な国民国家を脅かしているという信条である。確かに排外主義は右派ポピュリスト政党の典型的な反移民スタンスをピンポイントで示している。このため右派ポピュリスト政党の言説は「恐怖(fear)の政治」をもとに組み立てられることが多い。人民の意思を代表する集団は、「他者」からポピュリストのリーダーによって保護される「部族」として描かれる。たとえばドナルド・トランプの言説において「部族」とは国民のことであり、よって彼の「アメリカ・ファースト」スローガン、ボリス・ジョンソンによるEUから離脱しようとするブレグジット・キャンペーンが挙げられる。しかし国民はまたエスニシティ、人種、ジェンダーを基礎にしてアイデンティファイされる。国民の核には、ポピュリストのリーダーが、しばしばスケープゴートにされる「他者」のために脅威の下にあると考えられている共通の価値が存在し、これが文化的バックラッシュを作り出す。
こうした排外主義にとどまらず、Dani Rodrikは、現代のポピュリズムの起源を説明するために「グローバリゼーションに対するバックラッシュ」を提唱する。ロドリックにとってポピュリズムとはグローバル化の矛盾に対する反応である。経済的要因を強調しながら、とりわけグローバル化した政治経済における中国輸出の成功がしばしばアメリカの労働力の主要な部門に対する大打撃を引き起こしており、そのためこれらの労働力が経済的に周辺に追いやられ、ポピュリスト・リーダーへの支持を招いているとする。それゆえポピュリズムとはグローバル化の帰結なのである。しばしばグローバル・ノースにとってグローバル化とは移民の増加を意味し、グローバル・サウスでは外国の直接投資の増加を意味するため、グローバル・ノースにおいてグローバリゼーション・バックラッシュは移民に反対する右派ポピュリストの台頭を招き、グローバル・サウスでは資本主義に反対する左派ポピュリストの台頭を導きやすい。しかしいずれの場合もロドリックは、ポピュリズムの起源はゼノフォビアや移民の増加にあるわけではなく、グローバル化による経済的帰結そのものにあるとする。
他のポピュリズムの特徴として「欧州統合に対する失望の感情」を意味する欧州懐疑主義を挙げることができるかもしれない。やはりこれはグローバルな財政危機とEUの主権国家の財政危機の産物であるが、経済的な安全保障の欠陥がポピュリズムの台頭を許すというものである。Rodrikと異なるのは、グローバルな財政危機とユーロ危機に対応するためにEUから課された緊縮政策によるという点である。こうしたRodrikや欧州懐疑主義に対する分析からは、経済危機が、根底にあるグローバル化の矛盾を表面化させるトリガーとして働くという点が示唆される。逆にEU市民の精松水準の低下を招いた制度の非効率性が、典型的にはアンチ・エリート的、とりわけEUの権威をターゲットとしたポピュリストの反応を招いているとする。
こうしていくつかの特質と思われる点を列挙したが、今考えるべきは、政権を担うようになった右派ポピュリスト政党がどうなるのかという点である。果たして以上のような特質を変えていくのだろうか。
2.政権入りしたポピュリズム政党と欧州懐疑主義
ハンガリーのヴィクトル・オルバーンを別にすれば、イタリアのメローニやベルギーのデ・ウェーバーが首相になったことで、上記のポピュリズム政党の特質は変容してしまうだろうか。それともそれは維持されるだろうか。たとえばこれらの政党が「敵」としてきた既成エリートの側に今ポピュリズム政党はいる。そして具体的に政策を立案、実施していかねばならない立場にいる。
かつてこうした反体制的な単一争点を掲げたポピュリスト政党が政権に加わると、与党として当該争点に手をつけることができず、もしくは手をつけてしまうと存在意義を喪失して支持を落としていくことが常であった。これを「成功の故の失敗」と呼び、1980年代以降たびたびヨーロッパで観察された。しかし、おおよそこの10年間ヨーロッパ政治を騒がせるポピュリズム政党は、たとえ政権党にあっても支持を急落させることがない。
たとえば右派ポピュリスト政党の支持の源泉の一つとなっていたのは欧州懐疑主義であった。すなわちEUに対する批判が欧州の有権者をして右派ポピュリズム政党を台頭させた。政権に就いてから、しかしながらポピュリズム政党はEUの他国のリーダーと協調し、しばしばあたかも自らが批判の対象としていたEUのリーダーの一人のように振舞っていた。これでは欧州懐疑主義という主張は筋を通していないようにも思われる。しかし、それでも右派ポピュリズム政党に対する支持が急落しているというようには思われない。
この欧州懐疑主義をめぐる問題には、いくつかアプローチがあるだろう。一つはオルバーンのような、それでもまだ欧州懐疑派を貫くという戦略である。つまりしばしば「ブリュッセル」と形容されるEUのトップエリートを「敵」に仕立てて、自らの欧州懐疑主義を維持する方法である。しかし、こうした「欧州内の懐疑派」戦略は、いわゆる西欧と呼ばれる地域では通用しないだろう。むしろ拡大後に加わった旧東欧地域の国ぐににおいて通用する話である。「EUのエリート官僚が私たちを二流と見下している」という言説が通用するのである。実際にハンガリーのオルバーン政権は強力な支持を維持し続けて、それを基盤としてEUの集合的決定に反対することも多い。
もうひとつのアプローチは、デ・ウェーバーやメローニのように欧州懐疑主義という権力の源泉を捨て去るアプローチである。すなわちEUのリーダーとしてふるまうという戦略だ。デ・ウェーバーは、かつて多言語国家ベルギーにおいて、言語・民族の対立で揺れ続けるなか、「ベルギー不要論」「[ベルギーの1地方である]フランデレン地方の分離独立」を主張して支持された政党である。2010年の連邦選挙において第一党となった際には連立交渉でそれを主張するあまり新政権発足までに1年半の期間を要することとなった。このときは「ベルギー不要論」以外にも、「世襲は非民主的」として国王を批判し、共和国への体制改革なども主張した、ある種「目の前のもの何にでも噛みつく」野良犬のようなラディカルな態度を採っていた。
今回2025年の初頭に晴れて首相に就任して半年、現在では毎週国王に謁見し報告をしている。新聞ではこの態度の差を嘲笑するものいも多い。しかし同紙によれば、デ・ウェーバーは態度を変えた。つまり、首相になることを認めた国王に感謝し注1、陰の批判者でいるよりも表舞台へ立ち、そしてEUの政策決定にかかわろうと決めたというのである。戦略としてはリスキーなようにも思われる。今まで批判していたもののなかに加わっていこうというのだから。こうした戦略はメローニの場合も同様である。
ただ、それであってもデ・ウェーバーやメローニの正統性の源泉は維持される。その政策が排外主義である。移民・難民を受け入れることがEUの矜持であり、それがまた人びとにとって一定の重要な問題である限り、それを推進しようとするEUの政策(決定)から、右派ポピュリスト政党は批判票を引き出すことができる。そしてもしその批判が政策に反映されないなら、やはり欧州懐疑主義を超え高々に叫べばよい。もちろんその声は自らにも降りかかってくる諸刃の剣である可能性は高いが、「敵」を作り上げることは可能である。今回オランダの政権が崩壊したのも、やはり移民問題である。もはやそれが争点化すること、排外主義もしくは日本人ファーストを叫ぶことで突然支持されることは今回の日本の参議院選挙でもわれわれは目の当たりにした。2015年から今に至るまで移民・難民問題は右派ポピュリスト政党の大きな支持の源泉であり続ける。排外主義こそがヨーロッパのみならず世界的な争点となって多様な政党に戦略的に用いられてしまう危険性を感じざるをえない。
こうして排外主義が政策として残る限り、右派ポピュリズム政党は生き残る。しかし他方で右派ポピュリズム政党がこうして「現実主義」路線を取り始めていることも間違いがない。これはフランスの国民連合においても同様だろう。現実路線をとれば、ヨーロッパでは特にウクライナ、そしてイスラエルといった別の問題に直面することになる。果たしてロシアの侵攻を前に、西欧、そしてEUの中心国がオルバーンのように「反EU」であり続けることが可能だろうか。「狂犬」でいつづけることができるか。もしロシアを敵視すれば、それはただの既成政党化である。支援に不満を持つ支持者を取り込むことはできまい。だから今EUの舞台に出てきた右派ポピュリストは、おとなしい、しつけられた子犬のように目立たないリーダーでなくてはならない。今はそのときである。粛々と日々の仕事をこなすときである。もしそれでも支持を得ようとすれば、連立パートナーを「敵」として批判するしかあるまい。しかしその帰結は(同じ連立政権を維持するという点においては)諸刃の剣である。
こうして右派ポピュリズム政党は、今ジレンマのなかに自ら足を突っ込んだ。今のままならば、単に「排外主義政党」となるしかあるまい。排外主義がある限り右派ポピュリズム政党は右派ポピュリズム政党のままであり続けることができる。しかし、政権党となることで今度は自らが子犬となり、逆に「敵」として扱われる危険性も高まることになる。当面ヨーロッパ政治は、右派ポピュリスト政党の動向とその評価をめぐって揺れ動くことになるだろう。
(注1) ベルギーの場合、選挙後、首相の決定に国王が実質的に介入することが多い。詳しくは松尾秀哉(2015)『連邦国家 ベルギー――繰り返される分裂危機』、吉田書店、もしくは松尾秀哉(2022)『ベルギーの歴史を知るための50章』、明石書店を参照のこと。
まつお・ひでや
1965年愛知県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、東邦ガス(株)、(株)東海メディカルプロダクツ勤務を経て、2007年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。聖学院大学政治経済学部准教授、北海学園大学法学部教授を経て2018年4月より龍谷大学法学部教授。専門は比較政治、西欧政治史。著書に『ヨーロッパ現代史 』(ちくま新書)、『物語 ベルギーの歴史』(中公新書)など。
特集/いよいよ日本も多極化か
- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生
- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子
- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京
- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀
- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣
- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆