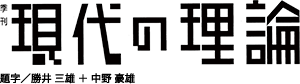論壇
「国民主権政府」李在明政権の時代へ
韓国――「光の革命」を引き継げるのか
朝鮮問題研究者 大畑 龍次
2024年12月3日の尹錫悦前大統領による非常戒厳宣布以降、国会による戒厳令解除決議(20241203)、大統領弾劾決議(20241214)、憲法裁判所による罷免決定(20250404)によって6月3日に大統領選挙が行われた。本来なら2か月ほどの「引継委員会」が組織され、政権移譲と新政権の政策が検討されるところだが、大統領不在のため、当選翌日の6月4日から李在明新政権「国民主権政府」がスタートした。新政権の誕生が今後の朝鮮半島情勢にいかなる影響を与えるのだろうか。
尹錫悦前政権の迷走から戒厳令へ
まず、尹錫悦前政権についておさえておこう。尹錫悦氏は文在寅政権の検事総長で、朴槿恵捜査にも関与したが、文在寅大統領や当時の曺国法相などとも激しくぶつかり、その「頑固さ」から野党「国民の力」の大統領候補に担ぎ上げられた人物だ。検事畑を歩んできたが、自治体などの自治体行政や国会議員の経験もなかった。大統領選挙では「共に民主党」の李在明氏と得票率0.7%の僅差で当選し、韓国社会の分断状況を反映して政権をスタートさせた。党内基盤はなく、検察人脈を政権内に登用したことから「検察共和国」と呼ばれ、専門性に欠ける人事も行われた。支持率は政権スタートから20%前半という低空飛行だった。当初から野党が優勢な国会状況で、野党単独で成立させた法案も拒否権を発動して阻止した。拒否権の数は22回に及び、歴代政権を抜いて1位を記録した。任期が半分ほどを過ぎた時点でこうなのだから、驚くべきことだ。不支持率の理由は、「独善的」や「一方通行」が挙げられていた。少数与党ならば、野党との妥協や「協治」が求められるべきところだが、政治経験のない「頑固さ」ゆえに政権運営に支障をきたした。2024年4月の総選挙でも、与党議席数を減らし、野党議席が300議席のうち192議席となってしまった。200議席になれば弾劾決議が可能になるところだったが、かろうじて踏みとどまった格好だった。解散のない韓国国会の議席数は尹錫悦政権の任期いっぱい続くことから、にっちもさっちも行かなくなって戒厳令宣布に及んだものだ。
その一方、日米との軍事協力を進め、日韓関係でも日本寄りの姿勢を鮮明にした。そのことで日本のマスコミは親日政権と高評価を与え、野党の李在明を反日政治家と警戒する論調となった。対朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)政策では、「大胆な政策」を掲げた。朝鮮の非核化が最優先で、朝鮮が非核化に応じれば朝鮮住民への援助を行うというものだ。文在寅政権は朝鮮が核保有を宣言していても、南北交流に進んだが、尹錫悦政権では対話を拒否したばかりか、「自由統一」と叫んで韓国の原理による吸収統一路線をとった。このため、南北関係は軍事緊張に包まれ、金正恩政権は「二国家論」を唱えて南北の交流・協力を中断させ、非武装地帯の「国境」を遮断した。尹錫悦政権は、脱北者団体による対朝鮮批判ビラ散布の容認、非武装地帯周辺での砲撃訓練、拡声器放送の再開、そして平壌上空への無人機侵入さえ行った。これらの対北挑発行為は、北の軍事行動を誘発して戒厳令宣布する条件を作り出そうとした「北風工作」と言われている。朝鮮側はいわゆる「汚物風船」を飛ばしたが、南の軍事挑発には乗らなかった。
大統領選挙を振り返る
大統領選挙について。尹錫悦前大統領の罷免決定を受けての大統領選だったことから、当初から「共に民主党」の李在明候補(61)が世論調査でリードする選挙戦だった。一方、「国民の力」では金文洙前雇用労働部長官(73)が党の候補者として決定したものの、党指導部は韓悳洙前首相への一本化を画策、党内再投票で金文洙が党候補者となった。選挙戦にはほかに、保守系野党「改革新党」の李俊錫(40)、正義党から党名変更した「民主労働党」の権英国が立候補し、事前討論会でも4人が主要候補者として舌戦を戦わせた。選挙戦の焦点は金文洙と李俊錫との一本化だったが、李俊錫は支持率を伸ばしていたこともあり、「次の大統領選」を意識して一本化を拒否した。
大統領選挙の投票率は79・4%を記録し、この20年間の最高を記録した。韓国国民の関心の高さを示した。主要四候補者の得票率は、李在明49・4%、金文洙41・14%、李俊錫8・34%、権英国0・98%だった。李在明の得票率は、「共に民主党」の得票率としてはかつてない高得票率だったが、圧勝を目指していただけに、満足できるものかどうか疑問。進歩党などの旧野党のうち革新系が候補者を立てずに、李在明に一本化したにもかかわらず、圧勝できなかった。それに対して金文洙と李俊錫の得票率の合計は49・48%となる。保守の候補一本化が実現していたらどうなっていたかわからない。韓国社会の保守と革新の勢力は拮抗していて、社会の分断状況は変わらなかったといえる。
朝鮮半島は南北に分断しているが、韓国内は東西に分断していると言われる。韓国の西部では済州島も含めて李在明が勝利し、東部では金文洙が勝利した。特に全羅道と慶尚道の対比は従来道理といったところ。その差がもっとも開いている例を示せば、次の通りだ。大邱では李在明23・2%に対し金文洙67・6%、一方全羅北道では李在明85・9%に対し金文洙8・5%だった。世代的には、李在明が20~30代の女性に支持され、金文洙が20~30代の男性に支持されていた。これは弾劾・罷免政局でも見られた傾向でもある。40~50代では男女ともに李在明が優勢で、60代では男女とも拮抗し、70代では男女をも金文洙が優勢だった。
李在明政権の課題
李在明のプロフィールについて触れておこう。李在明は、1963年12月生まれの61歳。中学校さえ卒業できず少年工として過ごすほどの貧困家庭だった。少年工時代の怪我が原因で徴兵免除となった。中学、高校とも検定試験を受けて大学に進学し、弁護士資格を取得した。労働者の立場に立った労働弁護士としてスタートした。政治活動を始めたのは2006年からで、京畿道城南市長(2010年7月~2018年3月)、京畿道知事(2018年7月~2021年10月)を歴任した。前々回の「共に民主党」の大統領候補者選挙に出たが、文在寅に敗北した。2022年の前回大統領選挙では、尹錫悦と大統領選を闘ったが、僅差で敗北した。その後、国会議員(2022年6月~)となり、党代表となった。これまでは「韓国のトランプ」と称されるほどの発言ぶりで、対日問題でも日本に批判的だった。日本のマスコミからは反日政治家と見られていた。しかし、最近は「中道保守」を自認し、歴史問題でない経済や文化問題では日韓協力もありえると現実主義に変更しつつある。南北問題では、尹錫悦政権で南北の軍事対決が高まったことから、南北対話の必要性を主張している。
李在明政権のスタートは尹錫悦大統領が使っていた大統領官邸を使用して始まった。尹錫悦が従来の大統領官邸・青瓦台を廃止し、新たに龍山に大統領官邸を設置して無駄遣いと批判されたため、とりあえずは節税のために大統領官邸から始めたという。しかし、ゆくゆくは青瓦台に戻ることになるだろう。
李在明政権は、政権支持率70%、与党「共に民主党」の支持率50%といったところから政権をスタートさせた。さらに、国会勢力では過半数以上を与党が占めている。総選挙は4年に一度行われるから、2028年春まではこの国会勢力が維持されることになる。また、不安材料として司法リスクがある。すなわち5件の裁判を抱えていたが、そのうち2件は任期中の停止が明らかになっているものの、3件について司法リスクという爆弾を抱えることになった。
新政権の人事では、側近の姜勲植議員(51)を大統領秘書室長に抜擢した。大統領秘書室長は政権のN02に当たるが、それほどの政治力を発揮する存在とはならないようだ。次に首相候補として金民錫議員(60)を指名した。彼はソウル大時代には全国学生総連合議長となり、1985年にはソウル米国文化院占拠籠城事件に関与して拘束され、1996年に32歳で国会議員となり今日に至る。学者や官僚上がりではなく、いわゆる「運動圏」出身だ。同様の経歴を持つ人物として金栄訓雇用労働部長官がいる。彼は元民主労総委員長で、指名を知ったのは運転士として列車を運転しているときだったという。現役の鉄道労働者だ。尹錫悦前大統領が拒否権を発動した「黄色い封筒法=労働法2・3条改正法案」がどうなるか注目される。対朝鮮対応の要となる統一部長官には鄭東泳(71)が指名された。キャスターから政治家に転身し、盧武鉉政権下では統一部長官を努め、金正日と電撃面談したことで知られる。国防部長官には安圭佰議員が指名されたが、朴正煕のグテーター以降続いていた軍人出身を覆して文民長官となる。外務部長官には文在寅政権で外務次官などを努めた趙顕が指名された。李在明政権の主要人事から分かるのは、いわゆる運動圏や盧武鉉政権や文在寅政権の関連者が登用されていることである。次官以下の人事ではその傾向が顕著になると思われる。主要な人事は一月後には出揃った。
さて、李在明政権の課題は何なのか。
第一に、再び「反乱勢力」を跋扈させないこと。「反乱勢力」の中心は野党「国民の力」だが、解体するわけにはいかない。それは民主主義を否定することになる。文在寅政権が「キャンドル革命」から生まれたように、李在明政権は「光の革命」から生まれた政権である。文在寅政権は、朴槿恵事件のような事態を防止するために検察改革を行い、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)を設置した。李在明政権は、尹大統領による非常戒厳令布告のような事態を再び起こさないために、いかなる政策が必要なのか。徹底した民主主義の確立は言うに及ばず、大統領権限の制限あるいは憲法改正が必要かも知れない。尹錫悦政権で検事総長になった沈雨廷(54)が6月1日に辞任した。新政権の検察改革に異議ありという理由だ。また、尹錫悦によって拒否権を行使されたもののうち、C上等兵特権法、内乱特権法、金建希特権法が可決された。大統領夫婦の不正を糺すとともに、韓国軍の隠蔽工作を明らかにするためだ。この特権法による捜査が「反乱勢力」一掃の第一歩になるだろう。
第二に、低迷する韓国経済の活性化。李在明大統領は6月26日、国会での施政演説で補正予算について言及した。戒厳騒ぎやトラップ関税のなか、消費が低迷し、物価高に苦しむ韓国経済を活性化することが急務と述べた。30兆5千億ウォン(3兆3千億円)の補正予算を提案した。消費を活性化するために国民一人当たり15万ウォンの商品券を配布する計画。また、債務返済困難者への救済措置がある。この政策によってGDPの押し上げになると試算している。法案は「国民の力」議員が反対するなか、6月4日に成立した。
第三に、少子化対策。韓国の生涯出生率はOECD最低の0・72となっている。ソウルに限って言えば、0・55だという。国民の51%が首都圏に居住している韓国では、この数字は驚くべきものだ。このままいくと、人口減は避けられず、経済力の弱化を招くのは避けられない。国家の存亡にかかわる問題である。理由は複合的であり、社会体制の改革が行われなくてはならない。住居費の高騰、若者の就職難によって結婚できない状況があり、さらに子弟の教育費負担が大きいことから、少子化になってしまう。また、女性の社会進出と高学歴化のために結婚や育児を躊躇うケースが増えている。根強い男女の役割分担意識も少子化をもたらしている。したがって、社会の抜本的な改革なしには少子化は解消されない。長期的展望に立った対策立案に着手しなくてはならない。
第四に、実用主義的外交の展開。就任早々に米国トランプ大統領、中国習近平国家主席、石破首相とそれぞれ電話会談を行って外交をスタートさせた。尹錫悦前大統領の不在で首脳外交は久しぶりのこと。カナダで行われたG7首脳会合に呼ばれ、早退したトランプ大統領との対面はできなかったが、石破首相とは対面会談を行った。反日と言われているだけに、日本を「重要なパートナー」と持ち上げる気の使いようだった。NATO首脳会談には石破首相とともに欠席した。アメリカのイラン攻撃直後だったこともあるが、中国やロシアへの配慮と思われる。尹錫悦前大統領が「自由と民主主義」という理念を重視していたのに比べ、新政権の基調は「実用主義」と呼ばれ、国益重視である。「自由と民主主義」を掲げたバイデン政権とそれに追随する尹錫悦とは違って、トランプ政権の自国第一主義路線にも通底する路線であるといえる。
どうなる南北関係
新政権がスタートしてまもなく、38度線周辺で行われてきた市民団体による朝鮮体制批判ビラ散布の中止、拡声器に宣伝放送が中断された。李在明大統領は「吸収統一はしない」と明言し、ともに繁栄することを望んでいる。それを受けて朝鮮は汚物風船と騒音放送を中止した。しかし、新政権に対する呼びかけやコメントは出されていない。南北協力事業も新政権になっていくつか認められた。韓国では現在、2018年に結ばれた軍事分野合意が効力停止状態にあるが、まずは民間交流の立て直しということだ。さらに、スポーツ・文化交流、離散家族面会などの人道問題の再開が望まれる。こうした事業促進の向こうに、軍事分野合意の再開があり、そのための軍事会談が必要になるだろう。
これまで南北の交流・協力事業を進めてきたのは、金大中、盧武鉉、文在寅の政権であり、「共に民主党」の系列である。しかし、これまで交流・協力事業の南北合意が行われていたものの、具体的な前進はなかった。特に、2018年の米朝会談と南北会談が実現したが、2019年2月の米朝ハノイ会談が「物別れ」に終わると、全てが止まってしまった。朝鮮は2019年末に、「正面突破戦」を宣言する。「正面突破戦」とは、交渉で制裁等を獲得するのではなく、強硬姿勢で相手に認めさせることである。さらに、2023年末頃から「二国家論」を提起し、韓国との関係を「統一に向かう特殊な関係」から国家関係に転換した。南北の道路・鉄道を遮断し、国境を要塞化し、統一事業を推進する組織を廃止した。しかし、韓国が攻め込んできたら、平定するだろうという。したがって、「敵対的二国家論」といえる。これらの朝鮮の方針は、基本的に自力更生路線と呼ばれている。南北の交流・協力の促進は、韓国による吸収統一を招き、韓国文化の朝鮮への浸透は避けられず、朝鮮の体制危機を招くと判断している。こうした自力更生路線による社会主義建設にあっては、何よりも米韓の戦争挑発から自由になる必要がある。国力と通常兵器の劣勢にある朝鮮は、核保有とミサイル開発が戦争抑止力になると判断している。さらに、ロシアとの軍事同盟の締結とウクライナ戦争への朝鮮軍派兵は、朝鮮半島有事へのロシアの後ろ盾を確保するものだ。核保有による軍事力強化によって平和的な社会主義建設が可能になると考えている。
しかし、韓国が同胞でなくなり、敵対的な隣国であったとしても、隣国韓国との友好的な関係は必要なことだ。朝鮮は当然にも李在明新政権を歓迎している。軍事緊張は緩和され、交流・協力への再転換が可能になるからだし、過重な軍事費負担から解放されるだろう。重要なことは米韓共同軍事演習がどのような規模と頻度で実施されるかである。朝鮮は来年、国防5か年計画を終え、第9回党大会が予定されている。韓国が、そしてトランプ政権がどのような対応を見せるか注視している。韓国の新政権やトランプ政権の対応を見ながら、新たな外交政策を確定するものと思われる。韓国の新政権の対応によっては南北の対話再開もありえるだろう。朝鮮半島の新冷戦構造のなかで今後の対応が注目される。
おおはた・りゅうじ
1952年北海道釧路市生まれ。弘前大人文学部、釜山大日語日文大学院を卒業。日本語教師として韓国、中国に居住経験あり。朝鮮半島問題、中国問題でのレポート、論考多数。共訳書として『鉄条網に咲いたツルバラ』(同時代社)、『オーマイニュースの兆戦』(太田出版)、『朝鮮の虐殺』(太田出版)。
論壇
- 「日本人」の主食は米であったのか?歴史民俗資料学研究者・及川 清秀
- 「国民主権政府」李在明政権の時代へ朝鮮問題研究者・大畑 龍次
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(下)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- 先史日本は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦
- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(中)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 「ウソと暴力」が壊す人権と民主主義ジャーナリスト・西村 秀樹
- 寄稿ヒロシマ、神学者が綴った悲歌と愛同志社大学大学院教授・小黒 純