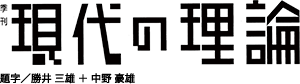特集 ● いよいよ日本も多極化か
外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相
防衛費GDP比5%、経済成長路線に賭ける新政府
在ベルリン 福澤 啓臣
Ⅰ つまずきながらもメルツ新政権がスタート
メルツ内閣の紹介 / 積極外交で評価されるメルツ首相 / GDP比5%の防衛予算
Ⅱ 課題が山積する内政、特に成長路線への復帰では
Ⅲ 偉大な国民政党SPDの凋落
Ⅳ 議会夏休み前の政治状況
メルツ首相が避けたかった与党内の衝突が現実に
2025年5月6日に発足したメルツ新政権、外交では存在感を発揮しつつあるが、内政では苦労している。特にドイツは、相変わらずプーチンとトランプによって大きく翻弄されている。2022年のプーチンによるウクライナ侵攻によって、30年間続いたヨーロッパの安全保障体制は根本的に崩壊した。それに加えて、今年就任したトランプ大統領の下では、米国の防衛協力には頼れなくなるという状況が重なっている。このため、特にドイツは、防衛予算を昨年までのNATO基準の2%をはるかに超える、GDP比5%にまで引き上げることに同意した。2、3年前まで想像もできなかった数字である。同時にメルツ政権は、経済停滞からの脱却に向けて様々な政策を打ち出している。これらの困難な政治、防衛、経済状況の中で外交では一定の成果を上げつつあるメルツだが、議会では出足でつまずき、その後も内政では苦労している。
Ⅰ つまずきながらもメルツ新政権がスタート
フリードリヒ・メルツは、5月6日の連邦議会における首相選出投票で賛成票が310票に止まった。630票の過半数、すなわち必要な316票に6票足らなかったのだ。再投票は三日後の金曜日に予定されていたが、翌日にマクロン仏大統領、さらにポーランドのトゥスク首相との会談が予定されていた。影響があまりにも大きいとみられ、与党側は「同日に改めて投票できないか」と動き始めた。ただし、それには議事運営の変更が必要で、議会の三分の二の同意が求められた。まず緑の党は、賛成したが、それだけでは足りず、左翼党にも協力を打診することになった。左翼党の幹部の携帯番号を探したところ、CSUの内務大臣候補のドブリントが番号を持っていたので、連絡を取り、なんとか同意を得ることができた。こうして午後に急遽二回目の投票が行われ、325票の賛成が得られた。やっとメルツ首相が誕生した。
戦後のドイツでは、首相はこれまで一回の投票で選出されてきた。そのため、メルツ首相は就任当初から大きな躓きをしたことになる。注目されたのは、この造反票がどこから出たのかということだ。連立政権を取りまとめたSPDのクリングバイル党首に反発するSPDの議員によるものなのか、あるいはメルツの「債務ブレーキの大変身」を裏切りと見るCDUの議員の造反なのかと、憶測が飛び交ったが、真相はいまだにわからない。
この造反票の存在そのものが、今後の政権運営にとってのリスクを含んでいる。どこに地雷―造反議員―が潜んでいるかわからないからだ。現在与党の議席数は、過半数をわずか12議席上回るにすぎない。今回のように18名の造反がでれば、法案は否決されてしまう。与党内に潜む「地雷」の存在が、メルツ首相政権の大きな脅威となっている。
メルケル元首相が傍聴していたが、メルツ首相が成立しないのを見て、首を横に振り、席を去った。かつて彼が首相の座を目指し、彼女に二度敗れた経緯を思い出していたのかもしれない。
メルツ内閣の紹介
メルツ内閣は、首相を含め18名で、男性が10名で、女性は8名。平均年齢は53歳(日本の石破内閣は、20名で、女性は2名。平均年齢は63.5歳)。最年長はメルツの69歳。防衛大臣のピストリウス以外は、全員が新人なので、新規の政策案を提出するにはそれなりの時間がかかるだろう。とりあえず閣僚の中から特に注目されている二人の女性を紹介したい。
メルツ政権の最大の課題は、停滞するドイツ経済を再び成長路線に復帰させることだ。それには、経済大臣の力が大きく左右する。そのためにメルツ首相は経済界で実績のあるカタリーナ・ライヒェ(52歳)を経済・エネルギー大臣に登用した。同氏は、化学の博士号をもち、98年から15年までCDUの連邦議員としての経歴後、エネルギー大企業のCEOを務めた。環境重視の緑の党のハーベックの後を受け、規制緩和によって経済成長とエネルギー政策の調整が期待されている。
次に 建設・都市開発大臣に就任したヴェレナ・フーベルツ(37歳)は、2021年に初めて連邦議員に当選した若手のSPD政治家だ。様々な企業に勤務した後、スタートアップを創業するなど、ビジネス面で多様な経歴を経てきた。深刻な住宅不足・インフラの老朽化への対応が緊急の課題だ。これまで5年もかかった建設配置計画の認可を2ヶ月に短縮するなどの政策を目標に掲げている。
デジタル化の遅れに対応するために、特に新たに「デジタル国家改善省」が創設されたことを付け加えておく。
積極外交で評価されるメルツ首相
メルツ首相は就任直後からパリ、ワルシャワ、キーウと飛び回り、首相外交を続けている。特にキーウではフランスのマクロン大統領、英国のスターマー首相、ポーランドのトゥスク首相の四人で同時訪問し、ゼレンスキー大統領を励まし、最大の支援を約束した。会談中にマクロンがトランプに直接電話した。ワシントンは朝の6時だったが、電話に出たので、四人は大いに意気が上がった。
6月5日にメルツはワシントンを公式訪問した。カメラの前で、トランプに特におもねることもなく、45分間の会談中ほとんど大統領に話させて、破綻もなく過ごせた。国民やマスコミの間では一応及第点をもらっている。メルツはトランプへの手土産として、大統領の祖父フリードリヒ・トランプの出生証明書のコピーを持参した。フリードリヒ・トランプは1869年にドイツのカルスシュタットで生まれ、16歳の時に米国に移住した。大統領はこの贈り物に喜び、ホワイトハウスに飾っておくと言っていた。
二人は馬が合うらしく、ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、会談後互いに携帯番号を交換したとされている。二人は時々この電話による意見交換をしているそうだが、公にはなっていない。
2週間後にはカナダでG7サミットが行われ、二人は再会したが、特に意味のある話し合いはされなかった。
引き続いてメルツは6月24日と25日にオランダのハーグで開かれたNATO首脳会議に出席した。そこで、各国は防衛予算を2035年までにGDP比5%(ドイツの場合2025億ユーロ。1ユーロ150円で換算すると34兆円になる)に引き上げるという目標に合意した。法的拘束力は持たないが、35年と目標年が記されている。最後の数年で目標達成するという駆け込み達成を避けるために、ルッテ事務総長の強い意向で、各国が斬新的に達成できるように年次計画を提出することが決められた。5%のうち3.5%が武器などの純粋な軍事予算で、残りの1.5%は重い戦車が走れる橋梁などへのインフラ投資である。トランプ大統領も出席し、ヨーロッパのメンバーの5%への引き上げを歓迎していた。以前から「自国の防衛予算を惜しんでいるNATOメンバーには米国は軍事支援を行わない」、と宣言していた。
GDP比5%の防衛予算
トランプ政権は、世界戦略の軸足をヨーロッパからアジア・太平洋に移している。最大のライバルである中国に全ての力を注ぎたいのだ。だから、ヨーロッパの紛争や戦争は、ヨーロッパが自分たちで、対応しろ、とオバマ、バイデン大統領以来の要求を、より直接的な発言で要求している。
歴史的な背景を辿ってみると、ドイツは冷戦終了後、仮想敵国もいなくなり、防衛予算を大幅に削減できた。そして、その分を平和の配当として福祉予算に振り分けて、豊かな社会を築いてきた。このような経緯は、トランプから見れば、「米国が国民の血税を使って、安全保障面で守ってあげている間に、福祉関係を充実させてきたドイツは、米国を騙して、自分たちだけ豊かにしてきたずるい奴だ」となる。その反動が現在来ているのだから、5%の防衛予算は仕方がない、あるいは当然だという声が、ドイツ国内で高まりつつある。国民の間でも、ZDF(第二公共放送)の6月の世論調査では、防衛予算GDP比5%の目標合意に65%が賛成している。
その時よく引き合いに出されるのが、東方外交を進め、東側との平和共存の基礎をつくったブラント首相時代(1969年から1974年)の軍事予算だ。当時GDP比3.8%だった。それもドイツ軍(ドイツ連邦共和国、つまり西ドイツの軍隊)の50万人に加えて、米国(27万人)を中心に英国(7万人)とフランス(5万人)の駐留軍が、西ドイツの防衛をガッチリ固めていた上での3.8%だったのだ。それもあってか東方外交は成功し、1975年の「ヘルシンキ宣言」(「全欧安全保障協力会議」はヨーロッパの安全保障・協力・人権尊重を定めた国際合意)、「デタント」と東西の緊張緩和の時代が到来した。つまり、強力な軍事抑止力を背景に平和外交をしないと成功しない、という教訓が読み取れる。
軍隊や兵器生産の拡大のために、ドイツは、債務ブレーキを緩和し、潤沢な予算を用意している。だが、この30年間に及ぶ平和の時代に、ドイツの軍需産業は生産能力を大幅に縮小してしまったので、復活するにも簡単ではない。その上、どのような兵器を重点的に生産するかも決まっていない。これまでドイツの兵器会社は、レオパルドなどの戦車生産を得意としてきたが、現在のウクライナ戦争をみる限り、20世紀の主力兵器であった戦車の時代は過去になりつつある。数億円の戦車が数万円のドローンで破壊されているのだ。ショルツ首相が宣言した「時代的転換点」があらゆる分野でドイツ社会を襲っているが、兵器体系もその只中にいると言ってもいいだろう。
その上、兵器が揃っても、それを使うのは、人間だ。ドイツの若者(男女)が、自国防衛のために武器を手に取って戦う気構えがどこまであるかが、最大の問題だとみなされている。メルツ首相は首相就任後、「ドイツの軍隊を通常戦力としてヨーロッパ最強に育てる」と何度も宣言しているが、「仏作って魂入れず」になるのではという懸念の声も聞こえる。
メルツ首相は前任者のショルツ首相に比べて、積極的に発言するーポカも時たまあるがーので、評判がいい。ヨーロッパで人口も経済も最大国として、ヨーロッパ及びEUを引っ張っていくという自覚があり、リーダーシップを発揮している。ドイツをヨーロッパ最強の国にするという発言も、そのように捉えられて、評判は悪くない。
Ⅱ 課題が山積する内政、特に成長路線への復帰では
新政権の最大の課題は、停滞が続くドイツ経済の成長路線への復帰だ。とにかく経済が成長しない限り、豊かな社会は次第に崩れていくという恐怖のシナリオが描かれている。ドイツのような、高度工業社会で、国際競争力が失われると、経済成長が止まり、不況になってしまう。すると雇用が失われ、経済危機から、社会危機にまで発展する。その結果、悪循環に陥り、国として衰退してしまう、というのがシナリオの暗い続きだ。成長のない循環社会やコモン社会(市場や国家に頼らず、市民が社会資源を共有・管理する社会)を目指すべきだという意見もある。だがそれは、地域レベルでは可能だろうが、現在のドイツ全体に関しては、全く現実性がない。すると、残るのはやはり経済の成長至上主義ということになってしまう。
この2年間、マイナス成長で、今年もほとんど成長しないだろうとつい最近まで予想されていた。なぜなら、経済の状態を測る重要な指標として「労働力」「資本投資」「総合生産性(TFP)」があるが、3指数ともここ数年鈍化しているからだ。
そのため経済に明るいとされる首相のメルツが先頭に立ち、経済界で実績のあるライチェ経済大臣という陣容で、ドイツ経済を立て直そうとしているわけだ。
ドイツの労働力は減ってきている。現在、ベビーブーマー時代(1954年から1969年)の労働人口が次々と年金世代となり、2035年までには約2000万人が労働市場から退出する。同期間内の労働人口の流入は、1250万人と見積られているので、750万人の喪失になる。それに対して、メルツ首相は、ドイツ人に「より働け」と鼓舞しているが、組合などからは、「みんな一生懸命働いている。それよりも、保育所など充実させて、女性の進出を容易にするなど、政策的に対応するすべきだ」などと反論されている。国民の間でも、評判が悪い。政府は、年金受給者が働いた場合、無税にしたが、抜本的な政策とは言えない。
資本投資促進には、まずインフラやデジタル化の公共投資の拡大、規制緩和、エネルギーコストの引き下げで対応しようとしている。公共投資の拡大には、政権発足前にメルツは「インフレ・気候ファンド」を創設し、10年間で80兆円と予算を確保している。さらに機械・設備の新規投資に対し30%即時償却(2025–27)と連邦法人税率15%を10%に段階的に引き下げることを決めた。だが、問題は、これらが呼び水となって、果たして投資の9割を占める民間投資が動き出すかだ。
「総合生産性(TFP)」の促進には、行政手続きのデジタル化・簡素化、産学連携促進、R&D強化を掲げている。
ドイツは日本と同様に資源に乏しい。唯一あるのは、人的資源である。その資源を豊かにするのは、教育及び研究体制である。2015年から25年までの文教支出は、19兆円(1ユーロ150円で換算)から29兆円と67%伸びている。研究費も、2兆5千億円から3兆3千億円と32%も伸びている。
ドイツの高等教育は、充実している。筆者も恩恵を受けたが、国立大学(272校。私立大学は130校)は無料なのだ。大学間移動も自由だし、大学入学資格(ギムナジウム卒業)さえ持っていれば、何歳になっても、大学に試験なしで入れる。ドイツの大学は留学生にとっても非常に魅力あるので、現在外国人学生は、50万人弱で、全学生287万人に占める割合は、17%(日本は4.3%)だ。この数は昨年に比べて5%増えている。24年度の新入学生においては、30%も外国人学生が占めている。
研究機関も充実している。国際的に評価の高い研究機関として基礎科学にマックス・プランク研究機構(予算:3000億円、人員:17000人)と国家的・社会的課題にヘルムホルツ研究機構(予算:8000億円、人員:3万6千人)が全国的に展開している。
トランプ政権が米国への留学生や研究者に対して歓迎しない政策を実施しているので、ヨーロッパ、特にドイツなどへの留学生および研究者がますます増えるだろうと予想されている。
高等教育や研究のための環境は優れているが、問題は、次のステップとしてのスタートアップへの「ベンチャーキャピタル市場」が米国や英国などに比べて小さいことだ。お金の扱いに慎重なドイツ人の国民性が反映している。
ドイツの景気動向が、主な経済研究所の予想によると、最近上向けに振れてきた。複数の研究所が26年の成長率を1.6%と予想している。投資傾向も「インフレ・気候ファンド」を創設、企業の投資に対する減税措置、加えて米国経済の不安定化に伴って、回復するだろうと見られている。
メルツ政権にとって次の大きな課題は、選挙公約で掲げた通り、難民を国境で追い返し、その流入を止めることである。新政権誕生後、ドブリント内務大臣は早速連邦警察に指示を出し、国境での交通を管理し始めた。
これは、人・モノ・資本の自由な移動を保障する「シェンゲン協定」に違反する措置だが、同大臣は「国内の緊急事態のため、やむを得ない」と主張し、内外からの批判を無視して国境管理を継続している。
7月に入ってからは、隣国ポーランドも難民を国境で送り返すようになった。
現在、EU単一市場の前提となるシェンゲン協定を無視している国は10カ国に上り、人とモノの自由な往来が困難になっている。
ここで少し話は変わるが、メルツ首相にとって少し頭の痛いことがある。二人三脚を続ける副首相のクリングバイルのSPD党内受けとジュニア・パートナーとしてのSPDの支持率が低いことだ。これでは、政権の安定が保たれない。ショルツ政権が与党三党間の不協和音で、国民の信頼を失ったが、その二の舞は絶対避けたいところだ。
Ⅲ 偉大な国民政党SPDの凋落
戦後政治を支えてきた国民政党・SPDの凋落が著しいが、現在の政局、党内の力学、そして歴代首相の軌跡を通して検証する。
SPDは2月の連邦議会選挙で、16.4%の得票率という戦後最低の結果に終わった。本来なら野党として野に下るべきだった。だが、同盟党(CDU・CSU)が極右AfDとの連立を拒む中、他の選択肢がなく、SPDはメルツ内閣のジュニア・パートナーとなった。政権発足から二ヶ月以上経つが、SPDの支持率は14%と低迷が続いている。
6月27日からの党大会では、復活の道を議論するため、600名の代議員が集まった。まず共同党首のクリングバイル(副首相兼財務大臣)とバース(前連邦議会議長で労働社会大臣))の信任投票が行われた。
クリングバイルは64.9%と惨敗とも言える結果だった。一方、左派を代表するバースは95%と圧倒的な支持を得た。
クリングバイルは、選挙大敗の責任を取らないまま、さらに院内総務のポストも手にした。しかし党内基盤が強いとは言えない。連立交渉でSPDの閣僚ポストを5人も確保した実績は評価されていない。ちなみに、7月のARD(第一公共放送)による政治家人気投票では、2位につけており、国民の間では人気がある。
党大会では、バースは、階級闘争的なスローガンを掲げ、格差是正を訴えた。しかし、連立を組むCDU・CSUは富裕層への課税―財産税の導入―と増税―所得税で富裕層への課税強化―に反対している。それどころか福祉予算の引き下げを要求している。労働社会大臣のバースには国家予算の36%を賄う巨大省庁が任されているが、CDU・CSUの攻勢をどこまで防げるか、彼女の政治的手腕が問われる。さらに、年金制度を支える年齢層の大幅な減少により、将来の年金予算の財源確保が、深刻な問題として立ちはだかっている。
SPDは、憲法擁護庁が極右政党と査定したAfD(ドイツのための選択肢)の禁止を前向きに検討する決議を採択したが、これは党内結束を図るためのパフォーマンスだとの見方も出ている。
SPDの凋落はドイツ固有の現象ではなく、イタリアやフランスなどと同様、欧州全体の社会民主主義が直面する構造的試練を反映している。その背景には、経済や社会の変化、ポピュリズムの台頭、文化的分断などが背景にある。
以下のように戦後のSPD首相たちは、時代ごとの課題に応じて、大胆な政策を実現してきた。その足跡を簡単に振り返ってみよう。
1. ヴィリー・ブラント(首相任期:1969–1974。1972年には得票率45.8%)は冷戦時代に東方外交を掲げ、旧東ドイツや東欧諸国との「和解と接近」の方針を推進した。社会改革では、教育・福祉・住宅・家族政策などの分野で、様々な社会改革を実施した。特筆すべきは、これらの改革が、68年世代と称される学生運動の求めた民主化や社会改革に沿った方向で行われたことだ(日本の全共闘運動に対する佐藤内閣の徹底的な弾圧政治とは対照的だ)。
2. ヘルムート・シュミット(1974–1982。1976年に42.6%)は、赤軍派(RAF)のテロ活動に対して毅然とした対応を取り、治安を維持した。国際的には、1979年、国内の大きな反対を押し切って、欧州への核中距離ミサイル配備を受け入れるNATOの「二重決定」に賛成し、西側の抑止力を支えた。
3. ゲアハルト・シュレーダー(1998–2005。98年には40.9%)は、2000年に原発の段階的廃止を決定し、再生可能エネルギーの導入を促進した。経済的には欧州の病人とまで言われたドイツを、労働市場の抜本的改革(ハルツ改革)を行い、失業率を大幅に低下させた。
4. オラフ・ショルツ(2021–2025。21年の得票率25.7%)は、2022年にロシアがウクライナに侵攻した後、「歴史的転換点」を宣言し、国防力増強へと大転換した。ロシアからの化石燃料の供給が止まった上に、緑の党と自民党による三党連立政権がうまくいかず、任期前に解散した。
このように見てみると、SPDが4年間の任期をまっとうできるのか、心配になってくる。クリングバイル、あるいはバースはSPDの救世主になれるのか、夏休み以降の与党内及び国会の攻防が山場になるだろう。
Ⅳ 議会夏休み前の政治状況
7月9日に議会が再会し、25年度の予算案が審議された。メルツ首相に対して、ヴァイデルAfD党首は、のっけから「嘘つき首相」と真っ向から決め付けた。債務ブレーキの選挙公約違反に加えて、連立協定でエネルギー費用の負担軽減として、電気税金の引き下げを国民に約束したが、大企業にだけ軽減し、中小企業や国民には、つい数日前に財源(8000億円)がないと言って、結局見送ったことを批判したのだ。
7月14日から連邦議会は夏休みに入った。閣僚も議員たちも首都を離れ、休暇を過ごす。その前に2月24日の総選挙での得票率と7月に入ってからの政党の世論調査による支持率を見てみよう。
| CDU/CSU(%) | AfD(%) | SPD(%) | 緑の党(%) | 左翼党(%) | |
| 総選挙 2/24 | 28 | 21 | 16.5 | 12.6 | 8.8 |
| IPSOS 7/10 | 26 | 24 | 15 | 12 | 12 |
| INSA 7/14 | 27.5 | 23.5 | 15 | 11 | 10.5 |
| FORSA 7/15 | 26 | 24 | 13 | 12 | 11 |
出典=DAWUM
AfDと左翼党が相変わらず伸びている。SPDの低落傾向は明確だ。この2ヶ月の間は、議会が夏休みなので、大きな変化はないと見て、原稿を締めくくろうとしたら、事件が起きた。
メルツ首相が避けたかった与党内の衝突が現実に
夏休みの前日(7月11日の金曜日)に、議会で思わぬ波乱が起きた。憲法裁判所の裁判官の任命を巡って、与党内で両党が衝突したのだ。国民の間で最も信頼されている憲法裁判所の裁判官は連邦議会が決める。政党が推薦し、議員の三分の二が賛成すれば、任命される。
憲法裁判所の裁判官は、任期12年間で、16名で構成される。3名の席が空いたので、選ぶことになっていた。3名の人選はすでに終わっていて、本来なら、形式的な投票で済むはずだった。
ところが、SPDが推薦したブロジウス・ゲルスドルフ教授(ポツダム大学)の任命に対して、CDU/CSUの議員の中に数十名の反対者がいると見られ、投票日の朝になってCDUからSPDに、「採決を延期したい」との連絡が入ったのだ。そのため、3名の任命は見送られ、議会は収拾がつかなくなった。週末明けの月曜から議会は夏休みに入るので、任命は休み明けの9月10日以降まで延期の見通しだ。このような与党内混乱は、メルツ首相が最も避けたかったことだ。
この問題はドイツの刑法218条(妊娠中絶の原則禁止)と結ばれていて、根が深い。ドイツでは、驚くべきことに、妊娠中絶は1878年以来禁止されていて、中絶をした医者は刑事罰の対象とされてきた。
68年世代の女性解放運動は激しく抗議し、廃止または改正を求めたが、実現しなかった。当時はドイツの女性は中絶のためにオランダなどに出かけなければいけなかったのだ。やっと1995年に改正されて、例外として12週間までの妊娠ならば、一応認められるようになった。それでも中絶それ自体は、禁止されている。実刑を課せられた医者が何人もいる。
中絶に強く反対しているのは、主にカソリック系の宗教団体で、母体に宿った命を断つことは、「殺人に等しい」とまで主張している。そして、ブロジウス・ゲルスドルフ教授は極左活動家だとして、強く反対している。同教授は、確かにリベラルな意見の持ち主だが、政府の審議会のメンバーに任命されているほど、学者として評価されている。その上、複数の世論調査によれば、国民の80%以上が、現在の218条による中絶禁止及び犯罪規定は廃止するか、根本的に改正されるべきだと述べている。
ドイツの議会は、夏休みに入ったが、国際政治はそうもいかない。早速、昨日ワシントンから重要なニュースが飛び込んできた。
1式あたり1500億円とされるパトリオット対空防御システムを、トランプ大統領がウクライナへの供与に同意したというのだ。ドイツが2式を、他のEU諸国が3式を購入し、ウクライナに引き渡す計画だ。これはNATOのルッテ事務総長とトランプ大統領との会談の場で発表された。さらに高性能兵器も同様にヨーロッパのNATO加盟国が購入し、ウクライナに引き渡す見込みだ。報道によれば、この動きの背後には、ルッテ事務総長とメルツ首相による根回しがあったそうだ。
このトランプ発言が実行されるならば、ウクライナや欧州にとって多少明るい材料となる。早期に停戦が実現すれば、ドイツにいる約125万人ものウクライナ難民の帰国が可能になる。ドイツにとっては財政負担の軽減と社会的圧力の緩和につながる。
こうした複雑な内政問題を抱えたメルツ政権は、外交面でも新たな試練に直面している。7月12日に、トランンプが、EU製品, もちろんドイツ製品に対しても、8月から30%の関税を課すと発表した。これが導入されれば、ようやく兆しが見えてきたドイツ経済の回復の芽は、摘み取られてしまうだろう。EUのフォン・デア・ライエン委員長とメルツ首相が、この関税問題にどう対処するのか、注目されている。
7月18日に恒例の首相夏季記者会見が行われた。まずメルツ首相が新政権の2ヶ月半になる政権運営について約12分間語り、社会福祉財政が厳しい状況にあるとして、国民にさらなる自己責任を求めた。そして、この期間の新政権の政権運営はおおむね良好だったと自己評価した。
その後、約80分間にわたって記者たちの質問に答えた。質問は主にブロジウス・ゲルスドルフ教授(ポツダム大学)の憲法裁判所裁判官任命問題に集中した。首相は、「自分たちはもっとうまく対処すべきだった」と反省を述べたものの、「これは政権の危機ではない」との認識を示した。その他さまざまな政策についての質問に答えた上で、最後には「ドイツは困難な状況にあるが、少しずつ改善している」と述べ、楽観的な姿勢で締めくくった。
(2025年7月19日 ベルリンにて)
ふくざわ・ひろおみ
1943年生まれ。1967年に渡独し、1974年にベルリン自由大学卒。1976年より同大学の日本学科で教職に就く。主に日本語を教える。教鞭をとる傍ら、ベルリン国際映画祭を手伝う。さらに国際連詩を日独両国で催す。2003年に同大学にて博士号取得。2008年に定年退職。2011年の東日本大震災後、ベルリンでNPO「絆・ベルリン」を立ち上げ、東北で復興支援活動をする。ベルリンのSayonaraNukesBerlinのメンバー。日独両国で反原発と再生エネ普及に取り組んでいる。ベルリン在住。
特集/いよいよ日本も多極化か
- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生
- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子
- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京
- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀
- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣
- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆