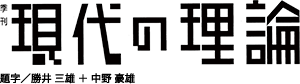論壇
先史日本は高校でどう教えられているのか
高校「日本史」教科書を読む
元河合塾講師 川本 和彦
1 はじめに
ここ数年、縄文ブームが続いているとされる。2025年に国立科学博物館で「古代DNA〜日本人のきた道」展が開催され、私も足を運んだ。発掘された頭蓋骨から復元された像があり、縄文時代の男性像は俳優の高橋克典さんに、弥生時代の男性は綾野剛さんにそっくりであった(かっこ良すぎるかも)。女性像はなかったが、想像するに縄文時代の女性は国仲涼子さん、弥生時代の女性は宮﨑あおいさんのようではなかったか(かわいすぎる気もするが、個人の妄想であり、ご容赦くださいませ)。
商業的な一面を持つブームに、教科書が直接の影響を受けるわけではない。だが教科書執筆および検定が、社会の動きとまったく無縁ではないのも事実である。
本稿ではまず、先史時代の日本に関する教科書の記述がどのように変化したかを取り上げる。続いて、旧石器時代・縄文時代・弥生時代を現在の教科書がどのように扱っているかを検証する。採択率の高さを考慮して、教科書は山川出版社『詳説日本史』を素材とした。執筆者の一人が、かつて菅内閣によって学術会議から排除された加藤陽子さんである。
2 教科書における記述の変化
「縄文」「弥生」という時代区分が中学・高校の歴史教科書で用いられるようになったのは、1950年代のことである。そして、縄文人と弥生人の混血によって日本人の原型が形成されたと多くの学者(歴史学・考古学・人類学)が考えるようになったのは、ようやく1980年代に入ってからだ。
Ⅰ 明治時代〜戦前
明治時代から戦前にかけて、日本人の形成については、以下の3説が対立していた。
❶人種交代説
日本列島の中で1回または2回人種が交代したという説で、縄文人の後に現代日本人の祖先が入ってきて縄文人と交代したと主張する。
❷混血説
縄文人の子孫が近隣の諸集団と混血して現代日本人になったという説で、多くの日本人(本土人)は中国や東南アジアの集団と混血し、アイヌは北アジア人と混血したと主張する。
❸移行説
縄文人がそのまま現代日本人に進化したとする説で、日本列島では人種の交代も混血もなかったと主張する。
『古事記』『日本書紀』が史実とされ1940年に紀元2600年を祝う時代になると、❶❷❸のいずれも教科書からは消え去るが、考古学者・人類学者間での議論は続いていた。現在の学説からすれば❷が妥当にみえるが、時代を反映して優勢なのは❸、そして❶であった。だが❷の主張が抹殺されたわけではない。
たしかに混血を否定することは、日本人の種としての純粋さを強調することになる。だが戦前の日本においては、台湾人も朝鮮人も法的には日本人であった。植民地支配を正当化する根拠として、日鮮同祖論などが唱えられていたのである。混血を過度に主張すれば日本人のアイデンティティ構築を妨げるが、全面的に否定すれば「帝国臣民」間に対立・分断が生まれてしまう。そのようないささか複雑な背景から、❷の混血説は学説の一つとして生き残り、戦後には主流となるのである。
Ⅱ 戦後――1970年代まで
1943年1月に静岡市で発掘された登呂遺跡の調査は、1946年から本格化する。1946年は、アマチュア考古学者の相沢忠洋が岩宿で旧石器を発見した年でもある。日本の先史時代における旧石器・縄文・弥生という時代区分がようやく明確になり、やや遅れて教科書にも反映されるようになった。その中で、記述が最も多かったのは弥生時代である。旧石器時代や縄文時代に比べて発掘された遺跡が多かったため、研究が進んでいたのは事実だが、それだけではない。右も左も真ん中も、それぞれの思惑を持って弥生時代に注目したのだ。
当時の研究者・教科書執筆者は、戦前までの皇国史観に縛られていた日本の先史時代を究明したいという情熱を持っていた。農耕以前の、天皇制と無関係な旧石器時代や縄文時代には、それほど関心が向けられなかったのである。
登呂遺跡には皇太子(現上皇)をはじめ、多くの皇族が見学に来ている。昭和天皇の人間宣言や、象徴天皇制を明記した日本国憲法施行の時期であり、皇室の新しいアイデンティティが模索されていた。その一環として、宮中祭祀の新嘗祭を戦前とは異なる視角から追求する必要があったのである。柳田國男が結成した「にひなめ研究会」はそういう問題意識を持って研究を進めていたが、この会の主催者は三笠宮であった。
他方、戦前の弾圧から解放されたマルクス主義は単線的な唯物史観を特徴とする。この立場からすると、弥生文化=稲作=階級社会の始まりということになり、皇族とは反対の立場から、弥生時代に注目することになる。
さらに言えば、登呂遺跡は後に発掘された吉野ヶ里遺跡と違って、戦争をしていた形跡がない。敗戦後の日本において、自分たちの祖先が平和な暮らしをしていたと思いたい心情は理解できる。
Ⅲ 戦後――1980年代以降
このような、それぞれの思惑は1970年代から変化をみせる。大阪万博における岡本太郎作「太陽の塔」は縄文文化に触発された作品とされるが、これは岡本の芸術的感覚だけでなく、政治的嗅覚が機能したのかもしれない。
変化の理由としては、まず象徴天皇制が定着したことが挙げられる。天皇や皇太子は皇室存続についての危機意識を慢性的に抱えていたかもしれないが、天皇制廃止を求める世論が盛り上がったわけではないし、今後も変わらないであろう。秋篠宮夫妻へのバッシングはあるが、これは愛子天皇待望論へ容易に転化しうるものである。対するマルクス主義は、凋落の一途を辿った。政治勢力だけの話ではない。後に網野善彦らが有名になるが、水田稲作中心の歴史観に異議を唱える歴史学・民俗学の台頭もあった。
加えて、1973年の第一次石油危機によって高度経済成長が終わる。そういう時代には経済以外の誇り、例えば歴史や文化が求められるものだ。
こうした中、二重構造モデルが確立された。現代日本人につながる集団は、基層集団である縄文人と弥生時代に渡来した弥生人との混血によって成立したとする説である。この説をいち早く打ち出したのは、国際日本文化センターに所属する学者である。同センターを発足させたのが中曽根康弘というのが何やらきな臭いが、それはともかく、高校教科書『詳説 日本史』に、次のような記述が登場した。
〈日本人の原型は古くからアジア大陸に住んでいた人びとの子孫の縄文人であり、その後、もともとは北アジアに住んでいて弥生時代以降に渡来した人びとなどとの混血を繰り返し、現在の日本人が形成された。〉
以下、教科書の問題点を列挙する。
3 旧石器時代
旧石器時代について、教科書に以下の記述がある。
〈この時代の人びとは、狩猟と植物性食料の採取の生活を送っていた。狩猟にはナイフ型石器や尖頭器などの石器を棒の先端につけた石槍を用い、ナウマンゾウ・オオツノジカ・ヘラジカなどの大型動物を捕らえた。〉
これが当てはまるのは、北海道〜九州の一部のみである。琉球列島には大型獣が生息しておらず、植物と狭い範囲で捕獲される小型動物が食料であった。先史時代に限らず、日本史の教科書はしばしば琉球列島を無視している。しかも多くの場合、悪意をもって切り捨てるのではなく最初から眼中にないらしい。それこそが最大の問題である。
4 縄文時代
縄文時代に関する記述を紹介する。
〈男性は狩猟や石器づくり、女性は木の実とりや土器づくりにはげみ、集団に統率者はいても、身分の上下関係や貧富の差はなかったと考えられている。〉
先に触れた登呂遺跡もそうだが、ご先祖様を理想化したい気持ちはなくならないようだ。残念ながら縄文時代は、それほど平和でも平等でもなさそうである。階級とまではいかないが階層があったことは、共同墓地の調査で明らかになった。
第一に、耳飾りや腕輪などの装飾品である。こういう装飾品を身に着けた遺体は1割以下であり、着けることができる人だけが着けたということだ。第二に、合同葬のあり方である。親子兄弟を同じ墓に埋葬するのは不自然ではないが、遺体数が多すぎる。主人が亡くなったとき、死後の世話をするために奴隷を生き埋めにしたと考えるのが自然であろう。
狩猟民だから無階級社会だとは限らない。北米先住民社会には、酋長も奴隷もいた。階級は、余剰が蓄積され持つ者・持たざる者が分かれることから発生する。縄文時代は完全な自給自足経済ではなく、塩や黒曜石など多くのものが交易品になっていた。教科書も、長野県産の黒曜石がサハリンへ運ばれたことを地図で示している。交易があったということは、余剰が存在したということである。
そもそも「縄文人」という語が不適切である。過去2000年の日本史を振り返ると、邪馬台国時代と現代とでは、言語も食生活も人体の骨格も大きく異なっている。ましてや1万年以上も存続した縄文時代の人びとが、単一であるはずはない。地域差・時代差からみて縄文時代は①北海道北部、②北海道南部から東北地方北部、③東北地方南部、④関東地方東部、⑤関東地方西部から中部地方、⑥北陸地方、⑦東海地方から中国地方、⑧九州地方北部から中部、⑨九州地方南部から種子島・屋久島周辺、⑩沖縄本島を中心とした南西諸島、に区分される。○の数字が1個違えば、言葉も通用しなかったと想定されている。
5 弥生時代
弥生時代の記述から引用する。
〈紀元前4世紀頃には、西日本に水稲農耕を基礎とする弥生文化が成立し、やがて東日本にも広まった。〉
現在では弥生時代の開始はもっと早かったことが判明しており、これは次の検定教科書に反映されるだろう。だが「西日本」「水稲農耕」という語句が継承されることは確実だ。そこに誤りがあるとは言えないが、偏りがあることは否定できない。
稲作そのものは縄文時代後期に、北九州や瀬戸内海地方でも始まっている。それに、弥生時代と称されるこの時代に流入したのは稲作だけではない。畑作や養蚕、織物まで入っている。今では長良川名物の鵜飼いも、このころ伝えられた。野菜の遺伝子を調べると、この時期にシベリア・ヨーロッパのカブが関東・東北・北陸に伝えられていたことがわかる。カブが歩いてくるわけではないので、ヒトが持ち込んだことになる。大陸からの渡来先は、西日本に限定されないのである。
縄文人同様、弥生人もまた多様であり、単一の存在ではない。九州だけでも ①北部九州を中心とした渡来系弥生人、②長崎県の沿岸部や離島から出土した西北九州弥生人、③鹿児島県の種子島から出土した南九州弥生人、という区分がある。
教科書には、このような記述もある。
〈弥生文化は、金属器をともなう農耕社会をすでに形成していた朝鮮半島から、必ずしも多くない人びとがその新しい技術をたずさえて日本列島にやってきて、在来の縄文人とともに生み出したものと考えられる。〉
あくまでも日本人の起源は古い縄文人であり、弥生人は添加物にすぎないと言いたいようである。しかしながら、それは無理というものだ。国立民族学博物館の研究によれば、縄文時代中期の人口は約26万人で、後期になると16万人、晩期には7万5000人へと減少した。寒冷化で食料不足になったのが原因である。これが弥生時代になると60万人、古墳時代になると540万人になる。縄文晩期から古墳時代までは、およそ1000年である。現在とは比較にならないくらい栄養状態や住環境が劣悪であった当時、1000年間で7万5000人から540万人に増加するというのは、自然増だけでは説明できない。膨大な人口流入があったとみるべきである。
6 おわりに
教科書は学問の成果を反映するものであるが、成果とともに問題点も取り上げるべきであろう。本誌41号で西村秀樹さんが指摘されている、琉球遺骨の返還請求訴訟が一例である。考古学・人類学には、真理追求のためと称して不当な発掘を行ってきた歴史がある。そのことは教室で教えられるべきだ。
また、グローバル化が進んだ現在、教室に外国籍・外国ルーツの生徒がいることは珍しくない。日本人の祖先はどこから来たのかというテーマは、人によっては歴史のロマンを感じるのかもしれないが、そこで疎外感を味わう生徒がいてはならないだろう。
ところで教科書には「縄文人」とか「弥生時代の人びと」としか書いておらず、縄文人・弥生人を民族として捉えているのか、人種として捉えているのか判然としない。意図的かどうかは不明だが、これは賢明な姿勢である。
「民族」は近代国民国家の産物という側面が強く、先史時代には不適切である。「人種」はさらに不適切といえる。人種といえば多くの人が「黒人」とか「黄色人種」とかいった肌の色を連想するが、それはメラニン色素量の違いにすぎない。より根本的な区分は、ミトコンドリアDNAの全塩基配列を用いた系統区分である。それによると人類は4つに区分され、そのうちの3つはアフリカ人だ。つまり人類は(1)アフリカ人A、(2)アフリカ人B、(3)アフリカ人C、(4)その他すべて、に区分される。私のミトコンドリアDNAは、ネルソン・マンデラよりもドナルド・トランプに近いということだ。なんたること!
それはともかく、縄文人も弥生人もそれぞれ多様な存在でありながら、同時に同じ人種でもあったのだ。歴史を学ぶ際には多様性と普遍性、個性と共通性の両面に目配りする必要があるように思う。
かわもと・かずひこ
1964年生まれ。新聞記者、予備校講師を経てフリーランス校正者。日本ブラインドマラソン協会会員。
論壇
- 「日本人」の主食は米であったのか?歴史民俗資料学研究者・及川 清秀
- 「国民主権政府」李在明政権の時代へ朝鮮問題研究者・大畑 龍次
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(下)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- 先史日本は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦
- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(中)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 「ウソと暴力」が壊す人権と民主主義ジャーナリスト・西村 秀樹
- 寄稿ヒロシマ、神学者が綴った悲歌と愛同志社大学大学院教授・小黒 純