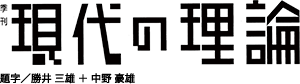追想
戦後80年、先立った友へ
追想――冨田武本誌編集委員
本誌前編集委員長 橘川 俊忠
本年の5月20日前後のことだったと思うが、富田武君から一個の小包が届いた。開けてみると、『共産党の戦後八0年――「大衆的前衛党」の矛盾を問う』と題された一冊の書籍が出てきた。数か月前、ほぼ原稿が出来上がり、年度明けには刊行できるが、その販路について相談に乗ってほしいと電話で話していた本ができたのかと思った。その時は、病状が芳しくないこと、これが遺著になるかもしれないなどとも告げられ、とにかく著作の完成を期待している、販路などできるだけの協力を約束するなどして、長い電話をきった。
その小包を開ける時、自筆らしい文字が少し乱れているように見えたが、その時は、ざっと目を通した後に連絡することにした。その翌日、新聞を見て驚いた。富田武の訃報が掲載されていたからである。前夜に目を通した「おわりに」を読み返してみた。それは、まちがいなく死を覚悟した者の文章であった。しばし瞑目して、安らかに眠れと祈るばかりであった。
* * *
富田君に、最初に出会ったのは、大学二年の時であったが、ただのシンパにすぎなかった私は、すでに立派な活動家であった富田君を遠くから見ているだけの関係であった。実際に言葉を交わすようになったのは、東大闘争が激しさを増す1968年秋ごろからで、二人ともすでに大学院への入学が決まっており、研究者への道を目指しながら、大学改革の方向をどう探るかという問題意識を共有できたからであった。
年が明けて69年は、二人にとっても激動の年になった。富田君は1月9日安田講堂前の集会で学内に導入された警察機動隊によって、ヘッドのないゴルフのクラブを持っていたため指揮者と見なされ逮捕・勾留され、私は当時所属していた憲法研究会のメンバー共々逮捕された全共闘学生の救援活動に専従することになった。1月18、19日のいわゆる安田講堂攻防戦をへて、大学闘争としての東大闘争は後退局面に移行し、卒業試験粉砕闘争、その結果としての卒業試験延期・レポート化という事態の中で、全共闘系学生は進路を問われることになった。富田君は、個人名で「立て看板」を出し、進学拒否を声明した。私は、卒業試験ボイコットの行き掛かり上、進学を諦めることにした。憲法研のメンバーで司法試験に合格していたものは、中退で司法研修所に入所した。
それはともかく、富田君は、大学院を再受験・合格し、菊地昌典教授の指導を受けることになった。そして、大学院修了後は駿台予備校講師などで見過ぎ・世過ぎをしていた。私も、塾講師などを経て、大学の同級生山田勝君の紹介で安東仁兵衛氏に会い現代の理論社に勤めることになった。その後、私は幸運にも神奈川大学に職を得、研究・教育を任とすることになった。そのなかで、比較政治論の講座を開設することになり、富田君に担当を依頼した。富田君にとっては、非常勤講師とはいえ最初の大学での講義ではなかったかと思う。その後まもなく、富田君は、成蹊大学に選任教員の職を得た。
富田君の就職が決まった時、多少の心配があった。根っからの活動家である富田君が、大学行政に深入りしないかということである。当時大学は、改革という名のもとに文部科学省からの干渉を受け、学生運動も壊滅的状況にあって、問題だらけであった。活動家でなくとも何か言いたくなる問題は山積みであった。成蹊大学の事情は分からないが、そうした問題に深入りしすぎると、折角の研究の機会を無駄にしてしまいかねない恐れがあった。老婆心ながら、富田君には「少なくとも数年は研究に専念しろ。学内であまり目立つようなことはするな」と再三忠告した。今から思えば、余計なお世話だったかもしれない。というのも、富田君の業績を見ると、ソ連の崩壊によって大量の文書が公開されたという幸運に恵まれたとはいえ、膨大な資料を読み込んだ実証的研究を積み上げており、研究者としての仕事に最大の力を注いでいたと思われるからである。
* * *
富田君の研究成果については、専門外の私に論評する能力はないが、かれの研究を支えた時代とのかかわりの意識については理解できるように思う。それは、戦後という時代認識であり、本当に反省すべきは何かを考えようとする姿勢である。1945年生まれという共通項は、専門や気質の相違を超えて深いところで作用し続けていたと思われてならない。ロシアのウクライナ侵攻以後、戦後世界の構造的破壊とでもいうべき国際社会の変貌について、ロシア研究者としての意見を聞きたかったという思いが募る。
それはともかく、いまでも富田君というと、思い出されるのは、彼の大学の同僚と三人で北アルプスの針ノ木峠を越えて黒部湖に行ったときのことである。富田君は、大学に職を得て余裕ができたせいか高校時代に山岳部だったことを思い出し、当時山登りを本格的に始めていた私をさそってくれたのである。彼は、昔カニ族と呼ばれるもとになった大型のリュックサックを担ぎ、米・タマネギ・じゃがいも・人参・肉、真鍮製の石油コンロ、鍋を持ち込んでカレーライスを作ることにした。コンロはポンピングして火をつける旧式のもので、料理を始めると、針ノ木峠小屋の宿泊者がみな珍しそうに見物する事態になった。カニ族のリュックも石油コンロも完全に時代遅れになっていたが、富田君は恥ずかしそうなそぶりも見せず、むしろ注目を集めるのが誇らしげですらあった。
編集委員としての富田君への追悼文を書くべきところ、個人的に過ぎる文章になったかもしれないが、60年にわたる友人としての心情をお汲み取りいただければさいわいである。
きつかわ・としただ
1945年北京生まれ。東京大学法学部卒業。現代の理論編集部を経て神奈川大学教授、日本常民文化研究所長などを歴任。現在名誉教授。本誌前編集委員長。著作に、『近代批判の思想』(論争社)、『芦東山日記』(平凡社)、『歴史解読の視座』(御茶ノ水書房、共著)、『柳田国男における国家の問題』(神奈川法学)、『終わりなき戦後を問う』(明石書店)、『丸山真男「日本政治思想史研究」を読む』(日本評論社)など。
コラム
- 沖縄発/沖縄戦から80年に思う沖縄国際大学非常勤講師・渡名喜 守太
- 発信/東京・杉並区政と区議会のいま―2025年春夏杉並区議会議員・奥山 たえこ
- 歴史断章/ビッグ・ヒストリーへの誘い市民セクター政策機構理事・宮崎 徹
- 追想/戦後80年、先立った友へ本誌前編集委員長・橘川 俊忠