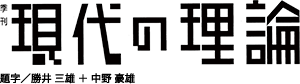論壇
「日本人」の主食は米であったのか?
“令和の米騒動”に隠された幻想の裏側
歴史民俗資料学研究者 及川 清秀
はじめに
令和の米騒動をうけ参政党の神谷宗幣代表は「やはり今、不足している米をつくることだと思います。米づくりをやっている方が人数も多いので、きちっとてこ入れをしていかないといけない。お米をつくって食べるというのが日本の国のかたちだと思います。古来からのかたちを崩してしまうと、日本が日本ではなくなってしまう。」(聞き手は(一財)食料安全保障推進財団専務理事 久保田治己氏)。と、米食=日本人を自明のように脳髄に刻み込んでいる。そして立憲民主党の原口一博衆院議員も参院選に向けて連合佐賀が開催した集会で「古古古米はニワトリさんが一番食べている。人間様、食べてないんですよ」と政府備蓄米に関する発言をして注目を集めている。(読売新聞デジタル版2025/7/08)おいしいお米=日本人の主食を前提とした主張を不可分のように論じているのである。はたして麦や雑穀を食べていた人々は「日本人」では無かったのであろうか。
さて、そもそも日本人は何を主食として食べて来たのであろうか。日本=瑞穂国は『古事記』の「豊葦原の千秋長五百秋の水穂国」に見られるが、食物起源神話としては大気都比売の屍体から頭に蚕、目に稲、耳に粟、鼻に小豆、陰部に麦、尻に大豆が生まれたとしている。『日本書紀』では保食神の亡骸の頭から牛馬、額から粟、眉から蚕、目から稗、腹から稲、陰部から麦・大豆・小豆が生まれたとされる。何も稲のみが食物では無かったのである。粟や稗や麦や大豆や小豆をも栽培し食物としていたのである。そういう〝日本人〟は、「日本人」では無かったのであろうか。本論では令和の米騒動に隠された幻想の裏側を少し垣間見てみようと思う。
雑穀へのまなざし
民俗学者の瀬川清子は、1956年(昭和31)に「日本人は果たして米を主食としてきたか」と、センセーショナルな論考を発表している。大正期の内務省衛生局の調査『全国主食調』を資料に、市部、市街地、村落部で米食慣行の相違を問い、麦飯、稗飯、粟飯、そしてこれらと米との混食、大根や芋等のカテメシという食習俗を明らかにした。東京市においては聞き書きも資料に、庶民の食文化を追った。また、米作地帯の新潟県においても必ずしも米食慣行で占められていないということにも言及した。食生活を示す資料が支配階層によるものであることに注視しつつわが国の食生活の歴史民俗的実態に切り込んだ刺戟的労作である。(瀬川清子『食生活の歴史』1983年)
雑穀をどうみてきたのか
近世の甲斐国(山梨県)の事例を見てみよう。『甲斐国志』(文化11年成立/1814)は、各領地の特色を地理や食について簡易に触れている。甲斐国河内領については、「山長地広シ潤中僻居山ヲ焼雑穀ヲ種ユ水田少ク」とある。「焼畑」をし「雑穀」を植え、「水田」は「少ク」と記している。こうした水田中心史観は文化期にすでに認めることが出来るが、そうした心理的根底はどこから来るのか。それは、『甲斐国志』が、武士階級である松平伊予守定能によるものであることによる。郡内領についてはさらに踏み込んで記述している。「民俗侠逸地大ニシテ皆山ナリ、水田少ナク蚕業ヲ専ニシテ頗ル利ヲ得、残簡風土記云福地郷此俗、麦毛モ食サズ食トナスハ、即チ多クハ其香ニ触レルコト無シ、粟稗之粥を常食而巳ト、地僻ニシテ今尚如斯者アリ」。同じく「水田」の多少、そして「麦」の香しさ、続いて「粟稗の粥」を常食のみという記述の順序、言い換えれば食の序列化を見ることができるのである。そして都市に居住する武士と農民という階層において食物が身分的に異なっていたことを示しているのである。
農学者宮崎安貞による最古の農書『農業全書』(元禄10年/1697年)では、粟は「稲に次、麦にをとらず」、稗は「尤いやしき穀」とし、穀物の差別化は江戸前期にはすでに見られていたことがわかる。文化12年(1815)の『再板農業全書』では、稗について次のように書かれている。「是尤いやしき穀といへども。六穀乃内にて下賎をやしなひ。上穀の不足を助け。飢饉を救ひ。又牛馬を飼。」とある。「卑しい」食物と早くも蔑視感を認めることができるが、「六穀」に入れその食の果たす効用や意義について冷静に筆は進められている。しかし、明治15年(1882)『改定農業全書』の記述では、「最も卑き穀物なり飢饉の救用又牛馬の食料とすへし」と短く、断定的で一見同様の内容のようではあるが、より卑賎感に支配されていることがわかる。「いやしき穀といへども」の重要性が欠落しているのである。
一方17世紀後期の『百姓伝記』では百姓の視点から救荒作物の段ではあるが、その段で「米をはじめ五穀、雑穀は、すべての人間にとって上食である」と記述している。粟については「粟を百姓の食物に使う場合に、いろいろな雑穀、干し菜、かぶなどと混ぜて炊くと、腹がへりにくく力が出る。糯粟は粘り気が強く、粳は粘り気が少ない。臼で砕き、石臼でひき割りにして、粥を粘らせるために使ったり雑炊を粘らせるために雑炊に混ぜて炊いたりするとよい。また、餅にすると百姓には上食である。しかし、収穫量が少ないのが難点である」。稗については「ひえにはいろいろの種類がある。晩生のひえは味うすく、早生ひえはの味がよい。臼で搗いて実だけを取り、飯に炊いたり粥に煮たりすると百姓の上食になり、しかも力が出る。粥にするにも雑炊にするにも粉にしたほうが特である。収穫量が多く有利な作物である。粉にしてしたるか徳なり。作る取る実有、徳多し」著者は三河国で武家としての教養に通じた上層農民とされている。救荒食としつつも百姓の視点から雑穀を、生産・調理・はら持ち・味覚に及ぶまで論じ「百姓の上食」としている。百姓身分の食文化を差別なく論じているのである。しかし忘却してはならないのは、焼畑地帯や畑地が多く占める地域において、雑穀は救荒食物ではなく食文化の核を形成していたのでる。
儀礼食としての粟
焼畑農耕においては、1月11日の「アラクウナイ」と10月10日の「トオカンヤ」という生産暦の行事において、粟は神聖視されていた。それは粟を粢として畑神様の供御物としたことに見られる。焼畑農耕文化においては、畑神様は生産・豊作祈願にとって大切な神様であって、収穫を終え焼畑地の出作り小屋から里へ戻る10月10日の「トウカンヤ」と、予祝いの行事である1月11日の「アラクウナイ」は大切な日であった。
民俗学者の野本寛一によると、山梨県南巨摩郡早川町(中世の頃には「早川入」と呼ばれていた/甲斐国河内領)新倉の茂倉集落では、畑神様は旧暦10月10日の「トオカンヤ」をやってから出雲へ逝くと伝え、この日、粟のオカラク(粢)を作って畑神様にあげた。1月11日は畑神様が畑へ下る日だとして「アラクウナイ」を行う。庭で、その年の明きの方に向かって、水神様にあげる松を立て、お茶と焼き粟餅・焼き黍餅を供え、鍬で三回地をガヂってからお茶を飲む。また、1月11日の夕方、「アーカラ節句」(粟刈りの節句)と称して粟飯を神棚にあげたと論じている。(野本寛一『焼畑民俗文化論』1984年)
茂倉の望月利子さん(昭和14年生まれ)の話によると、旧1月11日には「アラクウナイ」と言って勝手場の水つぼの所へ松の枝にシメ紙をして飾ったものを、粟・黍の餅を焼いたのを一枚、焼かないのを二枚と一緒に皿に入れてお盆に乗せて、庭の梅の木の所へ行き、ガジ(焼畑の道具)でウナウしぐさをして、その後、家に入りお餅を食べた。そして旧10月10日を「トウカンヤ」と言って粟餅・黍餅を搗いて神棚・仏様に供えた、と語っている。粟は儀礼食となっていたのである。
雑穀を選んだ日本人
柳田國男の論理によると、川をさかのぼり奥へ奥へと山間に入り山民となっても少しでも一反でも五畝でも田を開く地を選び棲んだという。しかし少なくとも山梨県南巨摩郡の「早川入」(甲斐国河内領)の事例における新移住者は400年前に遡ることができるが、「耕田乏し」という地勢から山腹に棲むことによって「山民」となって焼畑をした。稲を選ばなかった日本人、雑穀を選んだ日本人であったのである。寛文年間において「早川入」十八ヶ村の内、水田を持つ村は八ヶ村に過ぎなかった。しかし「早川入」最奥の奈良田ではいつ頃からか盆や正月には米・ぼたもちを食べていたことは奈良田追分という里謡からうかがうことができる。女性は険しい峠を越えて青柳や鰍沢の市へと歩き曲げ物と米・塩を交換し運搬してきたのである。
食文化の転換期としての大正時代―雑穀から麦へ
大正中期の各府県の主食を内務省による『全国主食物調』(大正6年調査)を参考に、畑作地帯(焼畑地を多く抱える)である山梨県の主食を検討してみよう。山梨県(甲斐国)の市部では「白米飯大部分ヲ占メ一部ノモノハ米、麦混食ヲ為ス」。市街部では「上流ノモノハ米飯ヲ食シ、中流以下ノモノハ米、麦、粟ノ混食ヲ為ス」。また「代用物トシテ小麦粉ニテ饂飩類ヲ作リ食用ニ供ス」。村落部では「主トシテ麦飯ヲ用ヒ、多数ノ部落ハ白米搗飯等分ノモノヲ用ヒ、之レニ次クハ白米三分粟七分ヲ混食シテ食スル部落、粟ノミヲ炊キ又ハ麦七分甘藷三分ヲ炊キテ常食トスル部落モアリ」。また「其代用品トシテ小麦粉ニテ饂飩ヲ製シ蔬菜類ヲ混シテ用ヒ、玉蜀黍ノ粉状ノモノニ芋、南瓜等ヲ混セシモノ又ハ玉蜀黍団子ノ焼キシモノヲ食用ニ供ス」。
「上流」「中流以下」という言葉と食文化が結びついていることを、押さえて置く。そして上流者になるほど米飯の割合が増し、米が上流であるかの指標となっていることがわかる。これはある面に置いて米を食べることが出来るかどうかが、生活において裕福か貧困かという経済的な「差別化」が興りはじめたという、歴史的・社会的な現象であると捉えるべきである。水田の希少な山梨県では麦飯の割合が高く、米や麦の混食、雑穀としての粟、また芋類としての甘藷、そして玉蜀黍も多く食べられていたことがわかる。麦食は食文化の中心として大麦の麦飯(オバク)、小麦の饂飩(ウドン・ホウトウ)として食べられていたのである。
しかし一例として南巨摩郡早川町の山村である新倉村の「明治十年産物表書上」によると、粳米81石8斗3升7合、糯米13石3斗7升3合、麦98石1斗3升8合、小麦10石9斗3升、大豆20石3斗、小豆20石2斗、粟85石、稗105石3斗、黍1石2斗、蕎麦10石を生産していたことがわかる。焼畑農耕による稗と粟の生産は抜きん出ていることがわかるが、生産石数が全体的に高いのは、稗を第一位とし、麦(大麦)、粟、そして粳米であった。特徴的なのは稗と粟の生産に占める割合の高さである。山の急な傾斜地や焼畑では稗、粟を中心とした焼畑耕作が適していた。明治初期においては「甲斐国志」の世界が息づいていたことがわかるそれが大正期には雑穀の食文化は下落し、転換期となっていたのである。粳米・糯米・稗・粟・大麦・小麦・大豆・小豆・蕎麦の生産と食文化はそれぞれに焼畑地帯の民俗文化におけるハレとケを形成していたのである。
米と麦の生産高を全国(『日本帝国統計年鑑』)と山梨県(『山梨県統計書』)において比較してみると、全国的にはコメとムギの比率は明治期から昭和20年代まで、およそ7対3で推移していることがわかるが、この数値からコメが全国的にあたりまえに「主食」、いわゆる民俗学で言うことの「ケ」の食事になったと推論するには難しいように思われる。それはいまだ3割をムギが占めていることによる。確かに都市部ではコメの比率は100%に近かったが、農村・山村ではいまだ麦を主食のひとつとしていたと考えられることによる。米と麦の生産高の割合は、大正10年から同14年の5ヶ年平均が全国で73.2%対26.8%(『日本帝国統計年鑑』)であったのに対し、山梨県では50.7%対48%(『山梨県統計書』)であった。例えば山梨県においては明治期から昭和45年に至るまでコメがムギに対して優位にありつつも、およそムギの占める比率は約50%と拮抗していたことである。その後、顕著にそのバランスが崩れコメの比率が急増し、高度成長期にムギは急落しはじめるのである。大麦・小麦ともに国内生産量は低下するが、小麦は食の西洋化によって輸入率を増加させるのであった。
山梨県南巨摩郡早川町の山村集落である茂倉(明治20年代半ばまで焼畑が行われていた)の望月利子さん(昭和14年生まれ)は、「昭和40年頃は、まだまだムギでしたよと」語るが、この言葉と統計の数値とは相交わるのである。深沢よ志さ(明治43年生まれ)んは、オバク(オオムギ)とホウトウ(コムギ)で歓待してくれた。オバクを煮ては昔を懐かしんでいたが、よ志さんの世代においてはムギが主食の時代に生きていたのであった。しかしここにおいてアワ飯やヒエ飯はすでに忘却されていることがわかる。倉本保春さん(昭和2年生まれ)は経済的には貧困な家に育って昭和20年を過ぎても小作で焼畑をしていたが粟飯と麦飯について次のように語ってくれた。
アワ(粟)は粒が、こう、小っちゃいから、炊くにすぐできるんだね。15分もたてば、もう飯になるから、飯として食えるから。でも、うまいもんじゃねえな。あの、うちじゃ、親父がそういう生活してたからね。粟のようなもの、ほんと、飽きるほど。苦しくなるほど、たくさん運んで来て。3年でも5年でも前のやつがある。しまっておくほど大変だっただけんど。それも、無かった家があるさに。粟飯も、オラのおばあら、好きどっちゅうか。オラあ、泣き泣き弁当に持って行ったことがある、小学校に。半々くらいで、米に混ぜて。だけん、半々入れると、本当に黄色くって、まずったらしいけん。今でも、部落の衆が、おばあさんたちが、バク煮たから、ネギミソ作って食えばうまいだとか。いやいや、オラ、子供ん頃から、麦はせいぜい食ったからね、オレはやだ。
大正期から昭和初期にかけて、焼畑の衰退とともに稗はもちろんのこと粟を作らなくなったことがわかる。そしてヒエ食は忘却されているのである。貧農のみが焼畑で小作をして粟を作っていた。大正期以降の食文化は粟飯から麦食中心への転換期であったのである。そして焼畑農業は廃れて行った。小学校の弁当もヨソ行きで米(配給米)を混ぜたが、混合の粟飯の味は「まずったらしい」ものであった。しかしおばあは粟食を「好き」と言っていた。この変容は粟飯から麦中心の食文化、雑穀から麦へという時代の推移を聞き書きから読み取ることができるのである。しかし稗食は忘却されている。
資本主義と米・麦・雑穀
さて、このように近代は米・麦・雑穀という食文化の大きな転換期を迎えていたのである。米を考える時にも、経済的階級とともに、その需要においても都市部、農村部、僻地の非米作の焼畑農業地帯を考慮しなければならない。都市部での消費をもって「国民食=米」と断定は出来ないのである。
大豆生田稔の分析によれば、「麦消費のピークは1900年だが、雑穀は1890年である。同年前後から雑穀消費量は漸減し、1920年代にはその速度を増している。1890~1930年の間に約半減しており、減少傾向は麦よりも大きい。米消費量の増加傾向が1890年代後半から明瞭になるが、それに応じて雑穀消費は減少をはじめたのである。「ただし、米消費が増加したとはいえ、1920年前後の農村の一般的な主食は麦飯であったといえる。……一方で雑穀の消費と生産は漸減した。雑穀消費の減少分は米や麦の消費へと向かったといえる」。経済史的な分析から、大正中期の主食は麦であったと論じている。「国民の主食」が米だけではなかったことの指摘は極めて重要である。
昭和初期、大都市東京の近郊農村である神奈川県高座郡寒川村においても、明治44年では粟144町歩を生産していたが、大正15年には10町歩と激減している。(『寒川村村勢要覧』)山梨県の聞き書きや寒川村における雑穀という食文化の変容は近代史の統計的分析において概ね理解することができる。
都市のコメと田舎のムギ
平山鏗次郎『東京風俗志』(明治34年)の記述もそうした文脈から位置づけられるのである。
都人の常食は米飯にして、麦飯を交うるは少く、偶まこれあるも多くは挽割を以てす。都人は実に麦飯を嫌えり。「麦飯喰うくれいなら死んだ方がましだ」という江戸ッ児あれば、里帰りに「一番困ッちまうのは麦飯のよ、お母さん、どうかして麦をいれないようにそう言って下さいな」と、だだを捏ねる花嫁をさえ見る。炎天汗たらたらになりて、耘殺胡耔を務むる農夫の、四分六の麦飯を弁当にすることなどは、殆んど彼等の夢視せざる所なり。但近時脚気に効ありとの説ありしより、漸くこれを怪まざるに至りしのみ。
このように近代日本の都市化は急激な米需要を喚起し、大都市東京は米の大消費地として発展を遂げ、一方田舎の食生活はいまだ麦を常食としていたことがわかる。そしてその麦飯への蔑視感には強いものがある。昭和2年(1927)の寒川村青年団誌『寒川の泉』には「田園礼賛」として東京へ出た青年が健康を害し療養のため郷里へ戻って来た時の感想を収めた作品がある。青年にとっての郷里は、心を癒す「田園」として映っていた。娘さんの稲扱きの風情と小唄、響きわたる寺の鐘の音。そして老母の皺だらけの手で摺られて作られた〝味噌汁〟、懐かしい秋刀魚と金山寺味噌で食べる昼食の〝麦飯〟に都会では味わえない感慨を抱いているのである。昭和初期の近郊農村においても、稲刈りをしながらも、昼食としては「麦飯」を食べていたのである。しかし『寒川村村勢要覧』で見たように、粟食の慣行は消え失せていたことにも目を配る必要がある。
米の大衆化へ
高度経済成長期の到来とともに国内の米の生産高は上昇を来し、輸入米に依存せずに国内消費をまかない、同42年にしてようやく自給率100%を達したのである。しかしそれもつかの間で同46年以降、成長期を過ぎると国内生産高は減少傾向をたどるのである。(農林水産省「お米の自給率」)
玉城哲は高度経済成長における大衆社会化の視点からコメ問題を取りあげ、その原点として食糧管理法とコメを位置づけ、高度経済成長期に一般国民の主食として大衆化したのであると、指摘している。(「高度成長と日本型大衆社会の成立」(「経済評論」所収1982年)。しかし1962年度に1人当たり年間118.3kgあった消費量は、2020年度には50.8kgと半分以下にまで激減した。(農林水産省「食料需給表」より)「日本人の主食=米」という幻想は高度経済成長期におけるこのねじれた米食文化にはじまったと言っても過言ではない。
まとめ
現代の食生活を高度成長期に焦点をあてれば、パン食・肉食などの普及など食の洋風化・多様化によるものであって米食慣行は下降線をたどりはじめる。近代から現代にかけて米食は、米食だけであったのは都市部であって、広くみれば麦飯とともにあったこと、いや少なくとも大正期以前の近代初頭においてに限っても麦だけではない、稗・粟・黍・大豆・小豆・蕎麦等と共にあったのである。その作物は儀礼食としての文化的意味を持っていたのである。米は日本人の〝主食〟というのはどの時代にあってもカッコ付きであったと言うことである。現代人が口にする「日本人=米」はある意味、共同幻想と言うことがでる。米にアイデンティティーを持つのは「私=日本人」であることへの心理的な、ある意味では〝国民〟という政治的な確認作業であるのかも知れない。「やっぱり日本人はお米だね」というテレビの何気ない旅番組のひと言の拡散、銘柄米への執着、美味しく炊ける炊飯器へのこだわりの追求、そこには洋食生活にまみれながらも、一粒のお米の裏には極度な政治性、ナショナリズムが隠されているのである。
おいかわ・きよひで
歴史民俗資料学研究者。1965年、神奈川県生まれ。神奈川大学法学部卒、経済学修士。歴史民俗資料学博士(神奈川大学 2021年)。資格:学芸員。
著書に『山のむらから―歴史と民俗の転換期』(2007年 近代文芸社)。資料紹介―「青年会における支部活動―田端青年会活動日誌「記録」」(「寒川町史研究」1993年)。「伊勢参宮日記」(「倉橋町史研究報告2」1990年)。論文に、「地方における青年会政策とその動向について―神奈川県の事例から」(「地方史研究」2001年)。「神奈川県下における青年団誌の発行状況と農民文芸」(「神奈川地域史研究」2001年)。「倉橋町の絵馬文化とその流行」(『倉橋町史 海と人々のくらし』2000年)。「積雪地方研究所と民芸運動」(『日本地域の歴史と民俗』2003年)など。
論壇
- 「日本人」の主食は米であったのか?歴史民俗資料学研究者・及川 清秀
- 「国民主権政府」李在明政権の時代へ朝鮮問題研究者・大畑 龍次
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(下)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- 先史日本は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦
- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(中)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 「ウソと暴力」が壊す人権と民主主義ジャーナリスト・西村 秀樹
- 寄稿ヒロシマ、神学者が綴った悲歌と愛同志社大学大学院教授・小黒 純