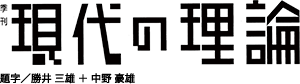論壇
テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(中)
フリーランスちんどん屋・ライター 大場 ひろみ
倉持、帰京後の行動
引き続き、添田知道の記述に基づき、倉持忠助のその後をたどる。
1922(大正11)年(疑義あり後述),大阪を中心に活動していた倉持が帰京する。たまたま空いていた下谷山伏町の唖蝉坊の隣家に住んだ。知道によれば、倉持はあちこち旅中にテキヤと懇意になり、浅草を拠点とする当時最大級のテキヤ組織、飯島一家の大立者、山田春雄と盃を交わし弟分となっていた。そして演歌でテキヤの一家を立てる。
前にも書いたが、テキヤと演歌師は、流浪したり、また人を集めて物を売り、商売の場所も重なるなど、形態に親近性はあるが、出自も決まり事のあるなしについても異なる。「神農」(テキヤを象徴する神)を掲げ、家族的紐帯を組織の基本とするテキヤとの敷居を乗り越えるのは、当時としては思い切った合理的な考えだと思うが、人の支えがなければ勝手にできることではない。山田春雄の後押しと、一家を立てる倉持についていく衆がいてこその話で、倉持にはそれだけの人望があったのだろう。野本虎民、野口岩男など、12,3人が付き従い、飯島一家内の倉持一家として名乗りを挙げた。
其の半年後に唖蝉坊の家の裏に移り、ここで震災にあって家がつぶれたが、すぐ戻り、やがて隣の二階建ての家も借りて若い衆を住まわせたりした。人手が増えたので、演歌だけでなく、『通俗法律書』ポケット『新語辞典』などのヒツジ物(紙の印刷物)を刊行したり、電気カバー、紙石鹸などの商品を考案製造して注1、普通のテキヤのようにござや台に商品を並べて売る者も出し始めた。
また、演歌師としては、震災でバラバラになった「青年親交会」の「演歌社」(唄本発行元名義)を引き継ぎ、「民謡と俗謡社」を刊行所として唄本を発行した。
倉持が新商品開発のために工夫、発明を行っていた痕跡を示すものに、大正期に現れた粉末を燃やすかまどの発明人として3件登録(大正14年)されている例がある。特許権者は川口の鋳物屋伊藤仙太郎(伊藤愃六総本店創業)。当時かまどの燃料である薪が物価高騰、都市の人口集中等により不足し、もみ殻、おが屑、藁くずなど、何でも燃やそうとするが、粉末が詰まる、空気が通りにくいなどの問題があり、工夫が必要とされた。倉持の工夫は外部容器を回転させて燃焼中の粉末を移動させつつ新たな粉末を補填するなどである(『発明にみる日本の生活文化史 住まいシリーズ 第1巻かまど』ネオテクノロジー刊)。この庶民の需要を感受し、自ら実験工夫するところなどは、後の市会議員としての姿勢や、テクノロジーである電気発送電のしくみへの理解にもつながっている。
演歌師、テキヤ、侠客にギシュウ
ところで、前回は添田亜蝉坊をはじめとして、倉持忠助や秋山楓谷などの演歌師が要視察人として警察の監視下におかれていたことに触れたが、演歌師やテキヤはどの程度社会主義を標榜、或いは主義者(テキヤ用語でギシュウ)と接点があったのだろうか?
演歌師に関しては、『雇用契約に就て労働法上に於ける二箇の合意 香具師に関する事項』(市原分⦅名古屋区裁判所検事⦆)なる文書に、「水平運動の闘士駒井喜作がもと演歌師たりしことを知っている」と、「神戸の頗川吉之、東京の倉持忠助等が何れも演歌師の元締であり、同時に思想要視察人である」また、「名古屋に高島三治と称する演歌師の元締が居る」と、後述する高島について演歌師の履歴があるように書かれている。この検事は「左傾思想を抱懐する所謂主義者の徒輩がその過激思想を宣伝鼓吹する方法として演歌師に身を託する」ことを危惧しているのである。権力側の見方はともかく、例えば倉持については、後述するアナキストの和田信義にいわせれば、「大阪でヴァイオリンを奏して歌本を売っていた頃は押しも押されもせぬ先頭切っての左翼闘士であった」。前号であげた要視察人指定を受けた一件からすれば、この頃(大正8年頃)確信をもって行動していたことが頷ける。
猪野健治の『テキヤと社会主義―1920年代の寅さんたち』(筑摩書房刊)はずばりタイトル通りにその辺の事情をテーマにした本であり、倉持についても多く触れている。実は先号で引用した『ガマの闘争』や後述の『千本組始末記』の存在もみなこの著作から教わった。
そこに取り上げられた例で見ると、テキヤと社会主義者の関わり方には大雑把に、テキヤがギシュウになる、ギシュウがテキヤになる、テキヤがギシュウを擁護するの3パターンがあるようだ(ギシュウを擁護するテキヤについては字数の都合で今回は触れない)。
テキヤがギシュウになる
テキヤの研究書というと、必ず挙げられるのが和田信義著『香具師奥義書』(文芸市場社1929年刊)である。この本はテキヤの成り立ちや生態、符牒などについて大まかに述べたものだが、中に「香具師の思想的活動」の項があり、「大正10,11年九州及び四国各地に於ける枚挙に遑なき所謂不穏宣伝ビラ事件、軍隊宣伝ビラ事件等々」「それらの多くは、かの香具師と称せられ」「最も下層の路傍商人として等閑されつつあった者等の思想的反発の現われ乃至強権に対する反抗の第一歩としての表現であった。」「そして大正12年末までに、彼等の仲間の中でともかく自ら社会主義者を以て任ずるものは夥しき数を算えるに至った」という。テキヤがギシュウになったのである。
猪野は『1920年代社会運動関係警察資料』(廣畑研二編、不二出版刊のマイクロフィルム)で、思想活動をしたテキヤとビラの実在を確認している。そこには「香具師一般の宣伝文書調」と題された警察の調書と共に1922(大正11)年1~10月までに撒かれた40のビラが挙がっている。その中身を
「資料ー警保局保安課「香具師一派の宣伝文書調」等」(ここをクリックで別窓表示)にまとめてみた。
その記録からは、流浪しバイ(テキヤの商売)をする厳しい生活の中、ビラを配り歩く、生々しいテキヤの姿が見てとれる。警察側の調書だから、事前に抑止されたケースが多いのは当然だが、ビラを刷ろうと依頼しても印刷所に拒絶、或いはタレこまれる例が多いのに暗然とする。彼等も印刷所の主(=小資本家)から共感を得られないことに歯噛みをしたことだろう。
行為者として吉田耕三、徳永参二、福本清人の3名が多く目につく。吉田耕三の宣伝文については猪野の本に複数引用があるので是非目を通してほしい。全体を参照すると、単純な主義の啓蒙に見えるものが多いが、何故か訴えかける切実さが胸に迫る。徳永参二は自分で書いた被差別部落民の解放と労農民との団結を訴えるビラを印刷しようとして3度阻まれているが、石川、和歌山、徳島県と流浪しつつ何度も挑み続ける粘り強さに頭が下がる。彼は「万年筆を射幸的手法にての販売」というテキヤのバイでさえも、官憲の厳重警戒によりほぼ売上げを得られなかった。「射幸的販売」は、テキヤの手法として知られている所謂「万年筆を焼け出され品として安く売るふりをする」方法(映画『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』にバイのシーンがある)と思えるが、35号で大西昌が「万年筆の抽籤販売」を中止させられている例は、抽籤(クジ引き)が販売に用いられているようなので、さらに賭博の要素を加えたものかも知れない。徳永はまた富山の遊郭で娼妓へ自由廃業を訴えるビラの撒布を計画するが、「経費の都合上中止」している。官憲につけ回されバイもままならぬ中、活動しようとする彼の辛い立場がわかる。後半になると、33、36,37号では数名が拘留されており、官憲の対応もどんどん厳しくなってくる(先の例で10号の九州一斉ビラ撒布計画では3名が拘留20日)。
知道は「香具師一般には、まず思想性はなかった」「底辺の生活者であった」(『てきやの生活』)であるという。演歌師の唖蝉坊も生活あってこそだった。香具師も流浪のついでにビラも撒くが、ビラを撒くために流浪するのではなかった。まず生活を成り立たせるのが最前提の不安定な存在である。しかしこの「表1」にあるような、例えばバイの現場である祭礼でビラを撒いたり、貼り付けたりする行為(11,23号)は商売の足も引っ張ったことだろう。その他映画館でビラ撒布計画(4、5,6号)や、崔正守は映画館の階上から階下の観客へ「吾々の力で吾々の敵である資本家と其の走狗たる官憲を血祭にして吾々の幸福を得る世界を創らねばなりません」というビラを撒布したりしている(37号)。かなり計画的且つ大胆なのである。この実行力と情熱は生活を超えている。
このような行動を起こす舎弟らに対して、テキヤの親分や仲間たちはどう対処していたのだろうか。
テキヤ組織会津家宗家五代目の坂田浩一郎(元東京街商協同組合理事長・詩人)は、猪野の質問に対して、「社会主義運動に走ると言っても、親分以下一家ぐるみで、なんてのはあり得ないことでね。あくまで個人レベルですよ。」「一人前の兄いになって、旅に出る頃には相当に自由が利くようになる。主義者になっても一家に迷惑をかけなければ、特に何も言われない。」「稼業に支障がなければ、たいていの親分は大目に見ていたようだな。」しかし「香具師の本業はあくまで露店ですからね。庭場を捨てたら終わりです」「専業で政治活動をするわけじゃない。稼業を続けながらの活動です」と、テキヤの本分あっての活動であることを強調する。不穏ビラについては、大正15年に郷里から出て来たから実物は見たことがないが話は聞いていると言い、「社会主義運動に投じたお友達(注;テキヤ仲間のこと)のホンネは、過酷な日常から飛翔したかっただけじゃないかな。社会に何かあると、真っ先にわれわれを取り締まりの標的にする権力に対する反発もあったかも知れぬ」と、同じ立場の者として、想像を巡らせている。
ギシュウがテキヤになる
『香具師奥義書』の著者は和田信義というアナキストである。後に述べる笹井末三郎の評伝、柏木隆法著『千本組始末記―アナキストやくざ笹井末三郎の映画渡世』(平凡社刊)によれば、大阪で「日本労働新聞」の編集長を務めていたが、1920(大正9)年荒畑寒村に追い出され、神戸で賀川豊彦が指導して大敗北した1921(大正10 年)の川崎・三菱造船所争議に加わっている。その彼が何故テキヤの本を書いたか?書中本人の序によれば、「私はふとした因縁から、過去数ケ年間親しく彼等と共にその放逸にして剛健、正直にして糜爛したる生活をなし」「漂浪の旅を重ねたことのある人間である」。理由は不明だが、自らその世界に飛び込み、体験と見聞を基に考察を交えてものにした。つまりギシュウがテキヤになったのである。『千本組始末記』によると、この本の出版は倉持忠助が和田の家計を援助するために「上森子鉄(のちの『キネマ旬報』社長)に持ち掛けて出させた本」で、1929(昭和4)年5月に出版記念会が開かれたが、そこへ酩酊した宮嶋資夫が現れて荒川畔村を殴りつけるという事件が起こっている。宮嶋は堺利彦、辻潤、新居格、岡本潤、花園歌子らと共に会の発起人の一人だった。当時の和田周辺の人脈が伝わって面白い。
和田の『香具師奥義書』において重要なのは、『千本組』でも『テキヤと社会主義』でも指摘しているのが、1924(大正13)年1月、大阪の有志により「全国行商人先駆者同盟」なる組織が創立されて、全国に趣意書を送付したといい、その3回にわたるリーフレット(大正13年2,5,8月)をほぼ全文載せている点だ。
その趣意書の中身は手っ取り早くいうと、同業者への啓蒙だ。乱暴に要約すると、店舗ある商人は資本家であり、行商人(テキヤ)は日々の生計を支えるために働く労働者と同じだが、労働者は資本家に雇われるも行商人はわずかに独立を保つ。行商人は資本主義による階級的差別感の不合理にさらされている。労働者は資本に搾取され、階級制度が出来、自らも階級を作り弱い者いじめをする。行商人は日本全国に強固な団結が作られており、日常お互いの難儀を救い合う相互扶助精神を有する。商業制度が営利本位で、小資本は大資本に駆逐される運命だが、資本家・営利本位の社会組織を根本より改革して、人間相互の必要を満たすよう、階級的差別感のない平和な世の中をつくろう。
そして2回目配布時には九州と近畿・東海で5支部が立ち上がり、3回目までには全国で11支部を加えたとしている。九州・近畿辺りが中心なのが、テキヤの宣伝文撒布行為と重なる。
知道は『てきやの生活』でこのリーフレットを長々と引用し、最後に「(和田が)てきやの多くと交友するうちに、その生態の見聞から、当然に批判も持ったろうがまた、その生活感情のなかにある人間原始性に、むしろ愛情まで感じていたことがわかる。ということは、この行商人先駆者同盟の動きのなかに、彼がいたろうことが考えられ、何よりもこのリーフレットの作文の多くは、彼が書いたもののように私には思える」と、リーフレットの文章の創作性を示唆している。一方『千本組』では、上森子鉄がリーフレットを「私が作り上げたものです」と証言した言葉を引用し、「行商人先駆者同盟などは影もかたちもなかった」とまでいいきっている。真偽のほどはわからないが、このリーフレットの記述によって、和田が商人や労働者以上の社会変革を起こす可能性(移動の自由や相互扶助精神、被差別的環境におかれていることなど)をテキヤに見て、呼びかけた思いが伝わってくる。
この大正デモクラシーの時代は、普選運動や労働争議を巡って、階級対立やアナ・ボル対決、官憲の弾圧など、様々な意見や分裂と抑圧が吹き荒れた時代だった。リーフレットに「真面目にやれ」と同業者にハッパをかける一文があるが、テキヤに限らず、この当時の人々は自らの立場を自覚し、今よりずっと真面目に社会と向き合っていたと思うがいかがか。
テキヤでギシュウ
猪野健治の『テキヤと社会主義』では、高嶋(高島)三治というテキヤでアナキストだった(そもそもテキヤだったのかギシュウだったのかさえも掴みかねるという意味でもある注2)人物が重点的に描かれている。高嶋は十代後半に京都で大杉栄らの後援会を聞いてアナキストの仲間入りをしたという。また横浜のテキヤ飴徳一家の身内となり、その後飴徳から独立した沼津の桜井庄之助の身内となった。高嶋はとても人好きのする好漢だったようで、テキヤ界でもアナキスト界でもすぐに人望を集めていい顔になっている。関東大震災後、大杉栄ら虐殺の復讐に端を発して、映画にもなった(『菊とギロチン』瀬々敬久監督)「ギロチン社」事件では、あまり表立って出てこないが(映画にも登場しない)、武器調達担当としてブローニング拳銃2丁を入手したり、事件の中心人物・中浜鉄に頼まれて朝鮮に渡り、爆裂弾を準備したり、また資金調達のためリャク(=掠、アナキストが資本家を脅して金をゆする行為のこと)に廻り、テキヤ仲間からも金を集めたようだ。
「(高嶋は)アナキストの先輩たちと交流を始めた大正7(1918)年頃から特高警察の尾行を受ける身になったようだ。しかし大正11(1922)年までは名前が出るような派手な政治活動はしていない」と猪野の本にはあるが、「軍隊に檄文を撒布せる犯人 越後高田市において就縛す」という1920年4月30日の東京日日新聞の記事 がネット上に上がっており、それによれば、「各地の軍隊に対して頗る過激の印刷物を撒布し又は名古屋方面より北越にかけて電柱其他に社会主義者の作成せる激越なる歌を貼付せる者あり」「犯人名は高島三治(26)」。例の宣伝文(反軍ビラ)を撒布するテキヤの中に高嶋が加わっていたことがわかる。
ヤクザでギシュウ
ヤクザ(博徒、侠客)とテキヤ(露天商)はれっきとした別の組織だが、一家の紐帯とか儀式とか行った先で名乗りを挙げる(アイツキ)とかの様式が似ている上に、2010年以降、各都道府県自治体は暴力団排除条例によって、暴力団と同一視してテキヤの商売を事実上奪いつつある(例外として元テキヤ系の極東会は指定暴力団)。テキヤとヤクザの区別や、昨今のテキヤへの条例による厳しい締め付けは、廣末登著『テキヤの掟』(角川新書刊)に詳しい。
『千本組始末記』は京都の侠客千本組の三男坊、笹井末三郎の評伝で、副題にあるように末三郎は「アナキスト」で「やくざ」という位置づけだ。しかしヤクザの子とはいえ、お金持ちのボンボン(父親は侠客になる以前、木材運びの筏乗りから始まって、浜仲仕の口入れ業、材木等の運搬などで財を成した。まあ侠客の「実業」としてありがちな職種だが)の末三郎はアナキストに感化された後、ヤクザになることは嫌っていた。いずれにしろ、社会主義に対抗した官製右翼「大日本国粋会」(1919⦅大正8⦆年結成)の看板を掲げる家にアナキストが住んでいたことになる。末三郎は「ギロチン社」事件でも高嶋三治と会い、協力関係にあったとされる。
先述した1921(大正10)年の川崎・三菱造船所争議に関わり、警察に呼び出されたので和田信義に相談すると、「東京へ行ったらどうか。僕の友人が浅草にいる。倉持忠助というテキヤの親分だ」と倉持を紹介した。1921年の9月に末三郎が倉持を頼って浅草千束へ行き、2,3日世話になった後、用意されていた隠れ家に移る注3。和田信義への援助として『香具師奥義書』を出版させたことと併せ、倉持のテキヤ的そしてアナキスト的相互扶助精神の発露を示すエピソードとしてとっておきたい。
ギシュウの「転向」
高嶋三治は、ギロチン社と共謀して大杉栄ら虐殺に対する報復のため爆裂弾調達の罪で名古屋で逮捕され朝鮮で有罪判決、1925(大正14)年収監されたが、大正天皇死亡の恩赦で1927(昭和2)年釈放。活動を再開しようとした矢先、いわれのない容疑で再逮捕される。その後「転向」して無罪釈放の後、名古屋の侠客・本願寺一家の4代目高瀬兼次郎の世話になり、高瀬の経営する名古屋「歌舞伎座」の支配人に収まる。高嶋についてはもっぱら猪野に拠っているが、その後の高嶋は「戦時下では軍部に協力する関連事業を経営し成功する。そして戦後間もない時期には日本社会党結党を蔭から支援する一方で、戦犯の釈放運動のリーダーとなる。その際にはフィクサー役も果たし、名古屋に根を下ろした晩年は、任侠界だけでなく、広く中部政財界からも『センセー』と呼ばれ畏怖された注4」(『テキヤと社会主義』)。なんともぬらりくらりと手に負えない人物である。
ヤクザアナキスト、笹井末三郎も、映画会社日活の経営に関わるようになってから、戦中は満州へ渡って、甘粕正彦が理事長の満映に「左翼」の俳優や技術者を送り込んだという。また戦後は映画界の背後でフィクサー的役割を果たす。
そういえば、前号で登場した演歌師だった南喜一は、その後グリセリン工場を経営していたが、関東大震災の時に南葛労働会の活動家だった弟・吉村光治を「亀戸事件」で殺害され、その後猛然と社会主義運動にのめりこむ。共同印刷(争議部長として―『太陽のない街』徳永直あとがき)、浜松日本楽器などの大争議を指導するが、1928・3・15の共産党一斉検挙後獄中「転向」、今度は玉ノ井の私娼解放運動に転じる。1940(昭和15)年には同じ転向組の水野成夫(のちフジテレビジョン創立、フジサンケイグループの礎を築く)と共に、岩畔豪雄陸軍軍事課長(陸軍中野学校設立者)の後ろ盾により、国策パルプ工業の全額出資で「大日本再生製紙株式会社」を設立。その後国策パルプ会長や、ヤクルト本社会長(この時水野のサンケイが所有するプロ野球チーム・サンケイアトムズを買収、のちのヤクルトスワローズ)歴任と、これまた面妖な人生を送る(『ガマの闘争』とウィキペディアに拠る)。どっちにしても振り幅が大き過ぎないか。
しかし南で面白いのは、グリセリン製造や再生紙の発明である。人力車夫をしながら東京薬学校に通っていた南には化学の知識があった。寺島町で石鹸会社が曳舟川に廃液を流し、農民ともめているのを見て、石鹸からグリセリンが製造できると思い立ち、廃液をタダでもらって来て、グリセリン工場を始めて大当たりする。が、廃液を有料化、また水増しされたのでグリセリンだけではダメだと、今度は硬質ゴムの発明・製造に乗り出す。生活の中から優れたアイディアを生み、身近なものを利用して実用化する。再生紙会社を興す元になる「古紙からインクを抜いてパルプに再生する方法」(鍋に古新聞を入れて米糠を加えて煮る)は特許を取っている。スケールは違うが、何だか倉持のテキヤのネタ発明を重ね合わせたくなる。
竹中労は大正アナキストの群像を描いた『黒色水滸伝』(かわぐちかいじ画・皓星社刊)で、「日本アナキズムの正史は、いわゆる『転向』のテーマをおろそかにしている」と指摘する。自らの父で画家・竹中英太郎も「右翼」に接近して、2・26事件で被逮捕者となった前歴があったことを挙げながら、しかし「ほんらいアナキズムは人間の気質に関わる。真の無政府主義者に、『転向』ということはあり得ない」「何が彼らをして、“右翼”への道をあゆましめたのかを明らかにすること。その営為なくして、アナ・ボルの協同分裂・大杉虐殺以降の日本無政府主義運動の“歪んだ軌跡”に、理会をすることはできない」と述解する。南喜一は共産党員だったが、共産党入りした理由も含め、「人間の気質に関わる」運動であったことは、彼の一筋縄ではいかない人生が物語る。いずれにしろ、彼らの行動に「転向」という、「社会主義の放棄宣言」しか意味しない、権力側が一方的に押し付けた言葉は当てはまらない。
「香具師の思想的活動」は、和田信義の『香具師奥義書』によれば、関東大震災後の不景気や、台頭してきた反動思想が、「彼等のまだ固まり切らぬ思想に動揺を与えそして亦彼等の境遇としての流浪性」が「甚だ時機のよからぬ時に企てられた同盟創立をして、竜頭蛇尾、一敗地に塗れさした」「かくて数年は流れた。其後筆者は彼等の仲間に又此の種思想的活動のあったことを聞かないのである」とわずか数年で潰え去ったことを伝えている。しかし彼等の(坂田浩一郎のいう)「過酷な日常から飛翔」しようとする思いや、アナキストと通ずる「相互扶助精神」は、「人間の気質に関わる」運動として「転向」することはなかった。
(注1) ここまでほぼ知道の『演歌師の生活』に負っているが、そこに売れっ子演歌師の石田一松の「支持者」として関口愛治の名が出ている。彼は、横浜のテキヤ飴徳一家の出でのち東海道桜井一家を名乗る桜井庄之助と、親子の盃を交わしている演歌師である(のちテキヤ系組織で新宿や池袋を拠点とした極東会結成)。その軌跡を描いた『桜道の譜:実録・風説の極東五十年史第1巻』(三浦エンタープライズ刊)では、関口が浅草十二階裏の家で、大正10年頃からテキヤや不良少年を集めて、まるでテキヤの一家を為したかのような繁盛ぶりであり、石田一松にヒツジ物を考案させて商品化したり、「その他にも、『けったい石鹸』とか、『簡単電機カバー』などを考え出し、職人に作らせて街頭商品のネタ元のような存在に転向しつつあった」とあるのが、まるきり演歌師でテキヤの倉持と行いが酷似しており、ハタと首をかしげてしまう(他にも交友関係や発言に重なるところ多々あり)。が、知道の著作が先行していることを考慮して、そのまま負った。
(注2) テキヤとしては、前述のように演歌師の履歴があるというのや、「香具師として商売を一度もやったことがない」(藤田五郎編著『公安百年史』公安問題研究協会刊)やら、かと思うと坂田浩一郎はテキヤと思想活動の関わりに関する証言の中で「高嶋三治先生にしても、稼業からは決して離れなかった」と、高嶋がテキヤの商売を営んでいたことを前提に語り、人によって話が異なる。アナキストになる辺りの事情についても、猪野も『公安百年史』の記述に拠っているようで今一つ根拠として頼りにならない。本人の書いた『たらい廻し』(名古屋新報1958・10・25~1960・4・5)は未見。
(注3) 『千本組』での倉持に関する記述では、「倉持が演歌師として千束町に一家を構えたのは大正9年(1920)で、関西旅行から帰ってきてからである」とあり、「のちに下谷山伏町49番地に移り」と続く。これは知道の記す、「大正11年上京して」「演歌でてきやの一家を立てる」(『てきやの生活』)と完全に矛盾している。知道のいう通り倉持が「大正11年上京」では、倉持が末三郎の世話をすることはあり得ない。知道は『演歌師の生活』においては、ただ「震災前大阪を根拠に中国、九州を経めぐっていた倉持」が「東京へおちつく」のに唖蝉坊の隣家へ住んだ、と、年代をあげていない。震災前だったという記憶で1922年としたなら、それだけあやふやだということになるが、『千本組』にも1920年に千束に住んだとする根拠は示されていないので、どっちなんだか途方に暮れる。個人的見解を述べさせてもらうと、1922年に倉持上京なら、その後のテキヤ一家起ち上げ、急成長が慌ただし過ぎるのだ。一方『千本組』では、この後末三郎は倉持の仲介で興行師・伊藤甚五郎の所有する長屋に移るが、女優の卵と恋仲になり、うつつを抜かした女優が舞台に穴を空けて首になると末三郎も居辛くなって引っ越す。結果倉持の顔にも泥を塗ったことになるなど妙に生々しいので、こっちを信じたくなる。
(注4) 高嶋のその後については、『千本組』によれば、戦中、「東海軍需管理部部長岡田資中将のもとで徴用工の駆り出しや物資の輸送など陸軍関係の仕事を一手にひき受けていた」。この話の引用元は小栗喬太郎『ある自由人の生涯』(佐藤明夫刊)で、愛知県半田市で共産党系の新団体が結成され、「戦争中横暴のかぎりを尽くした軍の親玉」岡田中将が半田市に住んでいたので追放しようとしたが、集会でその議題が上ると「名古屋大須のテキ屋の親分高島三治とその一派」が集会破りをしてめちゃめちゃにしてしまったという。「戦犯の解放運動」の戦犯とはこの岡田のことで、岡田はその後米兵捕虜虐殺の責を問われ死刑。かと思うと大杉栄と共に虐殺された甥の橘宗一の墓が発見され、墓碑保存会が準備されたがその時会に出席して涙を流しながら当時を語り、資金を提供したそうだ。立場に関係なく、義侠心が行動させるのだろうか。しかしアナキストとして朝鮮に渡り、朝鮮の人々と交流し、同志も多くいたはずの彼が何故徴用工の駆り出しを手伝えたのか。私には認めがたい。
おおば・ひろみ
1964年東京生まれ。サブカル系アンティークショップ、レンタルレコード店共同経営や、フリーターの傍らロックバンドのボーカルも経験、92年2代目瀧廼家五朗八に入門。東京の数々の老舗ちんどん屋に派遣されて修行。96年独立。著書『チンドン――聞き書きちんどん屋物語』(バジリコ、2009)
論壇
- 「日本人」の主食は米であったのか?歴史民俗資料学研究者・及川 清秀
- 「国民主権政府」李在明政権の時代へ朝鮮問題研究者・大畑 龍次
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(下)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- 先史日本は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦
- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(中)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 「ウソと暴力」が壊す人権と民主主義ジャーナリスト・西村 秀樹
- 寄稿ヒロシマ、神学者が綴った悲歌と愛同志社大学大学院教授・小黒 純