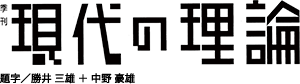特集 ● いよいよ日本も多極化か
2025参院選――組織された細切れの「民意」
社会を産み直す梃子は、無数の取組を繋ぐ《大きな物語》
大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員 水野 博達
1.賞味期限が尽きた自公政権
2.選挙の争点にならなかったことから見える風景
3.参政党の急伸が意味すること
4.自民党政治の終焉と戦後の社会制度の行き詰まりを超える道
5.補論~自民党の延命を賭けた「連合」の幾つかの形について
1.賞味期限が尽きた自公政権
参議院選挙が終わり、自民党は、「石破降ろし」の旋風の中で揺れている。石破首相に敗北の責任を取らせ、党の「顔」をすげ替えれば、党の支持が戻るというほど事態は甘くない。自民党支持層でも8割が「自民党全体に問題がある」(朝日新聞調査)と答えている。政治過程だけを見ても、長期政権を維持した安倍元首相の死後、「統一教会」と長きにわたる不正常な関係が明らかになり、続いて、安倍派をはじめ各派閥の「裏金づくり」の実態が判明し、国民の自民党への信頼・支持は地に落ちた。党の病根にメスを入れず(入れられず)、膿を出しきれなかった自民党は、今回の選挙で、国民からNo!を突きつけられた。
後ほど詳しく見るが、この敗北は、自民党の派閥政治の結果や失政の問題ではなく、自民党が政党として「賞味期限」を超えてしまったという時代の転換と重なった敗北であると見るべきであろう。この自民党に随伴してきた公明党も政党の存在意義が問われる局面に逢着していることも、また、明らかである。
他方、立憲民主や維新の不振と参政党の急伸や国民民主の躍進など野党の新しい動向と関係にも時代の転換の予兆が示されたと言えよう。本論では、今回の選挙が、時代が求めていたことに応えるものであったかどうかという視点で顧みることにする。
2.選挙の争点にならなかったことから見える風景
今回の選挙では、どのような「民意」が、組織されたのかを検討することが重要だと考えた。「民意」とは、人々が自然に抱く考え方などではなく、政治勢力やマスコミ、あるいは言論界等の働きかけによってはじめて可視化され形となって表出される人々の「意思・意志」のことである。選挙では、各政党の訴えと論争によって組織される人々の政治的意思の表れが「民意」である。
今回の選挙について、多くのマスコミの論評では、物価高対策として給付か減税かといった点に選挙の争点があったと総括しているが、その前に、私たちの生活と未来にとって大切なことであるのに、選挙の争点にはならなかった、あるいは、無視された論点は何であったかを見ることが、選挙で組織された「民意」全体の政治的性格と意味を理解する上で、重要である。
連日、猛暑が続き、干ばつや大規模な山火事に見舞われる地域がある一方で、突然の大雨と落雷が襲い、河川の氾濫が頻発している。今や世界中が、異常気象に見まわれている。この異常気象をもたらす「地球温暖化」の問題は、現在と未来の生活にとって最重要課題の一つであるが、今回の選挙では、争点にすら上がらなかった。これが一つ。
もう一つは、ロシアのウクライナ侵攻が3年続き、アメリカの「中東の蛮犬」イスラエルのパレスチナや周辺諸国・地域への無差別爆撃などの国際法と人権を無視した戦争が続き、国連もG7もそれらを止めることができない事態が続いてきた。そればかりか、他方で、従来の国際秩序を「アメリカ・ファースト」で塗り替えるトランプ政権の動きなどに対しても、アメリカの核の傘の下にいることがもはや意味をなさなくなっているのに、世界平和と安定のために日本がどのような外交政策を取るべきかが争点にも登らなかった。 この地球規模の二つの危機に対して、「平和で持続可能な社会」を今日から未来にかけて作り上げていく上で欠くことのできない課題であるが、今回の選挙では、問題にすらならなかったのである。
このことの意味は重大である。世界にとっても、日本にとっても無視しえない課題をスルーして闘われた今回の選挙が作り出した「民意」とは、各政党が、有権者に現実の厳しい社会と向き合うことは求めず、一人ひとりの目の前の小市民的な私的利害を刺激して、いかに『票』を集めるかに苦心した「ポピリズム的な組織合戦」であったと見ることができる。曰く、「一人2万円、困窮世帯には4万円を給付」(自民・公明)、「食料品への消費税ゼロ、皆さんの生活を守ります」(立憲民主)「課税最低額を178万円へ、手取りを増やす」(国民民主)「社会保険料を減額する」(維新)「消費税ゼロで経済成長を」(れいわ)等など・・・。
いずれも、減税か給付かなどの重点の置き方に違いはあるが、中長期を見据えた社会改革というよりも、政策の有効性は短期的なもので、どの政策も、今の生活に行き詰まりを感じている有権者の「(馬の)鼻先に人参をぶら下げる」ようなものであった。「持続可能な社会」への政策ではなく、「洪水よ、わが亡き後に来たれ!」といった考えであり、今だけでも良ければという「漂流する世相」=「民意」を組織したのである。
3.参政党の伸長が意味すること
参政党の言説には、確かな理論や思想の裏打ちはない。その主張と行動は、ほとんどドナルド・トランプのコピーである。訴えるのは、政策というより、「日本人ファースト」というキャチコピーに集約される事実に基づかない憶測やデマを取り交ぜた「プロパガンダ」とでも言うべきものであった。
でも、なぜ、伸長できたか。今回、自民党を支持してきた保守層の多くが参政党に回ったことは事実だが、「自民党の失った票がそっくり参政党に回った」という話には、自民党を再生させるためには、右に回帰すべきだとする政治的な狙いが隠されていて信用できない。他方、「自民党がリベラルになったので(石破政権=反安部、反高市)保守層の一部が参政に回った」 という「日本会議」の意見は、彼らの本音を表現していて興味深い。この見解は、日本会議が政治的な力を得ていたのは、自民党と組んでいたからであり、(石破)自民党から見放されたことで、影響力を失ってきたことへの恨み節でもあるからだ。
また参政党は、初めて政治に関わり議員になった者が多いと言われるが、組織を支える基盤には、自民党員として活動を経験してきた者たちがいる。これは、大阪維新の会が、元々自民党所属の大阪府・市の議員らによって結成され、当時、自民党残留組からは、「厄介者が維新に移り、すっきりした」と言われたことと似ている。参政党関係者から、神谷代表しかりで「自民党でやっていけない人が参政党に流れ、人材の質は、“劣化版自民党”」と揶揄する声もあるが、全国に287の支部をもち、地方議員は150人を超える。急激な党勢の伸長は、この全国各地の支部組織と地方議員を擁する組織力が土台にあることは確かだ。
だが問題は、反エリート主義的で参政党の排外主義的・差別的な言説が、50歳代以下の広い層の心を掴んだことを認めなければならない。2節で述べたように、物価高にどう対処するかを巡って、一人ひとりの目の前の小市民的な私的利害を刺激して、いかに『票』を集めるかの競争に汲々とする既成政党化した各野党の訴えが、人々の心を揺さぶることはできなかった。若者や就職氷河期を経験した世代は、国や既成政党の政策によって自分たちの未来が開かれるとは感じられなかったのだ。
先の見えないこの社会に抱く不安・不満は、漠然とはしているが、「失われた30年」を生きて来た感性には、重く圧し掛かっている。はっきりしていることは、自分たちは国にも社会にも大切にされてこなかったし、これからも見捨てら続けるかもしれない、という体に浸み込んだ感覚である。「自分たちは大切にされていない」という感性と「日本人ファースト」という叫びは、ぴったりと符合したのである。
参政党の排外主義や差別言辞や事実に基づかないデマ宣伝には、根気よく反論していくことが求められるが、何よりも参政党のプロパガンダが成功しているのは、各政党が、日本社会が逢着している危機を明らかし、その打開の方向を提示しない(提示できない)まま、短期的な安易な利益導入政策を氾濫させたことに対する失望であることを総括すべきであろう。
求められるべきことは、身近な小さな物語ではなく、地域や職場で、あるいは公共空間で、社会的課題に対して取り組まれている無数の実践が、社会を生み直す大きな流れとなって繋がっていく社会改革の構想=大きな物語なのである。
4.自民党政治の終焉と戦後の社会制度の行き詰まりを超える道
次に問題は、自公政権にNo!を突きつけた今回の選挙の意味とは、何か。それは、人々が現状と未来に抱く不安の基は何かということを考えることでもある。また、それは、2節で述べたこととも重なってくる問題でもある。
自民党を中心とした戦後日本の政治の安定はどのような構造を持っていたかを振りかえれば、今回の自公政権の敗北の歴史的な位置と意味が解る。
日本資本主義は、戦後の復興過程で、アメリカと安保条約(「核」の傘の下に)を結び、軽武装で経済成長を図り、60年代には、高度経済成長に突入し、1980年代には、アメリカに次ぐ経済大国へのし上がった。こうした経済成長とともにつくりあげた自民党の政治支配の安定構造は、独占資本を中核とする経団連などの資本家団体と全国各地に根を下ろした農協との連携による資本家階級と農民階級を両軸とした中道・保守の「国民政党」への歩みであった。田中角栄政権の「列島改造論」に代表される安定した社会・政治支配は、都市での産業から上がる税収を農村・漁村へ配分する公共事業や農業・漁業へ助成などによって支えられたのである。
この体制に対峙したのが社会党(国会で三分の一勢力)であったが、戦後改革以来、国は、アメリカ占領軍やILO等の国際的な圧力の中で、労働法・労組法などによる労働者の権利の保障を行ってきた。また、生活保護制度による生活困窮者の救済や労災保険、そして、医療保険制度、年金制度のどを国民皆保険制度へと整備し、2000年には介護保険制度を施行した。
だが、1980年代から世界は、新自由主義的グローバリゼーションの時代へ移った。人・物・金・情報(知識)が国境を越えて自由に移動するようになり、日本資本も、中国・東南アジア・北米、中米等へと生産拠点を移動させるなどして、国内の産業の空洞化も生み出し、「就職氷河期」が1990年後半から一時期を襲った。金融資本と大企業に富が集中し、経済格差が広がった。同時にそれは、地方(農・漁村)の衰退と過疎化、少子高齢化の進展でもあった。
戦後の資本主義各国は、「平和共存」下で国家主権と民主主義によって、「福祉国家」を形作ってきたが、グローバリゼーションによって、国家は、金融・独占資本の僕へと凋落し、これまで「社会の安定帯」の役割を果たして来た社会福祉をはじめとした社会諸制度へ「官から民へ」の民営化の攻勢が仕掛けられ、社会の大きな変動が進んだ。
政治の面では、自民党単独政権では、政治の安定が揺らぎ政治再編を経て、公明党との連立政権が組まれ、また、大独占資本下の労組(連合)との協調へとウイングを伸ばすとともに、伝統的右翼勢力の「日本会議」や反共宗教団体「統一教会」との結びつきによって、各種議会選挙での集票力を高めて来たのである。
自民党が、「日本会議」や「統一教会」などの右翼勢力へのウイングの伸ばしたことについては、3節で触れたので、ここでは、日本社会の持続的な安定に寄与してきた社会諸制度の行き詰まりの状況を一瞥する。
① 医療保険制度によって医療の提供体制を守るため国は、高齢化と医療技術の高度化に伴って、診療報酬や薬剤費が年々高騰する傾向を抑制してきたが、この「公定価格」の管理・統制によって、医師・看護士などの医療従事者の不足と偏在化が生まれ、「医療過疎地」が顕在化してきた。また、稼働現役世代に保険料負担が重くのしかかり、保険制度のあり方が世代間の対立を含みつつ問われている。
② 年金制度への信頼が揺らいでいる。若い世代は、支払った額に見合う将来の年金の支給に不安を抱いており、少子高齢化の人口構成に対応する安定的な年金制度の未来像をどう描くか問われている。
③ 介護保険制度の崩壊の兆しが見え始めた。全国一律の介護サービスの提供が、在宅介護、とりわけ訪問介護事業の人手不足によって、地方でも、都会でも困難になっている。「保険料払ってもサービスなし」という状況を抜本的に解決する国の姿勢が見えない。
④ 農村に根を張る農協の位置を使った米の食料管理体機能の不全が、今回の「米騒動」である。米の生産・販売の自由化以後にも、事実上の「減反政策」がなされて来たが、農業人口の高齢化と減少もあって、生産・価格調整機能の破綻を隠すことができなくなった。都市(消費者)と農村(生産者)の関係が改めて問われている。
⑤ 2025年4月で国債発行残高は、1,129兆円となっており、国の歳入全体の4分の一となっており、国債の入札不調(買い手がつかない)という事態も生まれている。国債に依存する国家財政の信頼が揺らぐことになる。
①~③は、日本の社会保障制度の持続性が揺らいでいることである。北欧の人々が、老後を含めた生活に対する不安は、大きくない。だから、貯金も多くない。税金などの公的負担率は高いが、社会保障制度への信頼は大きい。老後生活のための貯金の必要性を感じていないのだ。
他方、日本では、国の制度に対する信頼がない。現実に、高い保険料を払い続けても、介護サービスを受けられるかどうか疑問である。年金は、老後を支えられるだけの給付にありつけるとは思えない。それらは、国の社会保障制度に対する若者の本音である。
介護保険を例に取ろう。介護サービを市場化した介護保険は、そのサービスを担う介護職員の給与と労働条件は低い。だから、介護の仕事には人手が来ない。介護保険による介護サービスの準市場化とは、国による管理・統制によって、サービスのあり方全般を統制・規制するものである。この統制・規制によって介護報酬は安く抑えられ、その結果、介護労働者の賃金は他産業の平均より月5~8万円ほど低く抑えられて来た。だから、年々人手不足が深刻になっており、介護サービスが満足に提供できなくなっているのだ。もはや、部分的な手直しでは、介護保険は生き返らない。解体的な再編が求められることが、今やハッキリしている。
先に上げた①~⑤の行き詰りの解決は、一つ一つの制度の改革が、国の制度全般の改革と結びついており、戦後政治の中で形づくられて来た大きな社会変革の課題と重なっている。もはや、現状の自民党の政治力では解決不能である。諸制度の改革は財政のあり方と深くリンクしており、税制を含めた国民全体の負担と給付・配分の関係を巡る歴史的・国民的な再編を伴う政治的選択となるからである。だから、現状の自民の党政治では、力が及ばないので、いずれ、連合政権を含めた大きな政治再編を伴う、新しい政治の枠組みが求められることになる。
また、その政治の新しい枠組みとは、公共的な課題・制度について、そのあり方や運営に関して国や地方自治体の行政機関にその検討・決定を委ねて来た現状を打破し、検討・決定過程に当事者・住民が参画できるものへと改革していくことが求められる。とりわけ、社会保障政策に対して、当事者の意思が制度に反映させられるものにしなければならない。
そして、改めて地方自治が、生活者の生活と権利を支える政治的な役割を負えるようにすることが求められる。その意味で、社会改革の政策立案だけではなく、行政プロセスに住民が参画していける自治の力を育んでいく住民と政党や研究者などの協働の営為の積み上げが求められるのである。この人々の協働の営為の積み上げが、行政サービスの「受益者」としての住民ではなく、主権者として自主的・能動的な社会改革の力を生み出していくことになるであろう。それは、民主主義を掘り崩すポピュリズム政治から私たちが自由になることでもある。
5.補論~自民党の延命を賭けた「連合」の幾つかの形について
参議院選で敗退した自民党は、政権政党の位置から転落する崖っ淵に立たされている。とは言え、自ら政権を投げ出したりはしない。生き残りを賭け、復活を賭けた死闘が展開されることになる。現に今、選挙での敗北の責任が問われ、誰を党の総裁に据えるのかを巡る権力闘争が日を追って激しくなっている。自民・公明が、衆参両院で小数政権となっているもとでは、党の「顔」を定め直す争いは、同時にどの野党と連携・連合して権力を維持するのかという政権構想とも連動することになる。
A 最も「右」の政権は、参政党や保守党と連携・連合した政権である。自民党の中心に、高市議員や旧安倍派が座ることが自然なことになろう。「日本会議」等の在野右翼勢力との連携も復活することになる。そうすると、公明党は、政権内に残るのか、出ていくのか。あるいは、自民党のリベラル派が離党する可能性も考えられる。
B 党勢の陰りがはっきりした維新が、「副首都構想」を自民党が受け入れることを条件に自民党と連合政権を発足させようとする維新側の意向が語られ始めた。かつての代表・橋下は、「自民党と組んで副首都構想が現実化するのであれば、維新の会が消滅しても構わない」とまで主張している。橋下の自民党との連合論は、賞味期限の切れた維新の会を自民党と融合させ、大阪の政治的経済的地位を上昇させ、維新八策に記した中央集権型国家像ではなく、地方分権型の「道州制」による日本の統治機構を再編する「改革政党」を生み出すことなのである。言い換えれば、維新が自民党の軒先を借りて、母屋(自民党)を乗っ取る策謀なのだ。
Ⅽ 国民民主党との連合政権である。原発推進や政治資金を企業・団体から受け入れることは禁止せず、自民党と同じく透明性の確保だけを主張するなど、自民党としても組みやすい政党である。さらに、大企業の従業員を組織している労組・連合の支持を受けている国民民主党との連合政権は、労働者・労組との日常的な意思疎通が可能で、政治の安定化を担保することになる。だから、国民民主の党首を連合政権の首相にすることも考えられるのだ。その意味で、この連合政権は、戦前の「大政翼賛会」的な性格を持つ危険性が存在するかもしれない
Ⅾ 立憲民主党をはじめとする野党との「大連合政権」がある。この大連立は、自然災害や戦争、あるいは何らかの対外的な危機や深刻な経済危機などに基づく全般的危機が迫った際に組まれる政権のあり方である。平時に、このような大連立政権が組まれるためには、政権を構成する政党間で政治方針や改革方針について大きな合意が必要である。今回の選挙の過程と結果から言えることは、こうした与野党の大きな合意と世論の後押しは不在である。だから、大連立の可能な条件は見当たらない。結局、自公政権と各野党との様々な政策・方針の部分的、一時的な協力と合意の不安定な繰り返しが続くことになろう。
A、B、Ⅽ、Ⅾと考えられる「連合政権」も、その寿命は長くない。政党間、政党内の分裂と離合・集散、再編を繰り返しながら、政党再編が、急速に、あるいは緩慢に進行することになろう。
こうした権力奪取の政治過程に振り回されことを避け、この矛盾に満ちた社会を生み直す大きな物語を紡いでいく努力が求められているのである。 (2025年8月1日)
みずの・ひろみち
名古屋市出身。関西学院大学文学部退学。労組書記、団体職員、フリーランスのルポライター、部落解放同盟矢田支部書記などを経験。その後、社会福祉法人の設立にかかわり、特別養護老人ホームの施設長など福祉事業に従事。また、大阪市立大学大学院創造都市研究科を1期生として修了。2009年4月同大学院特任准教授。2019年3月退職。大阪の小規模福祉施設や中国南京市の高齢者福祉事業との連携・交流事業を推進。また、2012年に「橋下現象」研究会を仲間と立ち上げた。著書に『介護保険と階層化・格差化する高齢者─人は生きてきたようにしか死ねないのか』(明石書店)。
特集/いよいよ日本も多極化か
- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生
- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子
- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京
- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀
- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣
- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆