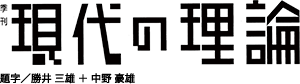コラム/歴史断章
ビッグ・ヒストリーへの誘い
時には、超長期の歴史を想起しよう
市民セクター政策機構理事 宮崎 徹
大きくはウクライナやガザでの惨劇、小さくは国内の政治の退廃ぶり、あるいは「事実は小説よりも奇なり」というほかないような社会的事件の数々。新聞やテレビの報道はそんな出来事で満載である。日々これらを「消費」するわれわれ、少なくとも筆者は、情けないことに疲労困憊である。
そのせいか、このところビッグ・ヒストリー、人類史のような射程の極めて長い書物を手にすることが多い。これはまちがいなく、一種の現実逃避なのだろう。さはさりながら、そこで得られたいくつかの知見を参考に供しながら、多少のコメントを加えてみたい。
生々流転の地球史
まず、この春に面白く読んだのはデイヴィッド・ベイカー『早回し全歴史』(ダイヤモンド社、2024年)である。本の帯には「歴史学、宇宙論、物理学、生物学などあらゆる知識を縦横無尽!最速で138億年掌握」、さらに「17か国で続々刊行、世界的ベストセラー」とある。まさにビデオテープを早回ししたような、ある種爽快なテンポでビッグバン以降の全歴史が綴られている。発刊の問題意識は「いま人間は支配的な種として地球に君臨しているが、それは長い歴史の中では一瞬のことにすぎない。それを理解しない限り、私たちが地球とその生物圏に及ぼしている劇的で急激な変化を正しく把握することはできない」というものである。さらに「人間の生活は常に一貫して健康的になってきたわけでも、生産的になってきたわけでもない。…絶滅しかけたことさえある」とも指摘している。
無茶に端折れば、138億年前にビッグバンがあり、45億年前に太陽が誕生し、その太陽系の初期に生まれた30個の原始惑星のうち、現在の地球軌道上にあった2つの惑星が衝突して原始地球が生まれたのだという。そして、38億年前に海で生命が誕生し、「古典的な進化論の時代」となり、様々な生物の繫栄と絶滅の歴史が始まる。たとえば、誰もが良く知るジュラ紀の恐竜は、その前の「三畳紀の大量絶滅(おそらく小惑星の衝突が原因)」を生き抜き、地球上の四肢動物の90%を占めることになったという。三畳紀末期には200万年も雨が降り続いており、砂漠は消滅し、ジュラ紀になると森林と植生がさらに増大して、酸素濃度は約25%に上昇した。恐竜にとってますます好都合だ。つまり、三畳紀の絶滅で空いたニッチに恐竜が入り込んだことになる。
しかし、歴史は繰り返す(?)。ジュラ紀に続く白亜紀には「中央アメリカのユカタン半島に直径10キロの小惑星が衝突した」。世界的な地震、津波、大陸規模の森林火災、大量の酸性雨が降って多くの生物が死滅するに至った。「昆虫やわずかに生き残った植物を食いつないで生き延びることができた鳥類や哺乳類は絶滅を免れたが、鳥類型以外の恐竜は滅んだ」。今度はそのニッチを埋めたのが哺乳類ということになる。
長い地球史では、何回も小惑星との衝突が起こり、そのたびに想像を絶するような環境変化が起こったことを改めて思い知る。火山の大噴火もあった。何百万年も雨が降り続くこともあったという。そういう危機の連続、あるいは流れのなかに現在の温暖化をはじめとする地球環境の危機があるという認識も大切ではないか。しかも、直面する危機は自然の営みではなく、人間活動が作り出しているのである。
ホモ・サピエンスの登場と農業革命
それはともかく、31万5000年ほど前にアフリカの地に現生人類であるホモ・サピエンスが登場した。ここから人間の歴史が始まる。その歴史の大部分(「人類発祥から現在までの時間のおそらく95~98.5%」)において、人間は小さな群れをつくり、遊動しながら狩猟と採集を行って生活していた。従来、この長きにわたる狩猟採集社会は単に野蛮であるとみなされてきたが、生きやすい側面もあったと現在では評価が改まっている。「食料集めは1日のうちのわずかな時間で足りた」。のちの農耕民の平均労働時間が1日9.5時間、現代の会社員は8時間が標準なのに対し、狩猟採集民は6.5時間だったとみなされている。もちろん、その反面では「それ以後のどの時代よりも暴力が日常的に広がっていた」。
1万2000年前に最後の氷河期が終わるころ、大きな画期がやってきた。中東の「肥沃な三日月地帯」で、緑が増え、食べ物が豊富になったため、食料を求めて移動する必要のない時代が始まったのである。しだいに人口が増え、食料が不足する「定住の罠」が出来すると、植物の栽培や動物の家畜化へと進み、かくて農業、農耕が始まる。
農耕を始めたことによって、人類の歴史は複雑化や高度化の閾値を超えた。一言でいえば、生き物が自らを環境に適応させるのではなく、「環境を自分たちに適応させる」という大きな変化が起こったのである。道具(技術)や社会構造の急速な高度化や複雑化が加速度をつけながら進展し、やがて産業革命に至る道程が切り開かれた。産業革命によって社会システムの複雑さは一段と閾値を超え、技術の爆発的進歩、思想や価値観の革命的変容、生活様式の急激な変化など「カンブリア紀(生物多様性の爆発的増加期)に匹敵するよう」な激しい変化がもたらされた。
一足飛びにいえば、直近の2~300年で人類は「人新世」という地質学的スケールで新しい時代の扉を開き、「生命誕生後の38億年の歴史の中で、どの種よりも急速かつ劇的に地球に影響を与える存在になった」。ちなみに毎年絶滅している種の数を見ると、「過去5億5000万年に地球で起きた5回の大量絶滅に匹敵する規模」なのである。人新世の人類は6度目の大量絶滅を引き起こしているというべきかもしれない。
生命誌研究に学ぶ
ビッグ・ヒストリーという観点から次に取り上げたい本は、中村桂子『人類はどこで間違えたのか』(中公新書クラレ、2024年)である。これは生命誌の視点から人類史の問題点を析出している。生命誌とは、「40億年の歴史を持つ生きものたちの歴史の中に人間を置く」ことを基本とする学問である。今日、生命科学の急速な発展に見られるように生命・人間についての科学的分析は進化している。しかし、生命誌は「科学を基本に置きながら生きものを機械として見ることなく、生きものは生きものとして捉えることによって人間が生きる本来の道を探る」ものだという。端的にいえば、「『私たち生きもの』のなかの私」という自覚を出発点とする。
生命誌も先の『早回し全歴史』と同じく、農耕、農業の始まりが大きな曲がり角、画期であったとする。この時から人間として他の生きものとは違う道を歩み始めたのだという。「自然の中で暮らしながらも自然を支配するという気持ちが生まれ、それがどんどん強くなってきた」のであり、それが「現代の科学技術、機械論へとつながった」とみなす。
つまり、自然と人間を切り離し、前者を後者が操作・利用するという二元論的なアプローチが生まれたというのである。そうした農耕の道への疑問が語られ始めたのは20世紀末である。近代化のなかでの農業の科学技術化、工業化という大きなうねりが生じ、そこで用いた薬剤が自然破壊や健康被害などを引き起こした。さらに、農業の始まりがその後に続く拡大志向と格差の端緒だったと指摘する。
それでは本来の農耕、農業とは何か。「自然が循環で支えられていることを理解し、循環の中にある自然の力を思いきり生かして、生きものである私たちが心身ともに健康に生きることを支える食べ物を作る作業」だという。この文脈では有機農業が浮上する。中村氏によれば、農業は本来有機であるはずなのに、有機農業を実践する人が特別視されるようになってしまった。しかし、近代農業への疑問が広がるとともに解決策としての有機農業への期待が強まり、「EUは2030年までに有機農業の面積率を25%に」するという。
そして有機農業への関心の高まりとともに、「土」への関心が浮上している。土そのものへの理解が進み、その複雑さや重要性が認識されてきたのは最近であり、「土壌革命」という言葉も生まれてきた。考えてみれば、土は農業だけではなくすべての人間活動の基盤である。近代農業と同じく、土木・建設という作業が自然破壊につながっていることも多い。例えば、土砂崩れを起こさないためには、土中に水と風の道ができていて、そこで微生物などの多くの生きものが暮らし、そこに生える木がしっかりと根を張ることが必要だ。土によって、農業、土木、環境がつながって、しっかりとした生活基盤が形成される。
蛇足ながら、ここで三番目に言及したかった本がある。藤井一至『土と生命の46億年史』(講談社、2024)である。これは土と進化の謎に真正面から迫る力作だ。惹句に「生命と土だけは人類には作れない」とある。この手の本にはめずらしく現在6万部のベストセラーだという。本稿の最初の予定では、この本も紹介しつつ、全体を三題噺のようにまとめたかったが、もう許容された紙数を超えてしまった。
なお、誤解を避けるために最後に付け加えれば、いうまでもなく生命誌は農耕文明を否定しているわけではない。主に問題としているのは「拡大志向」を生み出した点である。ただ、私見では農業をはじめとする生産力の向上が、拡大志向を避け得たかは難しい問題である。人間はそれほど理知的ではないから、事ここに行き詰まらないと方向転換ができないのではないかという疑いを消すことはできない。もっとも、現在はまさに万事に行き詰まった段階であり、生命誌的知見も深化・拡大しているから、転換へのさまざまな動きが出てきてはいる。
それにしても、生命誌の問題提起は、ただ別の道(オルタナティブ)に乗り換えようというのではなく、農耕の始まりにまでさかのぼって「本来の道」を歩むべきだというラディカルなものである。90歳に近い碩学、中村氏はいう。「本来歩くはずの道を選択しそびれたのだから、『生きものである人間としての本来の道』を探せ」、と。
みやざき・とおる
1947年生まれ。日本評論社『経済評論』編集長、(財)国民経済研究協会研究部長を経て日本女子大、法政大、早稲田大などで講師。2009年から2年間内閣府参与。現在、本誌編集委員、生活クラブ生協のシンクタンク「市民セクター政策機構」理事。
コラム
- 沖縄発/沖縄戦から80年に思う沖縄国際大学非常勤講師・渡名喜 守太
- 発信/東京・杉並区政と区議会のいま―2025年春夏杉並区議会議員・奥山 たえこ
- 歴史断章/ビッグ・ヒストリーへの誘い市民セクター政策機構理事・宮崎 徹
- 追想/戦後80年、先立った友へ本誌前編集委員長・橘川 俊忠