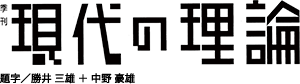特集 ● いよいよ日本も多極化か
自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌
人々の自発的で平等な協力関係で構成されるアソシエーション
労働運動アナリスト 早川 行雄
識者も憂う企業別組合の惨状
労働組合にとって何はさておき決して欠かすことのできない要件をひとつだけ挙げるとすれば、それは企業・資本から独立した自発的結社であるということだ。連合に限ったことではないかも知れないが、とりわけ連合傘下の大手労働組合の現状をつぶさに観察すると、これをもって自発的結社とみなしうるのかについて甚だ大きな疑問が生じることが少なくない。もとより現状といっても昨日今日の話ではなく、ここ半世紀ほどを射程に入れてのことだ。本誌に寄稿した別の論考でも適宜紹介してきたことではあるが 注1、労働組合に関心を寄せる有識者の間でも日本の労働組合の現状に対する憂慮が広がっている。
首藤若菜(立教大学教授)は23春闘時のNHK日曜討論で日本経団連十倉会長や連合芳野会長を前にして、賃金が上がらないのは労使の共犯関係と指摘し、その後毎日新聞の取材に対しても、企業レベルでみると賃金抑制策が経済成長を阻むという逆の動きを生んでしまっているとした上で「努力をしてこなかった労働組合にも重い責任があります。労組は企業サイドといわば共犯関係にあるわけです」と述べている。首藤は共犯関係の起点を2002春闘のトヨタショックに遡り、「奥田碩会長がトップだった日経連が『賃上げは論外』といった趣旨の発言を盛んにしていた頃です。トヨタの動きは業界横断的に他社にも広がり、企業や産業別労組の幹部が、一部組合員の反発をよそに『雇用を守り、国際競争に勝つには仕方がない』と連鎖的に萎縮していったのです」と振り返る 注2。ここで留意すべきは、雇用も賃金も会社ごとに分断された企業内労使交渉に委ねられていることが共犯関係の温床となっていることである。
日経新聞の労使の信頼関係に関するコラム注3で、藤村博之(JILPT理事長)は「欧米の労使は机を挟んで180度で向き合うのに対し、日本の労使は元々90度に座るイメージ。それがバブル崩壊後に同じ側に座るようになった」と指摘し、それは不況下で生き残り、雇用を守るためだったが、経済が持ち直す局面でも立ち位置は同じまま。労組幹部は経営者的になり、問題点を直言する力が弱くなったと批判している。戎野淑子(立正大学教授)も「結果であるべき労使協調が今は最大の目的になってしまっている。対峙することがなく、単なるなれ合いになっているところが少なくない」として労使関係の変貌を批判している。前出の藤村は25春闘についての朝日新聞の取材 注4に対し「定昇込みで5%の賃上げでは全く足りない。最低でも7%は必要だ」「賃上げが定着したというより、物価高でそうせざるを得なくなっている」と述べ、その背景として「いまの労使関係は異常」「労使は本来対面して意見を言い合うものなのに、労組も経営側と同じ席に座っている」と苦言を呈した 。いずれも企業内労使関係の劣化を憂慮したものだが、企業別組合の機能不全は、その組織形態に内在的な要因から生じていることに着目すべきである。
企業別組合の機能不全は連合春闘にも影響する。長らく諦めることなく連合運動への助言を続けてきた高木郁朗は、22春闘後に書かれて遺稿となった春闘総括のあり方に関する論考の中で、「政権に近接して、具申を繰り返すだけでは、とうてい実質的な賃金上昇はもたらされないことは明確なのである」と批判した上で「自民党の幹部や企業経営者と会食して、内意を通じ合っておくというやり方が、日本を国際的に二流国にしてしまったのだという、自覚をもつ労働組合幹部はけっして少なくないと思う」と心ある組合幹部に微かな期待を寄せていたのだが 注5、23春闘以降の展開は管理春闘の完成形に堕してしまった( 注1参照)。
すでに20年以上以前のことになるが、石田光男(同志社大学教授)は金属労協や主な産業別労組の賃金制度改革に関わる方針文書を通読した印象を「組合の改革論は経営の改革論と違いを見出すことは難しく、ここには労使関係の溶解という何とも不気味な構図が、個性や主体性の尊重やら、選択肢の多様化やらの麗しい言葉に飾られて我々の前に陳列されている」と述懐し、それが伝統的労使関係の協調的性格の帰結であるとしても、根幹にある対立が腐れば協調という花も萎れるのではないかと慨嘆していた 注6。これら産別方針は当然に企業別組合執行部の価値観を反映したものであり、藤村や戎野の懸念は少なくとも今世紀初頭にはその実態を晒していたことになる。
企業別組合とは何か
いまや懸念と批判を一身に浴びることとなっている企業別組合は、世界広しといえども類似品は存在しないとまではいえないにしても、日本固有のガラパゴス的組織形態(ガラ労)とみなして差支えなかろう。そうした現状にある日本的企業別組合の来し方は、そして行く末はいかなるものであろうか。
二村一夫(法政大学名誉教授)は企業別組合の「生成の根拠」と「存続の根拠」は一応分けて考えた方がよいとした上で、企業別組合が生まれたのは何故かに焦点を当てた議論を展開している 注7。二村は戦前の鉄工組合や友愛会など企業横断的労働組合と戦後の企業別組合を区別し、企業別組合生成の根拠に、熟練労働力の供給独占を基盤とするヨーロッパ型クラフト・ユニオンの伝統が不在であったことを挙げている。
鉄工組合や友愛会も熟練労働力の供給独占で労働市場をコントロールする力は持ち得なかったため、ストライキなどの争議行為は個別経営を対象とし、経営者も部外者の介入を拒否したことで企業横断的な団結が阻害された。労働者の要求も賃金・労働条件に加えて職種や学歴による不当な差別の撤廃にあったことから、経営者は上から意思疎通組織としての工場委員会を設置することで対応し、戦時中の労使一体思想で労働者を産業戦士に仕立てる産業報国会へと繋がってゆく。
二村は敗戦後の混乱期に未組織状態の労働者が企業というより事業所や職場単位で団結したことは自然なことで説明を要しないとしつつ、「敗戦と占領軍による民主化政策は、労働者の永年の不満を一挙に爆発させた。民主主義が、労働者にとっては、何よりも経営内での身分制の撤廃の要求となったのも、当然のことだった。この時に生まれた労働組合が、職場単位の組織であると同時に、工職混合組合となったことは、これまで述べてきたような歴史的背景を抜きにしては理解できない」としている。このとき結成された事業所単位の組合が自発的結社であったことは疑う余地がなかろう。
二村の論考であまり触れられていない企業別組合の「存続の根拠」をどうみるか。濱口桂一郎(JILPT労働政策研究所長)は、経済のグローバル化の中で企業リストラクチュアリングが余儀なくされた経済環境の変化により、企業、事業所レベルのさまざまな問題解決のために労働者を関与させる仕組みの必要性がクローズアップされてきたと述べている 注8。濱口はEU指令が労使協議を義務付ける欧州と異なり、日本では自発的結社とされる企業別組合が事業所内のさまざまな問題解決にあたってきたとし、「日本の企業別組合は戦前の工場委員会、戦時中の産業報国会を基盤として、戦後ホワイトカラーとブルーカラーの合同組合として結成され、その中心的役割は企業の労務管理機構における労働者との意思伝達機能にあった」と歴史的経過を語っている。
とはいえ、労働条件決定機能を主たる機能とする組織に事実上企業内意思決定関与機能を担わせていることには矛盾もあり、解決策として濱口は企業別組合に企業内意思決定に関与する法律上の公的機能を持たせるため、ユニオン・ショップ協定を通じた組織強制を行うことで、メンバーシップを管理職や非正規従業員を含む企業内すべての労働者に開くことに糸口を求めている。濱口も指摘しているように、すでに現行の過半数組合は純粋の自発的結社ではなく、一事業場の全ての労働者の利益を代表すべき責務を持った公的性質を有する機関なのである。
上記の歴史経過に登場する工場委員会や産業報国会とはどのような組織であったのか。工場委員会について東條由紀彦(明治大学教授)は「政府は団体交渉権獲得運動が拡大するなかにあっても、労働組合を法認しようとしなかった。代わりに、1919年から1920年にかけて、従業員代表を介した意思疎通機関である工場委員会を設置すると共に、民間企業にも同様の機関を設置するよう勧奨した」と述べている 注9。すなわち工場委員会は交渉主体としての労働組合を排除しつつ、争議行為などを除く機能の一部を代行させようとするものであり、天皇制軍国主義が深化する下で、国家を収斂軸としてその機能を純化した産業報国会へと収斂してゆくこととなる。
その産業報国会について渡辺章(筑波大学名誉教授)は、1945年の労働法制定に向けた労務法制審議委員会の第2回総会で報告された三井鉱山(単位産報)の事例を参照しつつ、「戦争期の工場・事業場別に組織された労働者組織(産業報国会)のあり方および活動を具体的の述べており、戦後一般的になった工場事業場別(企業別)組合の発祥なり、その社会的性質を理解する上で興味深い」と関心を示し、産報の実態については「概要はつぎのようである。報国会運動の主眼は「労資間ノ調整ヲヤル」こと、別言すれば「工場鉱山ノ中ニ於イテ意思ガ良ク上下疎通スルヤウニ」することであった」「産報は、会社との間で「懇談会」を構成するほか、健康保険組合、安全運動、能率運動、機関誌の発行、青年団など各種の事業を営んでいた」と述べている 注10。ここには労使の意思疎通機関とされた工場委員会の機能を純化して体現していた実態が顕れており、現下の企業別組合との機能的類似性も示されているとみなせよう。
このように歴史的経過を振り返るならば、現下の企業別組合が戦前の鉄工組合や敗戦直後に雨後の筍の如く自然発生的に誕生した事業者や職場単位の組合のような自発的結社ではなく、企業側の労務管理の都合に見合った組織に変質していることは明らかである。宮前忠夫(国際労働問題研究者)は多くの事例や学説を丹念に検証しながら、企業別組合は「トロイの木馬」であると断じているが 注11、ユニオン・ショップやチェック・オフ制度を介して、工場委員会や単位産報のような、企業側が上から組織して労働者を企業内ヒエラルキーに取り込むための懐柔組織に先祖返りして同様の機能を持つに至ったことが、現在に至るまで企業別組合が厳然と存続している根拠といえるだろう。
労働組合法と企業別組合
1945年(昭和20年)に憲法に先駆けて制定され(旧法)、1949年(昭和24年)の改訂を経て今日に至る労働組合法(現行法)において企業別組合はどのように位置づけられているのか、あるいはいないのか。旧法の制定に向けて設置された労務法制審議委員会には学識経験者、使用者、労働者及び貴衆両院議員からなる24名が名を連ねていた。政府や使用者側は職場に存続していた単位産報の温存を画策していた(ただしGHQの極東小委員会が解散させるべき団体に指定したことを受けて政府は産業報國会を解散させるよう指示した)。
一方、総同盟の松岡駒吉など労働側は、同一もしくは類似の産業で働く労働者によって組織された団体またはその連合体としての産業別組合を制限すべきではないと主張した。ここで留意すべきは、体制内改革を身上とする松岡ら総同盟右派の運動論・組織論においても、会社別従業員組織は迷妄であり、使用者に従属せず労使対等の交渉を実現するには、産別単一労働組合の組織と健全強固なる労働戦線の全国的同盟体の結成を重視していたことである(注7参照)。因みに総同盟左派の流れをくむ総評・全国金属の規約は単一の産業別労働組合として個人加盟を原則としていた。
労使の主張の隔たりは容易に埋まることはなく、第1章(総則)第2条に定める労働組合の定義は(現行法と旧法に大きな相違はない)、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」とされるのみで、自発的結社であるべきことは明示されているものの、企業別組合や産業別組合についてはいずれも排除していない一方で、どちらも自明の前提とはされていない曖昧な規定となっている。この曖昧さが禍根を残し、遂に企業内で労使関係が溶解する事態を招いたともいえる。
仁田道夫(東京大学名誉教授)は最近行った講演で、春闘機能の回復には労組法改正の制度改革が必要であり、ドイツ・モデル(ベトリープスラート)やフランス・モデル(工場委員会)を参考に、労組法上に企業別組合、産業別組合、地域組合、全国組合についてその要件と権能を明定すべきだと述べている 注12。これは運動論的には企業別組合の限界を乗り越えるべく、企業横断的な産業別労働組合や地域労組活動の強化を促した「連合評価委員会最終報告」注13とも通底する考え方と言えよう。これらの提起に関連して思い起こされるのは、1935年に制定された米国の全国労働関係法(ワグナー法)において、企業内組合を使用者の不当労働行為として禁止し、産業別労働組合の交渉力を強化することで労働者世帯の所得を向上させ、景気浮揚を実現した事例である。持続的賃上げを喫緊の課題とする現代日本の政労使会議においても、大いに学ぶべき歴史的教訓ではなかろうか。
労組法と企業別組合の問題を考察するにあたっては、組織強制であるユニオン・ショップ協定(ユ・シ協定)の問題を避けて通ることはできない。本人の意思に関わらず組織加入を強制するユ・シ協定は自発的結社の理念と背馳するからである。ユ・シ協定は会社が採用した従業員の協定労組への加入を強制し、除名・脱退により組合員の地位を喪失した従業員の解雇を会社に強制する制度であり、労組法上の根拠は同法第7条(不当労働行為)第1項但書「労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者が労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない」にあるとされている。
しかしこの但書は素直に読めばユ・シ協定というよりクローズド・ショップ協定を想定しており、最高裁判例も「労働協約においていわゆるクローズド・ショップ制の規定をもうけた場合に組合がその組合員を除名したときは,別段の定めのない限り使用者は被除名者を解雇すべき義務がある」としている 注14。しかも但書は組織強制を内容とする労使協定に基づく解雇は不当労働行為に当たらないとする、使用者に対する免罰規定と読むことができ、これをもってユ・シ協定の法的根拠とすることには疑問の余地が残る。
ユ・シ協定が既存の企業別組合の組織強化や交渉力の向上に資するとの建前で(実態としてはユ・シ協定がなければ多くの企業別組合が存続できなくなるので)、ユ・シ協定を擁護する見解が多数を占めてきたが、企業別組合の現状は、そうした期待との乖離を広げているとの疑念も広がっている。日本労働弁護団の会長を長く務めるなど労働者の権利擁護に生涯をかけた宮里邦雄弁護士は、労働組合の存在意義を語った論考の中で「ユニオン・ショップとチェック・オフは労働組合にとって団結維持の重要な装置となっているが、ユニオン・ショップは自ら労働組合を選択して加入するという自発的な団結の契機を欠いているが故に、団結意識が形成されにくいという面があることは否定しがたい。ユニオン・ショップとチェック・オフを獲得していることは強力な組合であることの証明であるとされてきたが、実際そうなっているか、団結の自己点検が必要ではなかろうか」とユ・シ協定の今日的実態に疑問を投げかけている 注15。
連合労働法講座の講師も務める野川忍(明治大学教授)は、ユニオン・ショップ制の法的意義を具体的に検証した論考において、「企業別組合が定着する中で、ユ・シ協定にもとづく解雇が実は少数派組合や少数派の労働者を駆逐するために行われたともの認められるような事例が裁判例の多くを占めるようになり、ユ・シ協定の効力を広く認めることで団結権が実質的にも強化されるとの思惑が破綻をきたしてきた」状況、さらに「ユ・シ協定が労働組合の組織拡大努力を弛緩させ、ひいては解雇の威嚇を通じた個々の労働者に対する抑圧に通じる実態が明らかになってきたこと」を理由に組織強制を内容とする労働協約は団結権自体を否定するような労働者に対してのみ効力を持つべきだとしている 注16。野川は結論として「 労働組合の自立した活動力が阻害される可能性も見逃せないことを 踏まえると、将来的には、ユニオン・ショップ制の必要がなくなる方向に向かうことが望ましい」と述べている 注17。
アソシエーション再考
最後に筆者の個人的体験から自発的結社について考えてみる。筆者は1976年に日産自動車に入社し6ヶ月の試用期間を経て会社と日産労組のユ・シ協定に拘束されて自分の意思とは関わりなく日産労組の組合員となった。当時は「塩路天皇」とも呼ばれた塩路一郎自動車労連(現日産労連)会長の時代で、例えば秘密投票の役員選挙も職場単位で開票され、批判票が出れば「犯人」を炙り出して徹底した説得活動で翻意させるほど締め付けが強かった。結果として役選であれ採決であれ常に信任・賛成100%という異常な組織運営が行われていた。こうした組織統制は労働組合の組織強化というより、「塩路天皇」の基盤を固めるための施策であった。
筆者はこのような強権支配に大いに反発し、日産労組に脱退届を突き付けて、日産に吸収合併されたプリンス自工の労働組合で合併後も少数組合として日産内に存続していた全国金属プリンス自工支部(後に日産自動車支部に名称変更)に加入した。「塩路天皇」の専制体制はいささか極端な事例ではあるが、ユ・シ職場においては逆説的に労組脱退持にはじめて自発性が発揮されることになる。支部に加入した後は、地域における典型的な企業横断組織である地区労や自発的結社の権化のような争議団とも交流する中でユニークな活動家諸氏と共に運動する機会を得た。分裂少数組合こそが、労組法が予定する自発的結社の内実を備えているという皮肉な現実がそこにはあった。
企業別組合全盛の時代にあって、少数派組合や地域に軸足を置いたコミュニティ・ユニオンが体現しているのは、カール・マルクスが階級や搾取が廃止された未来社会において、人々の自発的で平等な協力関係に基づいて構成される組織として定式化したアソシエーション 注18の原型とも位置付けられるが、実社会においては決定的な傍流組織である。いま考えねばならないのは、同じようにアソシエーションとしての性格を有する、働く者が中心となった労働者協同組合や市民が主体となって自主的な自治体運営を目指す地域主権主義(ミニシュパリズム)運動などと連携して、アソシエーションを社会の主流の位置に押し上げてゆくことだろう。
アソシエーションについては別途論じる必要もあるが、企業別組合への挽歌を哀悼の意を込めて謳い上げるのは、自発的結社たるアソシエーションのメンバーであるに違いない。因みに筆者が長年その下で活動してきた産業別労働組合JAMのAはアソシエーション(association)のAである。
(注1) 「連合芳野会長の春季生活闘争」(現代の理論第35号2023年8月)など
(注2) 「立教大教授・首藤若菜さんが見る23年春闘」(2023年3月1日夕刊)
(注3) 「労使はなれ合いより対峙」(内外時評2023年11月15日)
(注4) 「(ニッポンの給料)続く物価高、賃上げは不十分」(2025年3月13日)
(注5) 「「新しい資本主義」のもとでの春闘総括はどうあるべきか」(国際経済労働研究2022年8月)
(注6) 『仕事の社会科学』(ミネルヴァ書房2003年)
(注7) 「企業別組合の歴史的背景〔補訂版〕」(WEB版 二村一夫著作集)
(注8) 『労使コミュニケーションの新地平』(連合総研報告書2007年)第5章
(注9) 『「労働力」の成立と現代市民社会』(ミネルヴァ書房2016年)
(注10) 『労働組合法立法史料研究(解題篇』(JILPT 2014年)第1章
(注11) 『企業別組合は日本の「トロイの木馬」』(本の泉社2017年)
(注12) 「春闘システム-何が問題になっているか」(労働ペンクラブ2025年6月12日)
(注13) 座長中坊公平、委員に神野直彦、大沢真理ほか(2023年9月)
(注14) 大浜炭鉱事件・最二小判昭24・4・2
(注15) 「労働運動の活路はどこに」(ひろばユニオン2018年11月)
(注16) 「ユニオン・ショップ制の法的意義」(明治大学法科大学院2015年4月)
(注17) 『労働組合の基礎---働く人の未来をつくる』(日本評論社2021年)第2章
(注18) 『共産党宣言』(1848)『資本論』第1巻(1867)『ゴータ綱領批判』(1875)など
はやかわ・ゆきお
1954年兵庫県生まれ。成蹊大学法学部卒。日産自動車調査部、総評全国金属日産自動車支部(旧プリンス自工支部)書記長、JAM副書記長、連合総研主任研究員、日本退職者連合副事務局長などを経て現在、労働運動アナリスト・日本労働ペンクラブ会員・Labor Now運営委員。著書『人間を幸福にしない資本主義 ポスト働き方改革』(旬報社 2019)。
特集/いよいよ日本も多極化か
- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生
- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子
- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京
- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀
- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣
- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆