連載●池明観日記─第17回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫永井荷風の『あめりか物語』を読んで≪
永井荷風の「あめりか物語」を読みおえた。『荷風全集』(岩波書店、昭和38年)第3巻所収で、1903年からほとんど4年間アメリカに滞在した記録である。アメリカ讃美、そして日本批判の文章であるといえようか。文章によってはその当時には発表できなかったものもあるらしい。外国人にとってはこのような旅行記を比較研究する必要があるかもしれない。トクヴィルやディケンズのそれは19世紀、南北戦争以前のアメリカを対象にしたものであるが、全体としてトクヴィルはより肯定的にながめたとすれば、ディケンズはより暗くながめたといえるであろう。おのおのその祖国を異にしていたし、思想家そして小説家として見る目を異にしていたし、訪ねた地域も違っていた。

永井のアメリカ旅行はトクヴィルやディケンズの60年後、奴隷解放の宣言があった40年後であった。永井は黒人の暗い生活についてはほとんど描くことがなかった。彼は東洋人、特に中国人や日本人の暗い姿を描いただけでアメリカは自然も人間も美しいと描いたといおうか。このようにアメリカについて東洋人とヨーロッパ人とが書きあげたものは違っていた。アメリカ人が東洋人や黒人も同等に取り扱ってくれるということなど考えられなかったのかもしれない。永井のアメリカの婦人を賛美した文章から一節だけを引用してみよう。
「自分は西洋夫人の肉躰美を賞賛する第一人で、その曲線美の著しい腰、表情に富んだ眼、彫像の様な滑らかな肩、豊かな腕、広い胸から、踵の高い小さな靴を穿いた足までを愛するばかりか、彼等の化粧法の巧妙なる流行の選択の機敏なのに、無上の敬意を掃って居る第一人である……翻って日本の児女の態を見れば、彼等は全く此の能力を欠いて居る様に見えるでは無いか、尤も日本人と云へば非難と関渉の国民であるから、此の社会に養成された繊弱い女性は恐れ縮こまって、思ふ様に其の天賦の姿を飾り得たいのかも知れない」(p.337)
このような考え方は長い間日本国民を支配したのではないか。萩原朔太郎と高村光太郎もそうではなかったか(拙著『叙情と愛国』、明石書店p.75~76、p.119以下参照)。
しかし日本が侵略主義を掲げて国家主義を鼓吹する頃になると劣等感から優越意識へと転換して行った。日本はまず東洋において日本だけは白人化されたように考えたが、やがて自分たちを白人よりも優越した者としながら国民を戦争へと追い立てて行ったではないか。それは西洋文明に陶酔していたが一夜のうちに彼らを軽蔑し侵略の対象にするという武士社会の発想というべきものであろうか。それは一種の海賊的な思考ともいうべきかもしれない。その文明がたたえるべきものとすればその内容について深く考察してみなければなるまい。まさに帝国主義時代に他の文化をながめる目付きであるといえるのだが。まだアメリカは日曜日であれば海水浴もできないという禁欲の時代であり、日本は女学生は小説を読んではならないという時代であった。
チャイナタウンに対する暗い描写。そのような悲惨な日影の人生から彼らは今日のような教育を受けた世代へと育ってきたのだろうか。アメリカ社会の変化もあったであろうが、東洋人の身分志向的な生き方が大きな影響を与えたであろう。しかし永井はつぎのように考えたというのであった。
「吾等ら東洋人の負ふべき天職は、或人の云ふが如く東西の文明を調和すると称する夢の様な空想に酔ふ事では無く、男子は盡く花造りとなり、女子は盡く舞妓となって、全島国を揚げて世界歓楽の糸竹場たらしむる事では無かろうか」(p.334)
「一度ニューヨークに着して以来到る処火ならざるはなき此の新大陸の大都の夜が、如何に余を喜ばし候ふかは今更申上るまでもなき事と存じ候。あゝニューヨークは実に驚くべき不夜城に御座候。日本にては到底想像すべからざる程明く眩き電燈の魔界に御座候」(p.280)
永井はアメリカを見てほとんど絶望的な陶酔に陥っていたようである。彼は1907年にニューヨークを出発して10ヶ月の間パリに行っていた。彼の『ふらんす物語』も西欧文明の内容に関する言及はほとんどなく電燈のあかり輝く町に対する礼讃に終わっているというべきであろう。彼の文章は華麗な美文であり名文である。『ふらんす物語』は1909年に出版の予定であったが、発売禁止になった。それでその中の多くに多少手を入れていくつかの雑誌に掲載したようである。彼は「現実に見たフランスは見ざる時のフランスより更に美しく更に優しかった」といっているからほんとうに心酔してしまったのであろう。
「嗚呼わが仏蘭西、自分はどうかして仏蘭西の地を踏みたいばかりに此れまで生きてゐたのである」(p.545)とまでいった。発売禁止の前にはつぎのような文章まで入っていたという。
「髪の毛の薄い、歯の汚い血の気の失せた細君の顔は、日本と云ふ国では、化粧の技術を卑しみ、容貌の評論を許さず、総る恋愛の歓楽を否定し、女は全く、ロシアを征伐すべき未来の兵卒を産むべき、繁殖の機械に過ぎないと云ふ事をば、自分に向って暗示する如く、合点せしめる如く映ずる」(p.651)
ほんとうに永井は「いつも夢見るやうなしとやかな巴里の処女や、其れにも劣らず若々しく見える人の妻」などとパリの女性を描写してやまなかった。「あゝ黄昏! 其の美しさ、 其の賑かさ、其の趣きある景色は、一度巴里に足を踏入れたもの、長く忘れ得ぬ色彩と音響の混乱である」(p.548)
永井にとっては日本への帰国の道は「恋と芸術とを後にして、単調な生活の果てには死のみ待って居る東洋の端くれに旅して行く」(p.565)道であった。東洋というところは悲惨なところであり、労働の場所に過ぎなかった。帰国の旅にのぼることを「恐しい島嶼」(p.567)に戻るように思い、パリに残って労働者にでもなりたいと思うほどであったという。
このように西洋崇拝といえる境地にまで落ちこんでいた日本人を何が西洋征服までも夢見るようにさせたのであろうか。日本の伝統的な武士社会というものは自分より巨大な存在であるならば服従しなければならないと考えるのであるが、その一方でそれはいつかは自分が征服しなければならない存在であると考えるのであろうか。最初は東洋の覇者になることを夢見たが、それが許されないとなると苦しんだあげくに無謀なる道へと進んで行ったといおうか。劣等感から優越感へと飛躍したということであろうか。
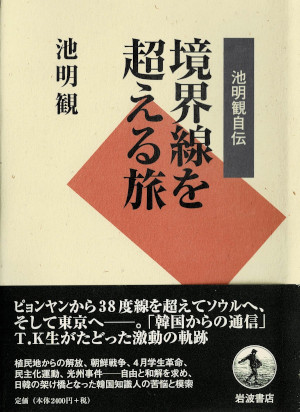
『池明観自伝 境界線を超える旅』(岩波書店、2005)
高村光太郎は1910年、ヨーロッパ留学から帰国した時には「猿の様な、孤の様な、ももんがの様な、だぼはぜの様な、麦魚の様な、鬼瓦の様な、茶碗のかけらの様な日本人」といったのだが、第二次世界大戦の時には戦争参加の詩人に突然変わってしまったではないか。そして1945年以降は懺悔の詩人に急変した。そこに論理も思想も欠如していたように思われる。ただ時代の流れに従って行ったのであろう。そのように永井も高村もアメリカやヨーロッパを見た時に、その文化、その文化の内容についてはそれほど深めなかったのではなかろうか。自分と異なるものに心を引かれ、日本を劣るものと考えたが、ある日これに妬みを感じて敵対視する態度を取り、暴力を宣布したということではなかろうか。相手側の文化と伝統、正義と自由、そしてそれにともなう苦痛と苦悩など深く掘り下げようとしなかったのではなかろうかと思われる。
永井の『あめりか物語』と『ふらんす物語』はまさにアメリカ特にフランスに対する陶酔の物語であったのではなかろうか。永井は第二次世界大戦前後はどのような姿勢を取ったのであろうか。事典によれば現実から逃避して江戸戯作に身を隠していたという。彼は耽美的な作家であった。これに比べて中国とか韓国が見たヨーロッパとかアメリカはどうであっただろうか。安昌浩(アンチャンホ、1878-1938年、亡命して独立運動をリード)の場合は当然にもアメリカの社会と政治に注目した。そしてそこに流れるキリスト教的倫理のことについて考えた。日本と韓国はアメリカ社会における中心的課題をおたがい異なった目でながめたのであろう。韓国の初期アメリカ移民のほとんどはキリスト教に帰依した。日韓の近代化について考えるとすればこういうところにも注目して思想史的な研究をしなければなるまい。日本の場合における政治家や思想家の考え方もさがしてみなければならない。こういうことは私にとっては日暮れて道遠しということであるのだが。
一つだけ特にわれわれが共同で考えてみるべき課題がありそうである。日中韓の移民たちがどのようにしてアメリカ社会において教育を受けて中上層のステイタスに向けて向上することができたかということである。韓国の移民はごく初期において日本の朝鮮統治政策によって禁じられたが、今日においては韓国人のアメリカ移民は終戦後急激に増加して日本のそれを越えている。アメリカ移民という問題で日中韓を比較してみることは興味ある課題ではなかろうか。私は今日においてはどこか一国を中心として考えるよりはこのように日中韓を比較してみることが重要であろうかと思っている。(2012年11月15日)
≫慶尚北道と慶尚南道≪
『三国史記』を時たま読んでいる。新羅が三国を統一する前の三国の歴史を比較してみることは有益なことであると思える。新羅と百済の使節がしばしば唐を往来しながら朝貢をあげていた朝鮮半島の情勢がとても緊迫していた頃である。唐が最後には新羅と一つになって高句麗も百済も滅亡に追いやるのであるが、特に百済本記によると唐はどうして隣りあう国どうしが相争うのかといいながら「沮兵安忍」すべきではないかといって「共篤鄰情即停兵革」をすすめたのであった。
これに対して百済武王は使臣を派遣してあやまったといわれるが、そのことは外を繕っただけであって実際は「内実相仇如故」であったという。そのうち唐は高句麗との対立で新羅に傾くようになるのではないか。百済の義慈王(ウィジャワン)の時の唐の高宗の諭書はかなり厳しいものであった。この時代における三国の国家戦略を比較研究してみる必要があるのではなかろうか。ある意味では今日朝鮮半島において南北が対立していながら中国に対して示している姿勢とあまりにも似ていはしないか。今の中国は唐と同じような態度を示して実利を目ざしているといえよう。(2012年11月16日)
北東アジアの文化において音楽と楽器があまり成長していない理由をどこに求めることができるか。東洋の宗教においては、音楽はそれほど重要ではなく、沈黙が強調されたようである。西欧においては教会音楽が成長して大きな芸術世界をつくりあげたように見える。東洋の宗教はより自然宗教的であるのは、いわゆる人格的な神を前提としなかったからであろう。キリスト教においては神は語る、Deus dixitとはっきりと人格的な神を前提としていた。音楽の問題は宗教がこのように言語的であったということ、言語によるコミュニケーションから始まったということと関係があるのかもしれな。そして西洋の楽器はいかに科学的な道を歩んできたことであろう。もしかしたらそのことは西欧における科学の発達とも関係がありそうである。人間の力を尽して神をたたえようとしたのではないか。音楽から科学へと考えを進めることはあまりにも飛躍した発想だといわれるかもしれないが。(2012年11月17日)
午前中にソウルから帰ってきたという李昇万(イスンマン)牧師と電話で話しあった。李は 呉在植(オジェシク)の自叙伝が出版されたという消息を伝えてくれた。私がソウルにいたとすればそのような集まりで、もっと詳細に呉在植についてはもちろんのこと、李昇万についても韓国の民主化運動行においてどのようなことが行われたかについて語りえたかもしれない。朴正煕政権の崩壊のために国内外の勢力を大きく動員することができたのは李昇万の努力に負うところが実に大であった。しかし彼は自分の働きはいつも隠してきた人である。私は彼に対して釜山と大邸、慶南と慶北について話した。1979年に金載圭(キムジェギュ)が朴正煕を暗殺したのは慶南北が政治的に分裂しているということを示している(注:金載圭は慶南の人であり、朴正煕は慶北の人)。実際、朴正煕の退陣のために大々的な示威をくり広げたのは釜山一帯であった。慶北の大邸は長いこと深い沈黙にひたっていたではないか。
先にもふれたことだが、南の政府に南の国民が積極的に参与するようになったのは、1950年の朝鮮戦争の後ではなかったかと私は思っている。南の国民の多くは諦めたといおうか、現実的になってきたといおうか、北の体制に対する観念的な憧れ、統一という政治的スローガンを放棄するようになった。そして彼らは積極的に南の政府に参与するようになって、終戦後、李承晩政府に参加していた北から南下していたいわゆる「以北勢力」は南の政権から後退せざるをえなかった。そこで北から南下した人々の子弟は官僚になる道などは放棄して学界とか医療系のような方向に流れ、やがてアメリカへの移民の道が開けると、その多くがこれを選んだ。このような現代史の底辺のようなものをさぐらねばならないであろう。
このような複雑な過程において政治勢力の中における慶尚道出身の力は大きくなり、だんだんとその勢力の中で慶尚南北道とは多少政治姿勢または政治における人間関係を異にするようになったといえよう。慶南の方が慶北よりは西南部の全羅道勢力に対して包容的であったのではなかろうか。それで慶南出身の盧武鉉(ノムヒョン)が全羅出身の金大中の勢力の中にとどまっていたであろう。そして彼が執権するようになると全羅道勢力との連立政権のような傾向を示したといえよう。これは慶南の勢力が国民勢力化しようとした動きであったといえるかもしれない。
この度、文在寅(ムンジェイン)と安哲秀(アンチョルス)が慶南勢力と単一化に成功し、 朴槿恵(パククネ)は朴正煕時代からの慶北勢力を結集させようとしている。この結果がどのような動きを見せるかは興味深い。私は文在寅の慶南勢力が勝利して湖南勢力をかかえ込んで全国化の道を進んで行くことが望ましいと思っている。そして朴正煕に対する悪夢の時代ができるだけ早く終焉を迎えることができればと思うのである。
軍事政権の時は、その中心勢力は慶北勢力で、慶南北が一つの政治勢力があるかのように見えた。しかしそこから、慶南北がたがいに対立するという政治的版図が成長していた。釜馬事態(注:1979年釜山・馬山地域の反朴運動)以後、慶南出身の金載圭(注:当時中央情報部長)によって朴正煕が暗殺されるという事件が起こった。

このような現実の動きに対する政治史的または政治思想的解釈はとても必要なことではなかろうか。長い間続いた儒教的対立の歴史がこのような過程を経ながら克服されて行くのであろうか。歴史は革命を必要とするのであろう。革命はただ未来を遠く明るく照らし出して見せてくれる。このように歴史を肯定的に評価しながらも厳しく問い詰めねばなるまい。韓国現代史に対する異見といおうか、意見といおうか。単なる政権交替が革命でもあるかのように興奮した時代は過ぎてしまった。これからは雑音のない大統領選挙で政権が交替されて行くであろう。アメリカでもケネディやマルチン・ルーサー・キングが殺害されたような歴史は過ぎ去ってしまった。オバマ大統領が再選されたではないか。韓国においても騒々しくない民主主義へと発展して行くであろう。慶南が全羅道勢力と共にする政権を生み出して全国的な政権となりうるとすれば、実に興味ある政治風景がくり広げられるのではなかろうか。そしてつぎには彼らが慶尚道出身以外の候補者を支持するようにまでなるとすれば、韓国の政治は地方政治的時代を完全に抜け出すことができるといえよう。そして南北統一の時代へと準備しなければなるまい。
1946年10月1日に一大暴動といわれた騒動を起こした大邸、1960年4・19以後には静かになり、やがて61年の軍事クーデター後には朴正煕の庇護勢力に化して行った慶北といわれてきたではないか。1979年、釜山は軍事政権に対して巨大な抵抗をなし、ついには朴正煕暗殺の金載圭を生み出したといわれた慶南ではないか。この政治風土が今度の選挙の底辺には今も依然として残っているのではないか。歴史は厳として存在し、革命はそこから吹き出されるときの声であり、火山の噴出はその風土に修正を求める警告であるのではなかろうか。朴正煕は釜山で大々的なデモが起こった時、あのデモ隊の中から数百名数千名を捕え上げれば事態は収拾されると考えたといわれてきた。今は民主的な政権交替の時代である。韓国もいつになればアメリカのように静かな選挙を行いうるのだろうかと思いながら、目をつぶる。(2012年11月17日)
今日の午後のKBSニュースであるから、韓国では昨日放映されたものであろうか。文在寅が選挙演説をしながら李明博は在任中何もなし遂げていないから0点をつけるべきではないかと大声を張り上げる場面を見た。そうかと思うと国民の間には国産の原子炉も海外に売り込んだし、韓国をして世界8位の貿易大国に育て上げたではないかなどといってマイナス点をつけるよりはプラス点をつけるべきことが多いではないかという人も多いという。文在寅はあまり知恵のある人のようには見えないので気がかりである。李明博がうまくなしえなかったこともあるであろうが、経済政策はかなりの成功を収めたといえるのではないか。歴代大統領の場合その任期末になると人気が地に落ちたのに比べると、それほど野党が彼の人気を引き下げようと躍起になっているのに比べて彼はよくも耐えているような気がする。それに与党内でも李明博系とか朴槿系とかの対立はかなり激しい。そのような扇動調の遊説が国民に受け入れられる時代は過ぎ去っているのではなかろうか。
野党の民主党が人物においても、政策においても貧弱であるような気がしてならない。この前の国会議員選挙においても野党が自らにとって有利な状況を十分利用できずに敗北したといわれた。与党と共に人物欠乏の時代に入っているといわれる。政治的人間に対する軽蔑が一層拡大して行くこの時代をいかに対処するのか。それで安哲秀のような医学徒も急に現れてきたではないか。朴槿恵はなくなった朴正煕を掲げ、文在寅も故人となった盧武鉉を掲げるのだが、それではそのような人物に批判的な人びとはどうするつもりであろうか。今度大統領選に出てきた人々はほんとうに良識の人であればと思ったのだが。できるだけ楽観的に考えようとするのであるが、韓国の民主主義には危機が訪れてくるような気がして心配でならない。(2012年11月28日)
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)
池明観さん日記連載にあたって 現代の理論編集委員会
この連載「韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート」は、池明観さんが2008年から2014年にかけて綴ったものです。TK生の筆名で池明観さんが1970年代~80年年代に書いた『韓国からの通信』は雑誌『世界』(岩波書店)に長期連載され、日本社会に大きな衝撃と影響を与えました。このノートは、折々の政治・社会情勢を片方に見ながら、他方でその時々、読みついだ文学作品、あるいは政治・歴史にかかわる書籍・論文を参照しながら、韓国の歴史や民主化、北朝鮮問題、東アジア共同体の可能性などを欧米の歴史・政治と比較しながら考察を加えています。
今回縁あって、本誌『現代の理論』は、著者・池明観さんからこの原稿の公表・出版についての依頼を受けました。第12号から連載記事として公開しております。同時に出版の可能性を追求しています。この原稿の出版について関心のある出版社は、編集委員会までご連絡ください。
