この一冊
『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』(樋田毅著 岩波書店、2018年2月)
戦後最悪の言論テロ事件、記者人生賭け追及
ジャーナリスト 山野 泉
1987年5月3日の「憲法記念日」の夜、朝日新聞阪神支局で目出し帽の暴漢が散弾銃を発砲、小尻知博記者(享年29)が死亡し犬飼兵衛記者が重傷を負う凶行が起きてから31年―。この事件など「赤報隊」による一連の襲撃・脅迫事件は2013年春ですべて時効となった。言論に対する戦後最悪のテロであるこの事件の迷宮入りは、いまなお言論の自由に対する不気味な重圧となり続けている。
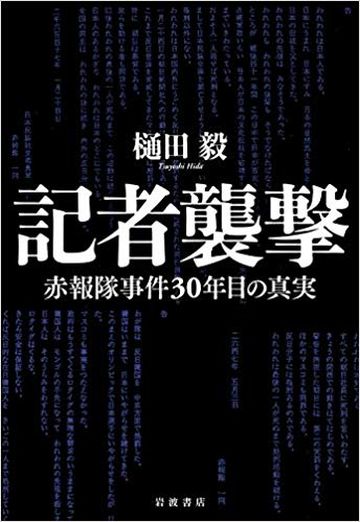
(樋田毅著 岩波書店、2018年2月、240頁、2,052円)
「赤報隊」事件解明を「記者人生を賭けた使命と思い定め」、事件発生当初から30年余り犯人を追い続けてきた元朝日新聞記者による迫真のノンフィクションである本書は、厳しさを増す言論・報道の自由の閉塞状況打破を目指す労作だ。
▼ ▼ ▼
筆者は阪神支局襲撃事件の3年前まで同支局に勤務。事件発生当初から時効成立までは同社の特命取材班メンバーとして、さらに時効成立後も取材を続け、同社を完全退職後に個人の責任で本書をまとめた。朝日新聞の新入記者研修では事件現場である阪神支局での講師役も務め、NHKの再現ドラマ「赤報隊事件」では草彅剛が樋田役を演じた。
事件を知らない世代も多くなったため、まず序章では物語仕立てで事件経過を追う。一連の事件は1987年1月から90年5月までに発生した計8件で、朝日新聞の東京本社、阪神支局、名古屋本社社員寮、静岡支局の4事件と、中曽根元首相・竹下首相脅迫、江副元リクルート会長宅銃撃、愛知韓国人会館放火。いずれも「赤報隊」名による犯行声明や脅迫状が送られた。朝日新聞関連の犯行声明は「われわれは日本を愛するゆえに、日本を否定するものを許さない。すべての朝日社員に死刑を言いわたす。ほかのマスコミも同罪で、反日分子には極刑あるのみだ」との内容。
中曽根・竹下脅迫は靖国・教科書問題、江副脅迫は朝日新聞への広告問題、韓国人会館放火では盧泰愚大統領来日などをそれぞれ「反日的」として、処刑するとしている。筆者は「結束の固い2~3人の少数グループによる犯行の可能性が高い」とみる。
警察庁は事件から約10年後の1998年に「赤報隊の可能性のある9人」のリストをまとめ、集中捜査を指示したが「総合的に判断してシロ」との結論を出したが、筆者はこれに納得できず数年前から再度、関係者の徹底取材を進めた。
▼ ▼ ▼
「新右翼関係者とその周辺」の章では▽ヘイトスピーチなどにかかわるグループの理論的指導者ともいわれる元ネオナチズムの活動家▽以前関西で活動していた右翼の研究会関係者▽経団連会館襲撃事件などで服役、1993年に朝日新聞東京本社で拳銃自殺した新右翼の「生みの親」の一人、野村秋介氏▽名画「マルセル」盗難事件(時効成立)に関与したとされる元教師▽民族派活動家の育成塾を開く元陸上自衛隊員▽阪神支局事件後、神戸支局に不審な電話をしてきた人物……など。結局、犯人を突き止めることはできなかったが、マスコミがタブー視しがちだった右翼、特に1970年の三島由紀夫割腹自決の衝撃の中で誕生した新右翼の実態に迫る。
「ある新興宗教の影」の章は、新興宗教団体α教団と関連団体について。α教団などは「霊感商法」や「スパイ防止法」制定運動などを批判する朝日新聞や『朝日ジャーナル』と緊張関係にあったことから、捜査当局も重大な関心を寄せていた。筆者も、同教団は事件当時、朝日新聞を敵視していた上、韓国で銃砲メーカーを経営し、日本各地に系列銃砲店・射撃場を持ち、信者に射撃の名手もおり、秘密特殊部隊もあったなどとし、阪神支局事件の3年前に起きた同教団系の内部テロ事件(時効成立)などの暗部を暴くが、「赤報隊」事件への関与を示す「物証」は見つけることができなかった。
取材で筆者が会ったのは、右翼関係者だけでも約300人に上る。「すべての朝日社員に死刑を言いわたす」(犯行声明文)とする犯人を探す取材は、命がけで困難を極めたが「仲間を殺された事件を解決したい想いの方が、恐怖に勝ったから続けられた」という。
迷宮入りに終わった警察の捜査については①警察庁は中曽根・竹下脅迫事件を「極秘中の極秘」とし(中曽根事件発生は朝日が9年後にスクープ)、特に竹下事件は関係府県警にも知らせず、捜査した痕跡もない。それが捜査員や取材を混乱させた②事件直後、警察庁の公安二課長(右翼担当)が「私は右翼を取り締まり対象とは考えていない。彼らの愛国心、愛国的行動は評価しなければならない」と言った例などは、当時の「捜査機関と右翼のある種の癒着関係」を示すのではないか③「リスト」の9人の中には、捜査当局のポリグラフ(うそ発見器)テストを受けていない者もあり、受けた者も「質問項目が物証をめぐる内容ばかりで、思想性についてはチェックできない」との捜査刑事の不満もあった―などの苦言も呈する。
▼ ▼ ▼
朝日新聞社の対応についても①報道トラブルをめぐり、朝日新聞社長が野村秋介氏と東京本社で会談(野村氏はその際に拳銃自殺)したのは間違いで、やむを得なかったとしても経緯を公表すべきだった②阪神支局事件の翌年、朝日新聞とα教団系新聞の幹部同士が会食(その後『朝日ジャーナル』を廃刊)したのは〝談合〟だったのではないか―などの問題点も明らかにする。
終章では、元取材チームメンバーの想いなどを紹介しながら、事件から30年間を経た現在の言論状況や社会状況の変化を考察する。時効成立時、ある右翼活動家は「赤報隊が逃げおおせたのは右翼にとって好都合だ。記事次第では赤報隊がまた動き出すぞ、という無言の圧力をかけ、社会の重しの役割を果たしていく」と予測した。その予測どおり、事件が未解決であることが言論・報道の自由の閉塞化を促す役割を果たし続けている。そして、事件から約10年後に旗揚げした右翼の集合体「日本会議」が、今や日本政治を方向付けかねない影響力を持ちつつある。
だからこそ「赤報隊」事件を問い続けるとともに、言論の自由圧迫に屈しない「覚悟と矜持」が、自分も含めたすべてのジャーナリストに問われているという。そして「赤報隊」に「もしこの本を読んだのなら、名乗り出て事件の真相を明らかにするべきだ。逃げ隠れするな」と呼びかけて本書を結ぶ。
やまの・いずみ
ジャーナリスト。本誌編集委員。
この一冊
- 『記者襲撃』ジャーナリスト/山野 泉
- 『グローバル環境ガバナンス事典』筑波大学ビジネスサイエンス系准教授/礪波 亜希
