連載●池明観日記─第24回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫フォークナーとアメリカ史の「創世記」≪
人間の歴史、それはなんとジグザグ、紆余曲折の過程であろうか。それは反理性的な過程であるといわねばなるまい。マルクスの歴史観は人間理性内における歴史といわねばならない。だからそれに従うという共産主義は世界史において破綻に陥らざるをえなかった。人間の歴史であるにもかかわらず、それは人間の理性を超えて進行する。それは実に非理性的であるといわなければならない。しかし流い歴史を振り返ってみると、そこには一つの法則があると感じざるをえない。それこそ目に見えない手がそれと共に働いたと告白せざるをえないようになる。アメリカは今日の世界史において多くの民族が織りなす版図の縮図であるかのようにみえる。その意味でアメリカは十分に世界史の象徴でもあるといえるかもしれない。

いま世界史は戦争なき時代に入りつつあるといえよう。人間の予想などを越えてである。だれも世界大戦のようなものを予想することができない。あれほど恐るべき武器を製造して世界戦争を予想し、そこにおける勝利を誓おうとするのであるか、実際において戦争なき時代が徐々に迫ってきているといわざるをえないであろう。この点で私は、この時代、この地に生をうけたことを感謝すべきであろう。
北が共産化されるといわれると、主に比較的上層に属していた者たちが北緯38度線以北から以南へと南下してきた。南ではかつて親日派であったといわれた人びとや北から南下してきた人びとが支配層を占め、反米的であった民衆とか知識人を抑圧する時代がくり広げられた。キリスト教は北においては弾圧され追放されたが、南においては一種の特権にあずかったといえようか。そこにはキリスト者の功過があったと言えるかもしれない。そのような時には自分が抱いていた考えに固執するのではなく、歴史に対する自分の無知を認め、新しい歴史を受け入れ、自分の考えを修正するという勇気ある知性が求められる。このような立場で書きつける歴史、私は歴史に対して間違った見方をし、誤った働きをしたと告白する知性によって書かれる歴史こそキリスト教的歴史観といえるのではなかろうか。謙虚な知性による歴史である。
私が書いてきた歴史は常に修正されなければならない歴史であり、それは暫定的に臨時の場を占めるものであるといわざるをえない。それは歴史というより一つの見解であったといえるかもしれない。繰り返すが、私は南における民衆が南の政治と支配層を肯定しここに参加することになるのは1950年の6.25、朝鮮戦争以後であると考えてきた。そこで北から南下したいわゆる越南してきたといわれた勢力は政治の前面から後退するようになる。このような終戦以後の歴史的経験に従って南にいた南出身の人々と北から南下した北出身の人びとは歴史的姿勢を異にしてきた面があったといわねばなるまい。その間、北では歴史をたどることのできる自由な空間が消えてしまい、歴史が歴史的現実から追放されたといえよう。そこでは歴史が徹底的にイデオロギー化され執権勢力に奉仕したといわねばならない。南においても歴史はこのように南北が対立してきた歴史的現実から来る歴史的歪曲をどれほど克服したといえるであろうか。韓国の歴史、特にその近現代史は実際の政治における対立のように複雑にからんでいるといわねばなるまい。私は私自身の歴史記述に対して、常に自責の念に捉われている。それは南の政治的イデオロギーを超えることができなかった。それこそそれに隷属したある意味では反民衆的だという批判を受けるべきものではなかろうかと思っている。私は韓国の近現代史を新しく書き直すべき義務をせおっているといえよう。このような立場から私は今日も歴史教科書について意見の衝突がしばしば起こってくるのはほとんど避けることのできないことであると考えるのである。
再びフォークナーの作品を読み出した。今度は『アブサロム、アブサロム!』という1936年の作品である。アブサロムは早死したダビデ王の息子の一人であるが、この小説の前の方にはつぎのようなことばが出てくる。
「なぜなら四十三年も経てばどんな相手だってわれわれをびっくりさせることも、心から満足させることも、激しい怒りを覚えさせることもなくなってしまうだろうから」

『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
われわれはこのことばにおいて日本統治時代を思い、朝鮮戦争を考えるようになる。日本統治は68年前に退いたし、朴正熙の軍事独裁は34年前にたおれた。朝鮮戦争は63年前に起きた北からの侵入ではないか。このような悲劇にわれわれは 60余年も対決してきながら忘れまい忘れまいと誓い憎悪心をかき立てたではないか。しかしフォークナーは「絶対に許すまいと思った古い決意の中で、張り続けてきた孤独でねじまげられた年老いた女の肉体の発する叫び」と冷たく表現したのであるが、われわれはこのことばをかみしめる必要があるかもしれない。この齢で私が過ぎ去った惨劇にからまった歴史を再び回想しようとすることは哀しいことといわねばなるまい。歴史がそれを抜き取ってしまうとすれば、私は芸術とか小説などからそれを探し出そうとしているといえるかもしれない。
歴史の自然への還元は不可避的なものである。フォークナーは『アブサロム、アブサロム!』において「<運命>の妻である<自然>」といったのではないか。フランス革命の後を追う反動の歴史、われわれの場合もその道をたどりながら朴正熙の娘が登場し、民主化を継承するという民主党の堕落が続くのではないか。このすべてが歴史の自然現象というものであろう。色浅い人間の歴史が時間とともに希釈され自然に帰って行く。個々人において忘却に追いやられてしまうように。歴史の自然化とそれに抵抗する歴史の人間化といおうか。生きた革命を口では継承するといいながら、実際は堕落へと転落して行く歴史ではないか。歴史の自然化を誰が防ぎうるといえようか。われわれ誰もがそのような時間のなかに生きているのではないか。『土地』も『太白山脈』もそのような歴史に対するごく人間的な抵抗の悶えではなかろうか。
歴史に記録して置くということ、それがまさに忘却されて消滅していき、自然に戻ろうとすることに対する人間的抵抗ではないか。しかしわれわれが死に抵抗しえないように誰がその忘却に対する抵抗に成功することができようか。いつか地球が消滅すれば地上のすべてが永遠の忘却に帰っていくのではないか。このような「政治日記」を書き続けながら私自身、このことがいかに無意味であるかを反芻している毎日である。時間と永遠の戦い―その敗北を反芻しながらも挑戦する。これが悲劇であるということを知りながらも挑戦するのだからその悲劇性、いやその愚かさはいっそう濃くなるといおうか。(2013年6月6日)
フォークナーの難渋な文章を密林の中をさまようようにして読み続けている。ヘンリーは彼の姉と結婚しようとするチャールズ・ボンが自身の異腹の兄であることを知って彼を殺害するようになる。だがチャールズ・ボンはミシシッピ大学で羨望の対象であるというよりは絶望の対象であるという。羨望は自分もそのような幸運に恵まれればそのようなことができる時に起こるものであり、とうていそのような幸運に恵まれるはずはなく、そこに到達することなどありえないと思うようになれば「絶望」の対象とならざるをえないという。実際われわれの周囲にはそのような意味における羨望の対象ではなく、われわれを激怒させるような対象がいかに多いことであろうか。個人に対してだけでなく国家に対してもこういう場合が少なくないはずではないか。そのようなことからくる反米主義もありうることではないか。またそのような感情を放棄してひたすら現実を受け入れる親米主義もありうるといおうか。フォークナーはつぎのように書くのであった。
「羨望というものは偶然さえなければ断然自分の方が上だと信じる相手に対して、また自分がこれまでよりも僅かでも幸運に恵まれれば、いつかはきっと手に入ると思うものに対して感じるものだからだ」
われわれの対日感情と対米感情とをこのことばに比較してみればどのようになるのであろうか。羨望の対象としてのチャールズ・ボンと彼を取り巻く学友に対してフォークナーはつぎのように記録した。
「ボンはその贅沢そうな快楽をほしいままにする時の異国風でほとんど女ものの服装で、学友たちの前をぶらぶら歩きながら、もう飽き飽きしたよ、とみんなに話すたびに、彼らは驚きと悔しいがどうしようもない激怒を募らせるばかりだった」
そこでヘンリーは妹のジュディスに対して近親相姦的感情を抱くようになるのであった。(2013年6月7日)
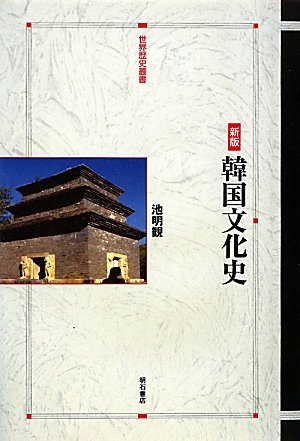
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
1860年代の初めの南北戦争から1世紀半が過ぎればアメリカに黒人大統領が生まれるであろうということを知っていたら、アメリカの白人の誰が黒人のアメリカ入国を認めたであろうか。アメリカの歴史は南北戦争後、後戻りはしないことにしたといえるであろう。とは言っても、歴史においてはこれから現れてくる多くの重要なことが今日のわれわれの目には隠されているといわなければなるまい。
1967年、私がニューヨークのユニオン神学校に行っていた時であるが、ある論者が講演をしたさい、われわれ異邦人の目にはまったくわからないことであったが、あの人には黒人の血が混っているといって異端視していた。マーティン・ルーサー・キングの民権運動を支持してユニオンはとても開放的であったのにもかかわらず、そのような有様であった。理解し難いフォークナーの作品を読みながらそういった過去を思い出し、人間と歴史そしてアメリカ社会の歴史認識を思わざるをえない。世界史におけるアメリカ社会の意味ということを考える。
フォークナーは8分の1が黒人の血だという女性を問題にしていた時代を描いたのであった。南北戦争後43年で、もうそのような歴史は忘却の彼方に押しやられたといいながらもそうであった。今日においてはわれわれもアメリカにおいて黒人に対する寛大な姿勢に驚いているといっているのだが。アメリカ史の世界史的な性格といおうか、意味といおうか、先駆的性格といおうか、そのようなことを何度も考えざるをえない。フランス革命に比べればアメリカの革命には反革命的反動がほとんどなかったのではないかと思われる。アメリカ史はたとえ遅々としたものではあってもやはり世界史に対して先駆的な立場にあるような気がしてならない。人種的に見てもアメリカ社会は世界の縮図であるとくり返して思うようになる。アメリカが進む道を世界史が後からついて行くように見える。歴史にはそのような見本ともいうべきものが選民の歩みでもあるかのように設定されるのであろうか。
歴史に対する不可思議性または歴史に対するある種の懐疑論をまた考える。それこそ神のみぞ知り給う歴史だといわれなければならないのだろうか。歴史における見えない手を思いながら、これからの歴史に対する謙虚な姿勢を私たちに求めるのが歴史ではなかろうか。われわれはややもすればそれを拒み、それに対して目をつぶろうとする反動的な姿勢を示しているような気がしてならない。それは北朝鮮だけではあるまい。そのような発想がもたらしてくれるネメシスをアメリカほどよく克服できる国はないのかもしれない。神は世界史のなかにいかなる時にもそのようなモデルとしての歴史を啓示するものだといおうか。まるで旧約聖書において世界史の始原としてアダムとエバそしてイスラエルの歴史を選択したようにである。今日アメリカをして予言者的な役割を担当するようにしているかもしれないと考えるとすれば、それは思い過ごしであると非難されるであろうか。(2013年6月9日)
かつては苦難を耐え抜かねばならない民族に人類の意味ある人生が示されたが、今日においては豊かな人々の歴史のこれからのありようを提示させているのだ。こう解釈すれば、あまりにも飛躍した歴史解釈であるといわれるかもしれない。トインビーは適当な富で満足して生きていく人生を現代における知恵ある生き方であるといった。そしてアメリカの革命が地球を何回も廻りながら革命を鼓吹しているともいった。このように考えるのが現代における宗教的姿勢でもあるとすれば、それはあまりにも飛躍した見方であると非難されるのだろうか。この問題は現代のキリスト教が考えなければならない重要な課題であろうと私は考える。トインビーは今日の豊かな国々こそ人類が初めて到達した飢えのない社会であると言ったのであるが、このような祝福された人生の中における宗教的な生き方というものを考えなければならないのではなかろうか。これが世界平和のためのわれわれの思索の出発点とならねばならないであろう。(cf. Arnold Toynbee, America and the World Revolution, 1962)
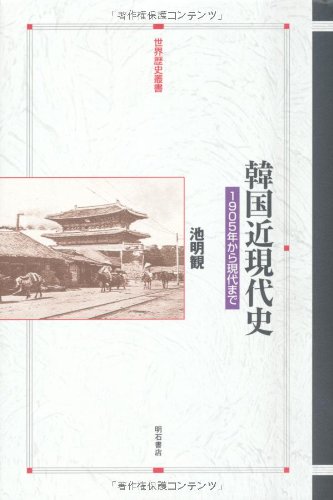
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
今日の世界史におけるアメリカの先駆的役割を認めながらも、それに至るまでの道がいかに峻しい歩みであったかを考えねばなるまい。海外に派遣されたアメリカ軍人のアジア人との国際結婚を認めその配偶者のアメリカへの入国の自由を認めたのが、第2次世界大戦後、朝鮮戦争の頃からではなかったか。アメリカの黒人たちがテレビにおいてニュース・キャスターとして活躍し、あのようにドラマで黒人白人が自由に混ざって出演するようになったのは2000年代に入ってからではないかと思われる。そのような風土であるからオバマ大統領まで登場するようになったのであろう。
『アブサロム、アブサロム!』を読みながら、開拓期のアメリカは旧約聖書の時代を思わせるものであると考えた。広い国土、人のまばらな地域で繰り広げられる開拓の歴史は残忍なものであり、人種差別は激しいものであった。そこにはすでにキリスト教会があったにもかかわらず、性の問題も結婚のこともそれこそ乱れに乱れていた。そこで、旧約時代におけると同じように宗教が何よりも政治と歩みをともにしながら、人間関係に影響を与え、秩序を打ち立てていったのではなかろうか。このような意味でアメリカ史は人類史が短縮されて反復されたものであるといえるかもしれない。旧約は人類史のモデルであり、それがフォークナーの描いたアメリカ史の中で反復されたのだ。
今日われわれが旧約聖書の創世記において人類史の始まりをみるように、フォークナーの作品においてアメリカ史の始まりを眺めることができるといえるのではなかろうか。『アブサロム、アブサロム!』の第5部を特にそのような目で読んでいる。そこに出てくるトマス・サトペンの狂気を創世記34章においてヤコブがヒビ人ハモルを没落に追いやる狂気と比べながらである。割礼を受けて「一つの民となりましょう」(16節)といってヒビ族に割礼を受けさせるのだが、「3日目になった痛みを覚えているとき」(25節)、ヤコブの子どもたちが彼らを襲って滅ぼした。このような人類史がアメリカ史において繰り返された。それが原罪といえるものではなかろうか。しかしそのような原罪からのみアメリカを眺めるのではなく、そこから出てきて発展してきた過程を認めなければならないであろう。それが人類史全体に対する見方であると言わねばなるまい。
人類史における歴史の方向とはどのようなものであろうか。敗北した側にも勝利した側にも個人的には善があり悪がある。歴史の方向を担った側にも、この罪多き世の中では悪が満ちていたであろう。私は朝鮮戦争の時にみた韓国軍側がなした悪を忘れることができない。それで歴史は個々人の善と悪を超えてそれ自体の方向を志向しているものではなかろうかと思ってきた。歴史とは個人の善悪を超えたそれこそ恐ろしい流れではなかろうか。目に見えざる手がそのすべてを利用していくのであり、それにかかわった個人に対する倫理的判決、または、評価は個人が参加した陣営がどちらであるのかに関係なくおろされるものではなかろうかと思うのである。
『アブサロム、アブサロム!』は現代における聖書の話である。人の稀少な南部の地で近親相姦など人類の悲劇が醸し出される。これは旧約聖書の話ではないが、フォークナーは現代における旧約聖書の話をアメリカ南部を舞台に再現してみせてくれた。実際は現代という「文明」の中でおおい隠されているが、まさにそれが人間の本源的な姿ではないかと問うたのだ。アメリカ史の始まりを創世記に比して第二の創世記として提起したといえるであろう。アメリカの創世記的性格とは、それはほんとうに驚くべき想像ではないか。そこに第二の人類史の始まりという暗示が込められている。『アブサロム、アブサロム!』において、われわれはそれをほのかに感じるようになるといえるではなかろうか。
わが国の文学はまだこのような深さからはほど遠いものであるといわねばなるまい。善悪の問題がそれほど単純なことであろうか。目に見える善悪を超えて、その底に流れる葛藤をそのように引き出しながら問いつめていくことが文学ではなかろうかと思われる。これに比べると哲学は単純な一元的思考ともいうべきかもしれない。文学は混沌をそのまま描いて暴露するものであるとすれば、哲学は早まって引き出した解釈と解決を提示しようとあせってきたものではあるまいか。文学における十字架は断然それとは異なるもであるといえよう。文学における十字架というイメージは解決とか救いとかあり得ない矛盾そのものであり、限りなき陣痛というべきもではなかろうかと考える。救いなき文学といわねばなるまい。とりわけフォークナーの文学はまさにそのようなものであるというべきではなかろうか。
大胆な解釈を許してもらえるならば、フォークナーにおけるアメリカの南部とは創世記まがいのアメリカではなかろうか。その混沌をあわわにするためのフォークナーの文学であったであろう。その混沌を示すための彼の文章であったというべきではなかろうか。コンマもピリオドもなく意味のあまりはっきりしない長い文章などでそこにはモラルの区別もなく、黒白の問題が秩序以前の世界におけるかのように入り混んでいる。例をあげれば特にチャールズ・ボンの息子と黒人女性の間では影のような関係ともいうべき意味のない日々が展開される。フォークナーの小説自体がそんなものではないか。トマス・サトペンをはじめ多くの人物が登場してくる。人間社会の意味を求め秩序を求めるということは、実際は仮のものをたずねることであり、人間の本来的な生というものは原始社会がみせてくれるように意味なき葛藤の流れではないかと語っているようであった。フォークナーはそのような問いと答えをアメリカという歴史の舞台の中で見せてくれたのではなかろうか。形式的な秩序を混沌という真実の世界に還元するといおうか。そのような意味で彼はアメリカ史の創世記、ある意味では第二の創造をたずねて現代史に挑戦したのではなかろうかと思われる。
現実または原始社会にはほんとうは意味を明らかにする句読点などあるはずがない。19世紀後半になってようやくここミネソタ州のような所にも東からの人が入ってきたというではないか。アメリカと第二の創造という世界史の課題は、謎のように現代のわれわれに残されていると私は考える。(2013年6月13日)
『アブサロム、アブサロム!』の終わりに「僕の考えているのはね、やがては、ジム・ボンドのような者たちが西半球を征服するだろうってことさ」ということばが出てくる。混血児の世界がくるというのだ。黒人を奴隷にし、性的対象にした貪欲的な占有、そのような自分達の制服と勝利の結果として白人の血が濁ってきてついには白人たちは失敗してしまうというのだ。制服とはもともとそのような敗北への道であるので、結局は「黒人サトペン」が独り残るようになるというのである。これを惜しむという発想は貪欲が生み出すものであろう。フォークナーは彼の伝統的なアメリカ南部という発想から嘆息し警告するのであろう。彼は創造の歴史とはそのように予定されているものなのかと問うているのであろう。そのように色あせていくものかと問うているように思える。そこに彼の終末的な発想が染み込んでいるような気がしてならない。それは勝利への道であるよりは果てしなき敗北と退歩への道であるとみる色濃いペシミズムがそこには染み込んでいると私は考える。
惨めな姿であるが、独り残ったローザ・コールドフィールは悲劇のフィナーレのように凄惨あるが、美しいものの痕跡として残れされた姿であったといえよう。それは今日もアメリカ南部に残っている恨(ハン)であり、白人の世界全体に残っている恨といえるのではなかろうか。歴史の中で失われていき、忘れられざるをえない彼ら白人の運命に対するであろう幻想からくるものであろう。フォークナーの作品は白人の意識の底にいまも残っているエレジーをその難解な文章構成にたたえているのであろう。それにもかかわらずそれが普遍的な共感を誘い出すことができるは、われわれ皆が歴史の進行の中で何かそういったものをそのように失いつつあることに対するエレジーの心を胸に抱いているからではなかろうか。進歩とは何か? それは何かを得ることであると思われ、同時に何かを失っていくことではないか。そのために進歩していく歴史に付き添ってくる哀歌は避けられないのだ。われわれは哀歌を口ずさみながら、前進せざるをえないといおうか。そうだ、歴史の前進または進歩には哀歌または終末論はつきものだといえよう。そのために老人意識とでもいおうか、老化した文化は過ぎ去った日々に対するエレジーを一人で静かに口ずさまざるをえない。黒白の差別と区別がなくなるとはという嘆息混じりのつぶやきが聞こえてくるかもしれない。フォークナーの文学からはどうしてかこのような嘆きが聞こえてくるような気がしてならない。(2013年6月19日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
