連載●池明観日記─第23回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫アメリカの黒人を見ながら≪
『三国遣事』(13世紀に一然禅師によって編纂された史書・民間説話などを多数含む)の紀違篇の中で新羅28代真徳王条を読みながら考えた。「太平歌」を作って唐に送った話しである。仁は天道といって唐の文治を称賛する。新羅でも唐でも堯舜の時代によって象徴される文治を崇めた。武とは非正常な状況において現れるものであると考えた。北東アジアでは文の社会とは理想的な社会を意味したのに、日本においては武の社会を正常の社会としたといわねばなるまい。そのために日本では戦場における悲惨な死を美化しようと努めた。日本は非アジア的エートスを伝えてきたといわねばなるまい。日本は仁を価値であるとするよりは美を価値としたと言えるかもしれない。このような点を西欧社会に比較して見れば、どうであろうか。『平家物語』に感動する日本の思想史をもう一度考えてみたい。『源氏物語』からしてすでに美はあっても善はなかったような気がしてならない。このような日本的発想の根源について思想史的にたどって見たいものである。(2013年3月27日)

フォークナーはアメリカの南部に対する彼の愛を自伝的エッセイ『ミシシッピ』においてつぎのように語ったと『アブサロム,アブサロム』の訳者藤平智子は伝えている。
「そのいくらかは憎んでいるものの、そのすべてを愛している。というのは、人は、<だから>というより、<にもかかわらず>愛するものであり、その美点のためにではなく、欠点にもかかわらず愛するのだ、ということを作家は知っているからである」(岩波文庫『アブサロム,アブサロム』上)
訳者は続ける。「これは、フォークナーが作家として、南部の歴史をすでに引き受けている喜びにも満ちた言葉に聞える」といった。これはそのまま韓国の場合にも適用されうることばではなかろうか。朴景利(パク・キョンリ)の『土地』を私はそのような心情で読み続けている。彼女の憎悪に近い韓国と韓国人に対する描写。彼女が「朝鮮の奴」という時には彼女の彼女自身に対する怒りの声があるというべきではなかろうかと思うのである。
藤平によればアメリカの小説家トニ・モリスンは、1985年の夏「ミシシッピのフォークナー会議」に招かれて、フォークナーが「歴史に記録されなかったアメリカの過去を、芸術として的確に表現している」といいながら「時に歴史が拒否するようなことを、芸術と小説はやってのけることができるのです」と語ったという。歴史、それはややもすると単なる政治史に過ぎないようになるものだが、実際は人間の呼吸を伝えるといおうか、そういうことは小説がすることではなかろうか。李光洙(イ・グァンス)の『土』も朴景利の『土地』もそのようなことを成し遂げようとしたのではなかろうか。私も特に終戦以後今日までの我が国の歴史においてそのような民衆の呼吸を伝えたかった。新聞記事とか小説などと私の経験したことを混ぜながら現代史を、普通の歴史では漏れていることがらといおうか、私が経験した現代民衆史とでもいおうか、そういったものを書きたかったのであるが、それは一つの夢で終わるのであろう。(2013年3月29日)
アメリカをどのように見るべきであるのか? アメリカに対する私の考えはいかに多くの変化をこうむってきたのであろうか。アメリカに憧れた時代、アメリカを特に6・25の戦争を通して美化しそれに感謝した時代。それから 1967年初めてアメリカに来ては韓米関係は何ら特別なものではない世界の100を超える多くの国々とアメリカという関係の一つだと考えようとした。アメリカの反ベトナム問題や黒白の問題や同性愛などを見ながらアメリカ文明もかつて世界のすべての大国がそうであったように今や没落期に入ったのだと考えようとした。
今日アメリカに来て生活しながら、米国史にかんする BBC のプログラムを見たり、昨日は在米韓国人教会の人びとの夕べの集まりに参加したりしながら、特にゲイの結婚式を教会で行うべきかなどの討議をテレビで見たりしながら、私はどう考えるべきかと改めてアメリカを見つめ直そうとしてきた。そしてアメリカは今日の世界史において先駆的な経験をしてきたのではないかと思うようになってきたようである。特に世界史の将来において肯定的な役割をなしうる国はアメリカ以外にはないのではなかろうかと思うようになってきたといおうか。
欧米の白人優越主義は崩壊一路の道をたどってきた。その歴史は黒人はもちろんのこと東洋人をも恐ろしく排斥してきた歴史であった。しかし今はほんとうにアメリカは人権においても「文化においても」まさにメルティング・ポットではないか。これは世界史が経験する歴史の流れ先立って体験することではなかろうか。アメリカは聖書的価値を主張しながらも現実においてはもっと通俗的な種族主義の道を歩んできた。
しかしそれは歴史とともに崩れてくる。聖書的理想主義と現実は葛藤していたが、世界史の前で例えば人種主義はアメリカから、崩れてくる。それがこれからの世界史の方向だといわざるをえない。アメリカにおける葛藤は世界どこにおいても起るべきことであった。それは世界どこでもみなが担ぎうべき人類史の方向ではないか。みながアメリカの現実において世界史の方向を見定めて明日を準備しなければなるまい。神の歴史はその徴候をもってわれわれに明日のことを示してきた。それは時には予言者を立てて予告し警告を発しながら展開されてきたものではないか。
われわれはそれに対してどのように対応しなければならないのか。ひどい反発を感じる時もあろうが、目ざめた信仰の目をもって生きて行くということは、周囲にある反発しがちな人びとをながめながらその中で賢明な役割を果たすということであろう。アメリカの社会では特に同性結婚の問題などをそのように受け入れようとしているのではなかろうか。それは明日におけるわれわれの問題でもあるであろう。キリスト教国ではないといってそれを教会外の問題として放置しておいていいのであろうか。私には何よりもそれは宣教の問題として提起されなければならないことであるように思える。(2013年4月8日)
アメリカのテレビにおける黒人の活躍を目にしながら色々な問題を考えるようになる。こうなったのは何年ほど前からであろうか。フォークナーの作品に出てくる息苦しくなるような白人のみのアメリカ。しかしそれもすでにヨーロッパ各地からやってきたいろいろな民族の融合を前提としているものであった。そこから黒人との融合そしてアジア人との融合の方へと進んで行く。今日のアメリカにおいてこのように民族を超えて世界へと実験が拡大して行くのではなかろうかと思われる。職業選択においてはこのような解放がヨーロッパや日本など多くの国に先立って行われてきた。
韓国においてはそのような解放はもちろんまだ遠い先の課題であるかのように見える。アメリカは人種の面からしても世界の縮図といわねばならない。だからその面でも世界に先立って実験をして行かねばならない。それは世界史に対する予告であると思えるのでいっそう注目せざるをえない。新しくやって来た移民たちのアメリカ社会への適応のための苦難と悲劇も続くであろうが、彼らのアメリカ社会への統合とステイタス向上のための血のにじむような努力が続けられる。これは人類史的な実験といわざるをえないのではないか。
17世紀前半に始まったヨーロッパの白人の移民、そして19世紀後半の黒人奴隷の解放、それから20世紀に入ってはアジア系移民などとアメリカの移民史は続いた。そして21世紀には黒人大統領の出現である。とても遅々とした発展だといえるかもしれないが、この道は人間解放に要した長い道のりであった。アメリカにおいてこの道はのろのろとした道であったといえるかもしれないが、後退することなく続いた。そして世界のすべての国はゆっくりと嫌な顔をしながらもこの道を続けざるをえないといえよう。アメリカのみが例外的にメルティング・ポットと言われるようであったが、これは間違いなく世界史の流れであるといえよう。この流れにおいてアメリカは先進的であり、世界に先立って人類の統合を宣言し、その道を学んできたといわねばならない。この点でもアメリカは現代史の先達であるといわざるをえないであろう。
革命的であると自称していた共産主義社会がそれとは異なった道を歩きながらそれをかたくなに守ろうとしたとはなんという自己矛盾であったことか。それは革命を掲げながらも古い価値とそれによる利益を独占しようとしたことに過ぎなかったのであろう。そのような姿を如実に示してくれる、もっとも堕落した形態が今日われわれが目にしているこの国の北の地ではなかろうか。実際彼らは今日においても単一民族云々の幻想を抱いて喘いでいる。縮小された今日の世界においてアメリカが見せてくれる先進性を問題にし、この歴史に対する理解を深めなければなるまい。世界史の未来とアメリカの歴史を考えるならひたすら民族に固執することがいかに滑稽なことであるかを知るべきではなかろうか。世界史は時にはこのように堪え難い犠牲を求めながら進行するものであるといわねばなるまい。(2013年4月12日)
≫『土地』から『太白山脈』へ≪
私は朴槿恵(パク・クネ)の浅薄さとでもいおうか、そして彼女の父親の発想の狭さと残忍性を思い続けた。いずれにせよ新しい権力によってこの国民が皆歓喜することのできる合意の時代、国民の時代は少なくとも5年後まで後退したことになるといえるのではなかろうか。彼女がもしも私は父親が歩んだ道は踏まない、父の時代に対してあのような悲しみをかみしめている人びとがいるではないか。私は父の避けられなかった点を、そして彼が労心焦思したことをよく知っている。しかし彼の専制政治で苦しんだ多くの国民のことを思わざるをえない。それで私は国民の一方だけの支持しかえられない権力の座は求めたくない。私は国民統合の新しい時代を導く人物を選択し支持すると言うことはできなかったであろうか。彼女がそのような人物となりえない韓国史の不幸といおうか。そういうことは政治家には求められない。愛国志士にだけ求められるものであろう。いずれにせよ、大統領が国民的権威を象徴した時代は、このようにして完全に過ぎ去ってしまった。
野党の候補文在寅(ムン・ジェイン)もそのような人物でないことは同じであった。北に対してより寛大でなければならないという人が彼を支持することは決まっていたにもかかわらず、なぜ彼は遊説中彼らに対する発言のみを繰り返したのであろうか。それではそれに対して懐疑的であった人びとは彼から離れて行くのではないか。北に対して寛大である勢力はすでに彼の影響下にあったのではないか。そうでない人々を引きつける努力をなすべきではなかったか。南北問題は重大な課題である。北はいま困難に直面している。北の権力は国民のための権力という姿勢を取らなければならない。われわれは北に対してどのように対応するべきか。そのためには国民全体とともにそれこそ開かれた場において苦しみを共にしながら道をさがし出さねばならないであろう。大統領になれば国民が圧倒的に支持することのない政策を私一人で独善的に選択することは絶対にあり得ないと。なぜこう国民に訴えることができなかったのであろう。北に対して懐疑的な国民が圧倒的に多いということは誰もが知っている現実ではないか。
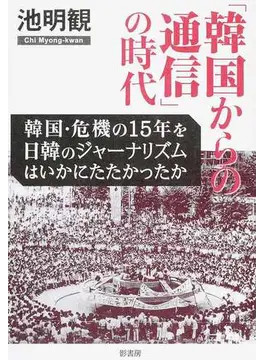
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
国民統合の歓喜の時代を求めようとするのではなく、ただ自己利益を目ざして走り廻る政治家を選出せざるをえないのが韓国の民主主義という政治制度であるといえようか。このような勢力の下でこれから迫ってくる危機をどのように乗り超えて行くことができるというのか。北に居るあの飢えに苦しむ国民を放置しておいたまま、その痛みを知ろうともしない政治という点では北も南も同じことではなかろうか。その痛みに共感できる政治力を生み出すことができなければ、この国の問題は出口をさがし出せないまま空転するのではなかろうか。いまのこの国の政治家というのは国民の痛みを知ろうとしない悪しき群像ではなかろうかという思いがしてならない。南北がともに同じような非人間的な状況の中にあるのではなかろうか。
私は続けて朴景利の『土地』を読んでいる。今読んでいるのは第 15巻である。かつて李光洙がその作品を『土』としたのだから、朴景利は『土地』といったのだろう。日本統治下または地上の間違った政治体制の下で苦しむ民族の不変の根源をたずねて土または土地としたに違いあるまい。『土』は日本の支配下で「自粛」しながら書かねばならなかったとすれば、『土地』は自由にすべてを描くことができたかもしれない。この作品では民族的合意を求めることが難しいあの歴史の中で何人かの女人像が美しく描き上げられている。朴景利はそのような女人像を彼女の希望の対象、または彼女自身の分身として第15巻の人物に投影したのではなかろうかと思われる。
「泣く代りに笑っているのかもしれない」
「まゆみにも虫がつくと言ったじゃない。老いて行くのを誰が遮ぎる」
「弓矢の如き歳月と千秋の如き一刻。この両側にまたがる谷。生と死の谷を超えて行く億兆の蒼生。荘厳たる悲劇だ」
「死ねば終りじゃ。寒さも暖かさも知らないから心配などいらない。腹いっぱいだ、おなかがすいたも知らないから大丈夫じゃ」
『土地』には仏教の無常感が底深く流れている。それで作者自身は独り身になった人生を耐え抜いたといえるのではなかろうか。『土地』は作者自身の恨の所産であるといわねばなるまい。それが民族の恨と一つになったともいえよう。(2013年4月13日)
昨日の日曜日、大学時代に対北運動に参加し、今はアメリカに来て学位コースに在籍している夫を支えている若い婦人にあった。韓国の今日の反動的な政治状況に触れながら涙ぐむのであった。彼女は韓国教会がどうしてあのようにこの世のことについてうとい状態に収まっていていいのでしょうかというのであった。私はふとアメリカにある韓国人教会が本国の教会の宣教に頼るのではなく、逆に影響を与えることのできる教会であるべき時点にきているのではなかろうかといった。このことは私が期せずして口にしたことばであった。実際そうではなかろうか。270万という在米韓国人であり、これからは彼らが信仰的立場にはっきり立って国内の教会にもの言うのでなければなるまい。
かつてアメリカの教会がヨーロッパからの移民による教会として成長し、だんだんと独自の教会をなしてヨーロッパに影響を与えるようになってきたようにである。アメリカにある韓国人教会がこのような宣教的姿勢が持てるように成長しつつあるといえるだろうか。宣教神学が求められるといえよう。このようなことのために私もこの人生の最後において何かを求められているように思うのは傲慢な姿勢であろうか。教会も民族も個人も誰かが私に対して何かしてくれることを期待するという姿勢ではなく、私が何かをしてあげるべきだと考えようとする時に大きく成長するのではなかろうか。(2013年4月15日)
朴景利の『土地』21 巻までを読み終えてから趙延来(チョ・ジョンネ)の『太白山脈』を読み始めた。『太白山脈』はいまのところやっと2、3 頁読んだだけである。『土地』に比べて『太白山脈』は文章から違うような気がする。李光洙の『土』が北を背景にしたものであるとすれば、『土地』は南を背景にしたものである。『土地』に満ちている南の文章といおうか南の地方語ゆたかな対話そして修飾語。北出身の李光洙を越えようとしたであろう。『土地』にしみこんだ土俗語、その文章は躍動するような立体性、力動性を備えている。それに比べると『太白山脈』は女学校の生活を描写しているところに現れているように力動性に欠けているようである。まだ2、3頁ほどしか読んでいないにもかかわらず、どうしてか平面的描写だという気がしてならない。『土地』は叙情的な文章であり、『太白山脈』は叙事的な文章であるといえようか。『土地』が女性作家の作品でありながらそこには彼女の個人的な人生体験が消えることのない恨として底に流れているせいであろうか。
『夜明け前』なども考えながら、アジアの近代化における土地を中心とした哀歓とでもいおうか、それら近代前夜の作品を中国の作者も含め一度比較してみたいが、もちろんそれは不可能な夢といわざるをえないのではないか。この齢でこのアメリカではそれはとうていかなわぬ夢であろう。『土地』を読み終えてはいやすことのできない憂愁のみが残ったといえよう。『太白山脈』は終戦後の南北分断の時代を取り上げたものである。『土地』には南西部の『智異山』があったのだから今度は『太白山脈』といったのであろう。このように、そこには表にされていない相互連関があるといえるのではなかろうか。
韓国の場合は解放後南北における抵抗勢力がそれぞれ性格を異にしていた。北では共産勢力の支配下であったために、それに対する抵抗勢力は市民階級であったといおうか。南においての抵抗は社会主義的であった。それで南北では反外勢的で民族的で反権力的抵抗が続いたといえるが、おたがい親共と反共の対決を生み出した。南ではそのはざまでかつて親日派であった勢力が生き残ることができた。日本統治下では反日的であり民族的であるといわれたキリスト教勢力は奇妙な位置に立たされた。その勢力は北では完全に撲滅され追放され、南下したのであるが、南では米軍政と李承晩政権の方に傾斜して行った。そして1960年4 ・ 19革命が起こると大きな衝撃に出くわさねばならなかった。南下した反共勢力は南でほとんど流浪の状態に落ち入ったのであるが、西北青年会などに見られるようにしばしば反共テロ集団と化した。
私は南の土着勢力がほとんど全面的に南の政治権力と結びつくようになるのは 6・25の朝鮮戦争後であると解釈している。南では6・25の前後に静かな転向が起こったのであり、今日でもそのような時代の余韻がだいぶ浅く残っていると思う。南の勢力の登場によって北から南下した人はほとんど政治から離れて行かざるをえなかった。そのためにその一部は政治に対する批判的な立場に立つようにもなったといえよう。いずれにせよ終戦直後南北の政治の場に現れたこのような渦巻は先にもふれたが、もう少し深く掘り下げてみる必要があるであろう。(2013年5月10日)
私は物書きになるとすれば一度はこのような文章を書かねばならないと思ってきたことを忘れることが出来ない。われわれはほんとうにわれわれの民族を愛しているのかという文章のことである。これは人間が人間を愛しているのであろうかという問いと結びつくものであろう。イエスがそれほど愛を強調しているのは、人間が人間を愛しうる存在であるにもかかわらず、実際においてはお互いに愛していないからではなかったか。極端の場合はカンボジアのポルポトのような残忍な行為さえあるからではなかろうか。
6・25のことを考え、韓国の民主主義のことを考えるときにはこのような問いをくり返さざるをえない。今は戦争なき時代であることを考えながら、人間は人間を愛しうる存在なのかと再び問わねばならないような気がする。民主主義はお互いに愛しえない人間どもが仕方なく提案する妥協事項ではなかろうかという思いもある。特に近代のあの恐るべき対立と争闘を思いだして見ると、民主主義とは対立しあう現実に向かって暫定的な妥協をさがし出そうとしたことではないか。それはそのような人類のためにようやくたどりついた帰着点であり、それ以上のものではありえないのではなかろうか。宗教はそれを超克しようとしたのであるが、あの原罪ということばで問題を回避したのに過ぎなかったのではないかと思われてならない。
にもかかわらず今や人類は政治においても闘争ではなく与野党の協力をさがし出さねばならず、ほんとうに人間の善意を求めるようになってきたのではないかと思う。与野党の争闘ではなく与野の祝祭を期待する。それのみが人間の救援であると考える。われわれ韓国人も民主主義を回復したと言いながらも、与野党の対立と争闘に今は耐えられなくなってきているように思える。そのような政治に対する嫌悪が拡大して行くのではなかろうか。新しい民主主義でなければ、民主政治をも放棄したいと思うようになるかもしれない。
このような変化と発展においてまさにわれわれは人類史の進歩を見てもいいのではなかろうか。歴史的に何かを放棄しなければならないとすれば、政治制度の場合もまずそれに対する感性的な嫌悪感が芽生えてくるのではないかと思われる。今の民主政治と言われるものに対するわれわれの嫌悪感といえると思うのだが、このことを深く検討する必要があるのではなかろうか。かつては、言うまでもなく未熟な民主主義であったというであろうが、それに対する不満から共産主義はもちろん、ファシズムという全体主義まで試みようとしたではないか。韓国ではいま国民が与党も野党も嫌いだといっている。(2013年5月21日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
