連載●池明観日記─第21回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫2013年―再び歴史とは何かと考えながら≪
ウィリヤム・フォークナーの短編集『熊』を読んでいる。「熊」「昔の人びと」「熊狩り」「朝の追跡」などの短編が入っている。アメリカの南部ミシシッピの森を背景にして白人、黒人、インディアンの平和的な共存ということを念じながら展開された物語である。もちろんそこに差別と虐待の歴史もあったであろうが、そのような差別を感じさせない自然的な生きざまもあったに違いない。差別で始まった暮らしであっても長いこと生きて行けば、断つことのできない絆が育ってくる。わが国の両班社会(注:両班とは文武両班の支配階層を意味したが、漸次文官系上層階級のみを意味した)でもそのようになったであろう。身分制度のなかでも芽生えた、制度にしばられない暖かい人間関係といおうか。

このような伝統の中でアメリカの南部ではいまだに黒白というのは何か自然的なもので人間の左右しえないもののように感じているというとの印象を受ける。南部を旅行していてそのような空気を感じた。南部には少しのろいといえそうだが、沈んでいるようなしかし安定的な印象を与えるものがあった。この頃黒人たちの登場を見ながらアメリカ人たちは白人の場合、黒人に対してわれわれよりずっと自然的な感じでつきあっているのではなかろうかと思われる。黒人の子を養子縁組した白人の姿をあちらこちらで見ながらいろいろと考えるようになる。われわれの目には多少異常なもののように映る。東アジアに来ている宣教師の間でも黒人を発見することなどほんとうに珍しいのではなかろうか。確かにわれわれ東洋人たちがずっと人種差別的だといえるのかもしれない。フォークナーの作品の中では慣習による自然的な黒白合流のようなものを感じる。
このような現象は黒人差別に反対した北部にはかえって少なかったのではなかろうか。黒人を奴隷とする制度に反対したということでは親黒人的であるといえるかもしれないが、実際には南部よりも黒人を嫌悪したに違いない北部ではないか。今はそれから150年も過ぎて北部の白人もだいぶ変わってきて黒人大統領まで選ぶようになってきた。奴隷制度に反対したヨーロッパがかえって黒人嫌悪から抜けきっていなく、われわれもヨーロッパ人と同じような黒人観を持っているのではなかろうかと思われる。
私自身も観念と現実との隔差といおうか、恥ずかしいことだが、そのような意識が堆積しているところから抜け切っていないと思う。実際わが民族の歴史には長い間、他民族体験というものが欠けていたではないか。フォークナーの作品世界はそのようなアメリカ南部の風景を前提としてこそ理解できるのであろう。それは古い制度を擁護することではなく、そのような人間の習性を指摘しながら、北米における観念的な黒人観にいどんだのではなかろうかと思われる。このような人種問題においてもアメリカ史は人類の歴史における先進性を担っているといえよう。
こう考えるならば古い観念が打ち砕かれる経験をしていないということはいかに悲しいことであろうか。もちろんそのような激動を経験することは実に痛みの多いことであるのだが。われわれが今経験している南北分断という歴史もこのような新しい歴史に連なる日が来るであろうか。南側だけでも、今度の選挙においてもう一度見てきたように、地域対立がつくる陣痛は、容易ではなく実に根深いものである。このような問題がいつになったら克服されるのであろうか。
(2013年1月3日)
『源氏物語』を読んでいる。11世紀初めの作品であるという。現代語に訳された第2巻目を読んでいる程度であるが、反復される宮廷人の放蕩生活に興味を失い読み続けることが難しい。女遊びの放埒な生活と言わざるをえない。しかし読み続けれていれば興味を引く箇所に出くわすのかもしれない。
その一方で朴景利の『土地』第4巻を読み続けている。川辺の風景のような話といおうか。これから何かはっとするような話が現れてくるのであろうか。私としては理解しがたい南部の言葉が収録されている。その対話録がこの作品の残してくれた貴重な資産であると言えるかもしれない。風俗画のようなものがこの作品が見せてくれた功績ではなかろうかと考えている。ちりぢりに裂けている社会であり家族関係である。これからその中でも主人公の劇的な話といおうが、英雄的物語といおうが、そのような展開を見せてくれるのかと期待している。
『源氏物語』を日本のすばらしい文化遺産といっているが、私はやはりアウグスティヌスの『神国論』、もっと遡ればギリシャ時代の戯曲のような作品にひかれる。やはり西欧文明の先進性を認めざるをえないのではなかろうかと思う。そしてキリスト教の聖書文明といおうか、我田引水のようで論じ難いのであるが、その文明の先進性を受け入れざるをえないのではなかろうか。そのような東西文明の差異が近世ではもちろん今日においても続いているようで、歴史の不可測性を感じながら歴史とは何かを改めて問いたくなる。東西比較文化史とでもいおうか、またはこれから展開される世界史とでもいおうか、そういったものについて問いたくなる。
(2013年1月5日)
アニミズムとか多神論にとどまっている限り、世界を統一的に考えて解釈することなどできなかったのではなかろうか。一神論において、一つの原理をもって世界を解釈しようとする姿勢において、科学は発展しえたのではないだろうか。このように西欧の世界観を解釈しながら、東洋の場合と比較する思想史が可能ではなかろうか。統一的な科学が西欧では可能であったが、われわれはそれにおいて遅れを取ったのではないかと思われる。それでは東洋というものが成し遂げた人類史的な貢献とはどのようなものと考えるべきであるかとわれわれは問うてみなければなるまい。(2013年1月6日)
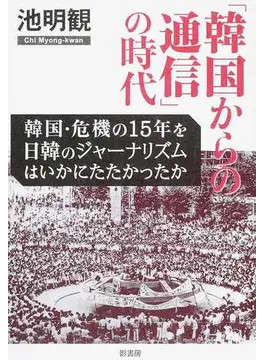
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
日本の『源氏物語』を読んでいるのだが、一夫一婦制が日本においてもだいぶ遅れているということを考えざるをえなかった。10世紀初めにも一夫多妻制に対する批判などはありえなかった。中国も日本も朝鮮も一夫一婦制というのは近代以降ではなかったか。儒教以後であるならば、男尊女卑、一夫多妻制の下で夫につかえることが強要されたのではないか。日本の場合は一夫従事の倫理もそれほど強くはなかったようである。ヨーロッパにおいてはキリスト教の導入に従って一夫一婦制の倫理が強いられたのではないか。
そうであるとすれば一夫一婦の倫理が家族倫理として採択されたのは東洋においてはヨーロッパに比べて2000年近く遅れたことになるではないか。そしてアウグスティヌスの『神国論』に現れたような進歩史観もそれだけ遅れたことになり、終末論などは見られないといわねばなるまい。それに東洋は多神論的な世界観であった。多神論的な世界観では進歩史観と終末論は成立しえなかったのではなかろうかと思われる。このような意味において東西の思想史的比較を率直に展開してみる必要があるであろう。そこで近世以後の東西の出会いを人類史的に位置づけることができるだろうと思われる。
ここに救済史的キリスト教史が世界史的に成立しなければならない理由があるといえるではなかろうか。そこでキリスト教が示している歴史の発展史的展開が重要になる。たとえ聖書が歴史を短縮した形で提示したとしても、それは無限ともいうべき歴史を人間が考えることができる象徴で表象したものであるといえる。一目瞭然とした形で提示した宇宙の創造史とか人間の歴史の始まりとか、バベルの塔の説話に現れた人間の言語の分裂とかのようにである。そのすべては世界の始まりに対してわれわれが考えうるもっとも適切な言語表現であったと言えよう。これ以上に表現できる手段がどこにありえたのであろうか。
言語とは何か巨大なものを象徴しうるほとんど唯一の手段であったといえるのではなかろうか。それでそれらの表象は人間が理性で思考した結果ではなく啓示されたものであるとした。神の御言葉によってであると言えた。そのように超越界から歴史の中に入ってきたとした。そしてそのように信じるイスラエルからヨーロッパへと、そしてアメリカに、そこからアジアに流れてきたというのである。その宗教をここまで運んできた手段というのが時にはあまりに人間的な、嫌悪すべき人間の罪悪に染まったものであった。歴史における真理は人間のこのような血に染まった手によって生かされてきた。凄惨なる植民地化という歴史なくして文化伝播がありえなかったという思いがしてならない。
多くの人々の非難を受けざるをえないと思うのだが、歴史とはそのような過酷な道を歩まざるをえなかった。人間の罪と死、その貪欲によって伝えられてきた文化。6・25以後の厳しい歴史の中でわれわれは古い反動的な歴史、身分社会的なことも閉鎖的思考も克服してきたではないか。迫害を避けて清教徒たちを初めとしたヨーロッパ移民たちがアメリカ大陸に来ていなければ、アメリカの階級のない民主主義社会がそのように重い悪しき遺産の圧力なしに打ち建てられることができたであろうか。ヨーロッパに比べてアメリカが先に民主主義の道を歩むようになった。それで今はヨーロッパでは考えられないような黒人の地位が可能になった。韓国が封建社会の抑圧なしに民主主義の歴史の道を歩むことができたのは、6・25の悲劇とその破壊を経験したからだという逆説が可能であるといえるかもしれない。日本の植民地支配という悲しい歴史もそのような歴史意識から振り返って見ることもできるといえるのではなかろうか。
これは何という歴史のアイロニー、なんと冷酷な歴史といおうか。この歴史に対して悪しき者と善なる者、殺人者とその犠牲者という道徳的判断は避けられないものであるが、その線を越えて歴史は進行するものであろう。特に賢明な民族である場合は行為に対する善悪の判断はそのままにしておきながらも、歴史は悪しきことも、否定的なことも、善用しながら前進するものだというべきなのかもしれない。このような歴史に対しては感謝することなどなしにただ諦念の目で眺めるべきだといえよう。それでイエスも十字架上の死を前にして「わたしの思いのままにではなく、みこころのままになさって下さい」と祈らざるをえなかったのであろうか。歴史は善悪をはっきりとふるい分けながらも、それを超えて進行するものと思えてならない。(2013年1月9日)
岩波書店が2012年2月に出した『「思想」の軌跡 1921-2011』という本を読んでいる。2007年8月に『思想』1000号を迎えたというので「思想の100年をたどる」という座談会を時代を区分して行い、その内容を収録したものである。日本の思想史をたどるような気がする。このような内容は日本における知識人の間における問題を示してくれるものであるが、その背後には実際の政治の動きがあるのだから決して現実とかけ離れたものではない。戦後の日本では米ソの対立という政治情勢を前にして日本はどのように対応しなければならないかと論じ合わねばならなかった。共産主義的体制が崩壊した今日から見れば、その当時の知識人はその時の現実にとらわれて歴史の流れを正しく見通したとはいえないかもしれない。

この意味で思想史は、知識人の政治的または歴史的判断を超えて現実の歴史はどのように流れ行ったかをたどらざるをえない。事実の歴史は我々の願望とか判断を超えて進んで行くものである。私はどうしても過ぎ去った日本の戦後史または思想史を日本とアジアとの関係という課題を前にして考えてみたくなる。ソ連の崩壊からも20年近くの歳月が流れたではないか。「戦後における東アジアと日本の関係に関する研究-『朝日新聞』と『世界』を中心にして」とでもいおうか。こんな題目でなぜソ連の世界支配の夢は破れて、アメリカの世界支配は実質的に目の前に迫ってくるようになったかとたどってみたいと思うのである。
世界支配においてソ連の場合は作為的でアメリカの場合は歴史的であったといおうか。日本は戦後において東アジアに対するかつてのような作為的な関与は、もちろん放棄しなければならなかったが、その一方で東アジアの苦悩も発展も無視してきたといえるのではなかろうか。実際、日本は戦争中のアジア観をそのまま続けてきたといえるかもしれない。そこで今日の日本がそのネメシスによって苦しまなければならなくなったといえよう。東アジアの国々は力をつけるまで先発国である日本から多くのことを学びながら沈黙してきたが、これからはそうはいかないように見える。このような東アジアの日本に対するネメシスの時代に日本はどのように対応しうるのであろうか。いまはややもすれば反動的で保守的な姿勢で対応しようとしているように見えるが。そして北東アジア三国には保守的で反動的な政権が現れているようであるが、いまは保守反動が対立しているこの地域であるというのであろうか。
岩波の本で見れば、日本において終戦前のあの困難な反動の時代に節を守って耐え抜いた人々が戦後になって決して「思想的優位」を占めることができなかったという。小林秀雄のような評論家は「僕は無智だから反省などしない。利巧な奴はたんと反省してみせるがいいぢやないか」と厚かましくも反動を正当化して人気を博したという。戦後にも「過去は美しい」と言いながら人気を勝ちえたとすれば、そのような反歴史的な思考が日本人の間では共感をえたということではないか。それは何よりも反理性的な反発であり、アジアとその和解を拒否する姿勢であった。彼らは集団的な思考の中に生きていて内面的な苦悩などはなかったというのであろうか。実際、彼らはそれまで自分個人の考えというよりは集団に頼って生きてきたとすれば、ここでも彼ら個人の姿勢ということよりも日本の武士社会という伝統の問題を韓国の儒家社会と比較してみる必要があるのではなかろうか。
この問題とは別に李光洙の転向に対して韓国人が非常に苛酷であったことにも多く理由があったというべきであろう。儒家社会における倫理的な生き方という問題もそこにあるであろうが、何よりもそれは代表的な文学者が異民族の支配に屈服したことに対する憤りであった。その後、特に軍事政権の国民に対する反逆には我々もだいぶあいまいな姿勢を取ってきたのではなかろうか。そのために朴槿恵の政治的帰還もありえたのではなかろうかと思われる。これからは彼女自身の政治が国民の審判を受けるようになるであろう。彼女の政治に対する判断である以上に、かつての軍事政権とそれに同調した勢力に対する審きでもあるであろう。
そのような意味においてこれから五年間は遅まきにやってきた彼らの統治に対する国民的審判であるという意味を帯びるのではなかろうかと私は考える。朴槿恵は朴正煕に対する真の審きを受けるために国民の前に立たされたというべきであろう。これまで民主化勢力もそのような歴史的審判を受けなければならなかったではないか。フランス革命後一世紀の間、革命と反革命が反復したようにである。アメリカの革命はそれとはだいぶ異なる道を歩んできて今日においては世界史のモデルともいうべき位置を占めているように見える。
日本の知識人たちが今まで歩んできた道を振り返って見て感じることはやはり歴史的判断における誤謬というものではなかろうかという思いがする。現代史における過ちといえば、われわれはソ連に対する過度な幻想的な期待と「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という日本に対する過度な期待も数えられるのではなかろうかという気がする。ソ連に対する判断-あれほど独裁の国であり、人民は圧政の塗炭に苦しんでいた、それこそ人工の歴史であるにもかかわらず、それを理想の国であるとまで宣伝するという恐ろしい過ちにわれわれは陥っていたのではないか。それは常に自分に与えられたものは見すぼらしいもので、ひとのものは大きくてすばらしいものと考える人間の習性からきたものであったといえるかもしれない。この朝鮮半島においても北からは南を、南からは北をそのように憧憬したのではないか。そうした知識人たちの没落は避けられないものであった。自縄自縛ともいえるかもしれない。
ほんとうに知識人の歴史的判断とはなんと愚かなものであっただろうかと時には思わざるをえない。このような人間の過誤を指摘する歴史を別にしたためなければならないのかもしれない。人間の予想と希望を裏切ってきた歴史を別に書き留めなければならないということであろうか。現代史におけるアメリカのことを考える時などいつも個人として私はそのような思いに駆られざるをえない。トクヴィルとかラスキのような人々がくり広げたアメリカに対する予見を見て多少はホッとするが、彼らは政治評論家ではなく真の歴史家であった。人々はこのように考えたが、実際に展開された歴史はこのようなものになったという歴史記述が必要だと思わざるをえない。
カール・ポパーは「グランドデザインとしての歴史を設計することは理性の傲慢だ」といった。(『「思想」の軌跡』)だから私は人間の歴史と神の歴史という二重の物差しが必要なのではなかろうかと思う。われわれは未来を予測しながら行動し、その結果によって反省を強いられる。これは歴史に対する懐疑論といえるかもしれない。少なくとも「過去は美しい」というような反動を直視しながら歴史をたどって行かねばなるまい。
日本ではこの頃そのような自国主義、そのような歴史的な思考が大きな危機に直面しているのではないか。このような時代に進歩でなければ保守、保守でなければ進歩というのではなく、このような危機こそ新しい機会であるという考えで静かに立ち止まって考えなければならないのではなかろうか。それで私はアメリカの世界における成功を考えながら日本も北東アジアと日本との関係を実証的に振り返って見るべきではないか。歴史が進んで行く方向を直視しながらと思うのである。それこそE.H.カーがいったように歴史を未来から解き明かそうとすることであろう。
日本はアジアの支配を夢見て失敗するとアジア忘却を当然のこととして経済的利益を欧米に求めた。その間にアジアは発展して日本と対決しようとするまでになった。日本は世界に対するアメリカの対応方式から学ばなければならないであろう。アメリカはゆっくりと歴史を見つめながら、相手の国家が自ら成長してアメリカを一層必要とする所まで成長するまで待っているといおうか。かつてのソ連は自分の陣営に統合してくることを強要し、自分の支配に服従することを強要した。アメリカは自由にしておいて、その国の内発の力を信じて待っている。歴史に対する楽観論がその背後にはあるといえるかもしれない。
丸山真男が考えた日本の古層回帰の心を思うべきなのかもしれない。うまく行かなければかつての古層に蟄居しようとするかもしれないが、それは非歴史的であり、反現実的である。回避の思想といおうか、かつて武士社会において力に余る相手また状況であればひとまず避けて時を待とうとした姿勢なのかもしれない。しかし「過去は美しい」といいながら歴史を引き止めることができるといえようか。そのような幻想的な歴史観から抜け出てこなければ、日本も北東アジアも不幸に落とし入れられるだけではないか。日本はかつて、日本はアジアに属しているだろうかなどと愚かな質問をしてきたことを私は何度も指摘した。それは地政学的にも、地政文化的にも、また現実的にもありえない問いではなかったか。戦後でさえアジア忘却に陥りがちであったことを日本は反省しなければなるまい。そして何よりも日本にとっても今の危機がやはり機会であると私は考える。(2013年1月25日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。池さん本当に長い間ご苦労様でした。もうゆっくりお休みください。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
連載
- 連載/池明観日記─第21回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート池 明観(チ・ミョンクヮン)
