連載●シリーズ「抗う人」⑭
言論弾圧に抗い、読者の知る権利に応える
沖縄の新聞記者~松元 剛
ジャーナリスト 西村 秀樹
沖縄県と日本政府が正面からぶつかる。辺野古へのアメリカ軍の新基地建設をめぐる闘いが先鋭化している。日増しにつよまる政権や右派からの沖縄の新聞への弾圧に抗って、読者の知る権利や声を背に沖縄の新聞記者たちはきょうもペンをとる。(文中・敬称略)
【「沖縄の新聞はつぶせ」】
その発言は、突然降ってきた。場所は自民党本部。いわずと知れた、日本のコントロールタワーの一つ。
時は2015年6月25日、いわゆる戦争法案の国会通過を前に、与野党はもちろんのこと、シールズなど若者を含め、世の中で法案の正否をめぐり活発に議論されている最中のことだった。会合の主催者は、安倍総理に近い自民党若手議員が日本国憲法改定の推進を目的に作った勉強会「文化芸術懇話会」。安倍親衛隊といっていいメンバーが揃った。
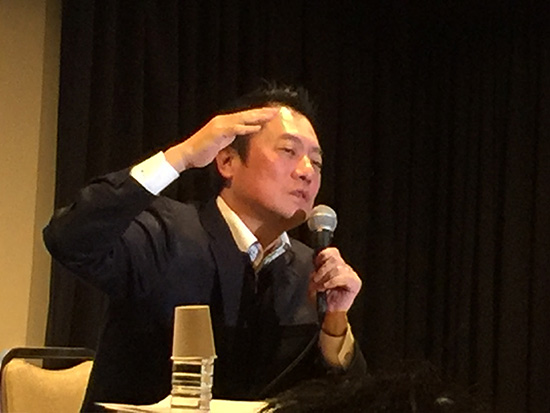
琉球新報の報道本部長・松元剛は読者目線を大事にする(2015年12月、大阪・十三の第七芸術劇場で筆者撮影)
ゲストスピーカーの作家百田(ひゃくた)尚樹に対し、議員から勇ましい意見が出た。「沖縄の地元新聞が政府に対し批判的だ」。この挑発意見の直後だった。会合のナショナルな雰囲気に呼応してか、百田が笑顔を振りまきながら、次のように応じた。
「やっかいやな、つぶさんとなあ」と。
ことはそれに留まらなかった。百田の発言に触発されたのか、自民党国会議員からは「マスコミを懲らしめるには広告収入をなくせばいい。文化人が経団連に働きかけてほしい」と。
つまり政権与党に批判的な新聞テレビは広告減らしで締め上げるぞという露骨な言論封殺だ。経団連に加盟する大企業に働きかけ、そうしたメディアには広告を出稿させない。言論を自分たちの言い分どおりにコントロールする制裁措置までが声高に議論され、会合は高揚感に包まれたという。
【沖縄の二つの新聞が反論】
沖縄の二つの新聞は、さっそく反撃にでた。琉球新報と沖縄タイムスの二つの新聞は翌日、編集局長名で共同抗議声明をだした(2015年6月26日)。
「(この発言は)政権の意に沿わない報道は許さないという“言論弾圧”の発想そのものであり、民主主義の根幹である表現の自由、報道の自由を否定する暴論にほかならない」と冒頭、釘をさす。
さらに、国会議員ではない作家の発言は自由だ、と表現の自由に配慮を示した上で、「政権与党である自民党の国会議員が党本部で開いた会合の席上であり、むしろ出席した議員側が沖縄の地元紙への批判を展開し、百田氏の発言を引き出している。その経緯も含め看過できるものではない」と、自民党に大きな責任があることを厳しく指摘した。
このあと、なぜ沖縄の新聞は政府に批判的な論調なのかをつぎのように説明した。「戦後、沖縄の新聞は戦争に加担した新聞人の反省から出発した。戦争につながるような報道は二度としないという考えが、報道姿勢のベースにある」。と、戦前、戦中の自らの過去への反省からだ。
その上で、こう続ける。「政府に批判的な報道は、権力監視の役割を担うメディアにとって当然であり、批判的な報道ができる社会こそが健全だと考える。にもかかわらず、批判的だからつぶすべきだ―という短絡的な発想は極めて危険であり、沖縄の2つの新聞に限らず、いずれ全国のマスコミに向けられる恐れのある危険きわまりないものだと思う」。
最後に、こう結論づけた。「(二紙は)今後も言論の自由、表現の自由を弾圧するかのような動きには断固として反対する」
この勉強会は、自民党青年局長の木原稔が代表をつとめていた。こうしたあからさまな報道への弾圧・圧力を示した暴論に、さすがの自民党も木原の党内役職を一年間停止する処分をした。しかしその舌の根も乾かない時期、戦争法案が国会を通過したあと、幹事長の谷垣禎一は「本人も反省している」との理屈にもならない理屈で、処分を3か月間に短縮し、木原は自民党の文部科学部会長に就任した(10月)。
結局、自民党内部では、ジャーナリズム機関に露骨な言論弾圧をほのめかしても、大したペナルティが課されないことを世間に示した。自由で民主的という党名の由来はなんだっただろう。
【防衛局長“レイプ”発言紙面化にゴーサイン】
沖縄の新聞記者から話を聞きたいと願っていたら、琉球新報の松元剛報道本部長が関西で講演することを聞きつけ、さっそく講演会にでかけた。会場は全国紙の新聞記者OBを含め多数の聴衆が詰めかけ、松元の話も熱がこもっていた。わたしは率直に感銘を受けた。そこで、この連載で紹介することにした。
松元が関わった新聞記事は当然のことながらたくさんあるが、ヒヤリングした中でもっとも印象に残った件を最初に書く。それは、防衛省沖縄防衛局長のオフレコ発言を掲載した記事だ。2011年11月29日の琉球新報の朝刊一面トップに載った。琉球新報の記事をそのまま引用する。
見出しはこうだ。「『犯す前に言うか』田中防衛局長 辺野古評価書提出めぐり」記事に移る。「沖縄防衛局の田中総局長は28日夜、報道陣との非公式の懇談会の席で、米軍普天間飛行場の代替施設建設の環境評価(アセスメント)の『評価書』の年内提出について、一川防衛相が『年内に提出できる準備をしている』との表現にとどめ、年内提出時期の明言を避けていることはなぜか、と問われたことに対し『これから犯しますよと言いますか』と述べ、年内提出の方針はあるものの、沖縄側の感情に配慮しているとの考えを示した」と事実関係を書いた。その上で、「県民、女性をさげすみ、人権感覚を欠いた防衛局長の問題発言に反発の声が上がりそうだ」と記事掲載の理由を加えた。
さらに、この発言が非公式の懇談会での発言という性格上、取材から記事掲載にいたるプロセスを次のように説明している。「田中局長は那覇市の居酒屋で、防衛局が呼びかけた報道陣との懇親会を開いた。報道陣は県内外の約10社が参加した」と懇親会は防衛局が呼びかけたものと説明した上で、続けて経緯をこう書く。「田中局長は非公式の懇談の席で発言したが、琉球新報社は発言内容を報じる公共性、公益性があると判断した」。
早い話、沖縄防衛局長は、国と沖縄との関係を男女間のレイプに例えたのだ。当時の野田民主党政権の新基地建設計画の是非が問題というより、ポイントは男女間の性犯罪に例えた、発言者の人権感覚こそが問題だったわけだ。
だから、完全オフレコを条件とする居酒屋での非公式懇談会の席上での発言とはいえ、そんな人権感覚の欠落した例え話をするエリート官僚・沖縄防衛局長の発言を琉球新報の新聞記者は見逃すことができなかったのだ。新聞記者の使命は、記事を書くことだ。耳にした情報は、読者、沖縄県民、ひいては広く日本の市民に、判断材料として提供することにある。
2015年に関西で開かれた講演会の席上、松元は次のように舞台裏を披露した。松元はこの記事掲載当時政治部長、いわば記事の直接の責任者だ。
「オフレコを条件にした懇談会の席上での発言だが、参加し発言を直接耳にした記者が憤懣やる方ないと電話をしてきた。記事にするかどうか、一瞬、迷ったが、記事にしようと決めた。沖縄県民を蔑むこの暴言を報じなければ、県民・読者への背信行為になると考えた。記事にするからには、沖縄防衛局に事前通告し、コメントを取るように指示した」。
予想通り、この発言は大きな問題に発展した。琉球新報が一面トップで記事を掲載した当日(29日)、田中沖縄防衛局長は東京の防衛省に呼び出され、事情聴取を受けた。
その日の夜には、田中局長の更迭が決った。
もっとひどい報道機関になると、「完全オフレコの席での発言を記事にするのはそっちの方が問題だ、そんなことが続くと、今後、取材がやりにくくなる」と、ぼやいた。
JCJ(日本ジャーナリスト会議)は、2012年度のJCJ賞に「沖縄防衛局長の『オフレコ』暴言スクープをはじめとする米軍普天間飛行場移設問題をめぐる一連の報道」を選んだ。
【琉球新報の報道本部長】
松元にインタビューを申し込み、貴重な時間をとってもらった。
現在、琉球新報の報道本部長と編集局次長を兼務する松元剛は、1965年11月3日生まれ。最初、日付を耳にして、とっさに、わたしが返したことばは「明治節ですね」と口走ったら、松元は皮肉っぽく、にやりと笑った。明治天皇の誕生日は、かつて大日本帝国の時代は、紀元節(2月11日)と並んで、国家の一大行事だった。
父親は県庁(正確には、琉球政府)の職員。那覇市に合併する前の真和志村(まわしそん)で、村議会議員選に立候補し当選し、1期だけ務めた経歴がある。母親は久米島をルーツにもつ。父親はどちらかといえば、当初は沖縄社会大衆党(1950年結成した地域政党)の支持者だったらしく、保革の対立が激しい沖縄の地にあって、リベラルな家庭に育った。

松元剛は沖縄の置かれた厳しい現実に直球勝負のスクープを連発。酒も強い(2015年12月、大阪・十三の居酒屋で筆者撮影)
小学校時代の思い出は二つ。沖縄の施政権がアメリカから返還された1972年5月15日、父親に連れられて、那覇市内与儀(よぎ)公園で開かれた「基地つき沖縄返還反対集会」に参加したこと。そして一年後の73年5月15日、小学校で「特設授業」が開講された。
その授業で担任の教師が「1年前の本土復帰の前と後で何が変わりましたか?」と質問した。
松元が「パスポートが要らなくなりました」と返事をすると「よく知っていましたねぇ」とえらく誉められた。松元が社会へ関心を向ける最初の出来事だという。
沖縄の進学校、那覇高校から、大学は地元の国立琉球大学の法文学部に合格した。が、当時、テレビ番組「JNN報道特集」でゲストスピーカーとしてたびたび政治解説を担当する政治学者の福岡政行にあこがれ、福岡がゼミを担当する、東京の駒澤大学法学部に進学する。
「体育会系のようでした」
福岡ゼミは出欠が厳しく三回遅刻すると除名処分だったと、苦笑まじりに松元は当時をふり返る。福岡に伴われ、日本全国の選挙区をフィールドワークする活動が続いた。社会への興味が深かまったという。福岡の著作リストを国立国会図書館で検索すると、松元が駒澤大学に進学し福岡ゼミに籍を置いていた時期、つまり1980年代に日本政治分析に関係する単著を6冊出版している。著作活動で見る限り、福岡が一番油の乗っている時期に、松元は「体育会系」ゼミで厳しくも楽しい学生生活を送ったことになる。
松元は島根県と大分県で進められていた、ふるさと村おこしや一村一品運動のフィールドワークに参加。ゼミ生も交えたこの研究は一冊の本になっている。「問題のありかを探っていくのが、興味深かった」という。北海道の夕張や室蘭、岩手県の釜石など、重厚長大産業が斜陽した地域での地域おこしや島おこしを直接見聞きするため、学生時代、日本中を歩いた。
やがてジャーナリストを志す。朝日新聞の就職試験も最終段階まで残ったが、学生時代暮らした沖縄出身者のための学生寮の先輩や福岡ゼミの先輩の新報記者・前泊博盛(論説委員長から沖縄国際大学教授に転身)の「琉球新報は自由な社風だから」という言葉が決め手になって、琉球新報を選ぶ。
【トロッコからキシャに】
新聞記者の世界では、一人前の新聞記者になることを「トロッコからキシャに」と自嘲気味に表現するが、松元に新聞記者になって原点を教えてくれたのは取材先であった。
多くの新聞記者がそうであるように、松元の振り出しは警察担当、二年目は校閲部で先輩記者の原稿をお手本に記事のイロハを勉強する。三年目、松元は裁判所回りに配属された。司法記者一年生を待っていたのは、那覇市の情報公開をめぐって、地元那覇市と防衛庁が真っ向から対立する裁判であった。
自衛隊の対潜水艦作戦センター那覇基地の建設計画をめぐって、建築基準法に基づき那覇市に提出された設計図を公開するかどうかが裁判の争点であった。那覇市は公開をしても問題はないと主張、防衛庁は公開の取り消しを求めた。「ここでの論点は、情報は誰のものか」。松元は、那覇市民からの公開請求をめぐって、「知る権利」と国家の安全保障政策がせめぎ合う厳しい洗礼を、司法記者の第一歩から受けた。
【沖縄の闘いの原点を知る】
決定的だったのは、嘉手納基地の爆音訴訟であった。
ご存知のように、嘉手納基地は東アジア最大の米空軍の基地。広さは民間空港で日本最大の東京国際空港(羽田)の約2倍、長さ3700メートルの滑走路が2本。嘉手納基地といえば、ベトナム反戦世代としては怪鳥のような巨大なB52が沖縄から北ベトナムへの爆撃に出撃した映像が鮮明な記憶として残っている。
北谷町(ちゃたんちょう)砂辺(すなべ)地区は、嘉手納基地の3700メートル滑走路の米空軍ジェット戦闘機や爆撃機の飛行コースの真下に位置する。米空軍は、日米安保条約、そして地位協定に守られ24時間、夜中であろうがお構いなく飛行を実施している。
松元は国を相手取って基地周辺住民が起こした飛行差し止めを求める裁判の原告から取材を開始し、その騒音被害の余りのむごさに絶句する。
訪ねた原告は齢60を越しそれまでの仕事をリタイアした夫婦であった。子どもが結婚し、嫁との間に孫が誕生したので、62歳のジジは子どもと嫁、孫といっしょに暮らすのを夢見て、自宅の敷地に家を建てた。
62歳の原告の男性を取材した際、沖縄テレビ(フジテレビ系)がお昼の時間、午後1時近くになりタモリの『笑っていいとも』のエンドテーマ曲がかかった。少し歩けるようになった1歳ちょっとになる孫の男の子が反射的に血相を変えて、おじいちゃんのところに駆け寄ってきた。理由は米空軍パイロットのランチタイムが終わり、エンドテーマがテレビから流れるとまもなく、訓練が再開されたジェット戦闘機F15が、北谷町の真上をかすめるように飛んでいく。訓練がやんで静かな時間帯が過ぎた後、轟音を振りまく戦闘機の訓練が再開されると、1歳の孫がパニック状態に陥って泣き出す。その場を目の当たりにした松元は大きな衝撃を受け、言葉が出なかった。その戦闘機が生み出す音は騒音というような生やさしいレベルではないと、原告は若き司法記者に現状を訴えた。
62歳の原告は松元に問うた。「この赤ん坊が最初に口にした言葉が何か、分かりますか。パパでもママでもありません。じぃじ、ばぁばでもない。自分で耳をふさいで『怖い、怖い』というんです。母親がジェット機の飛ぶたびに口にする叫び声を、この子は本能的に受け入れ覚えたんでしょうね」。米軍のジェット機の騒音に耐えられなくなって、ジジがなけなしの退職金から子どもたち夫婦のためにせっかく建てた家から、子どもたち一家は1年もたたずに逃げ出さざるをえなかった。
地元の小学校に取材に行くと、小学校の教師がこう現実を説明したという。「小学校で突然、大きな声を上げる生徒が年々増えています。きっと自分で自分の感情が制御できなくなるんでしょう。ジェット機による騒音が子どもたちにいい知れぬ恐怖を与えているです」。
松元は、ショックを受けた。米兵の事件・事故、訓練による被害に苦しむ住民の目線で、当たり前に保障されるはずの平穏な生活を求める声に寄り添って基地の弊害を突き、改善を求めることこそが沖縄の新聞、基地ジャーナリズムの使命だと胸に刻み付ける原点になったのが、嘉手納基地爆音訴訟の取材だった。
その裁判は、1981年に原告団が結成され、翌年初めて提訴。以来、三回にわたって裁判が起こされた。一次原告が907人、二次訴訟の原告が5542人、そして三次訴訟の原告に至っては22000人余りを数える。判決はどれも原告住民の訴えを認め、過去の賠償を認める(つまり金は払う)。一方で、肝心の飛行差し止めは認めなかった。日米安保条約が存在しているからだ。
【米海兵隊員によるレイプ】
司法記者をしていると、こんなことも耳に入ってきた。米兵に沖縄の女性がレイプされたが、基地内で拘束されていた容疑者が脱走し、忽然と姿を消してしまった。読者から情報提供があったのだ。レイプされた被害者周辺から「こんなことが許されるのか」と怒りを帯びた電話があり、米軍の対応を断罪してほしいと望んだらしい。そこで、琉球新報の記者たちが取材を始めた。日米地位協定の定めにより、基地内で拘束された米兵は起訴されるまで、日本の警察に身柄が引き渡されない。その間は、米軍の憲兵隊が基地から護送する形で警察の取り調べを受け、基地に戻る仕組みだった。その制度的不備を突き、容疑者の米兵はやすやすと拘束されていた嘉手納基地から逃げおおせたのだった。
松元の同期の記者が取材した沖縄県警刑事部の幹部は「自分からは言えない」と確認を拒否したが、部屋からの出際に「オレの口からは言えない。しかし、君たちはどんなことがあっても、この事実を突きとめろ」と言われたという。つまり、事件の詳細を教えられないけれど、あったかなかったということについては、暗黙の了解でレイプ事件の存在と米兵の脱走を認めたことになる。
脱走により、那覇地検が起訴できなくなっている事実とどのようにして民間航空機で本国に戻ることができたのかを琉球新報がスクープ報道した。犯人の米兵は出国の書類を偽造し、那覇空港からノースウエスト航空機でサンフランシスコに出国していたのだった。
その上、レイプされた女性のもとには、米軍の法務官が訪ねてきて「示談で済ませませんか」と交渉に来たという。女性は「セカンドレイプされたみたいだ」と不快感をもったはずだ。国家からの言い知れぬプレッシャーを感じて、レイプされたとの被害届けを取り下げてしまった。強姦罪は親告罪なので、被害女性からの被害届がなければ、捜査機関は捜査できない。結局、このレイプ事件は容疑者が特定されていながら、日本の裁判所では裁かれないままだった。容疑者は米国で拘束された後、沖縄に送り戻され、軍法で脱走を罰せられただけだった。
こうした女性に対する数々のレイプ(しかも容疑者が処罰されない)事件の積み重ねの上に起きたのが、沖縄米兵少女強姦事件だ。早いもので、発生から20年経過した。
1995年9月4日、米海軍と海兵隊の三人が基地内でレンタカーを借り、沖縄北部の商店街で買い物をしていた少女をレンタカーに拉致した。粘着テープで少女の手足を縛り、近くの海岸で少女を輪姦し、負傷させた。この少女は12歳の小学生だった。3日後、日本の警察は容疑者3人を特定し逮捕状を請求したが、米兵3人は日米地位協定の規定で日本側が身柄を拘束して取り調べることができなかった。
沖縄県民の感情は爆発した。県議会や宜野湾市議会など沖縄の自治体の議会が相次いで抗議決議を採択。10月21日、事件に抗議する県民決起大会が開かれ、県知事をはじめ8万5千人(主催者発表)が参加した。
琉球新報は一面と最終面を見開きで大きな写真を載せ、県民のやり場のない怒りを伝えた。沖縄県民の米軍に対する感情のベクトルが変わったのは、この事件の影響が決定的に大きい。
一番の問題点は、日米地位協定の内容だ。アメリカ軍が駐留する、ドイツやイタリアでも日本同様に米軍の法的地位を定めた協定を結んでいるが、今度のように公務外に基地の外で刑法を犯した米兵の取り扱いは国内法に準じる扱いに改訂されている。まるで沖縄が植民地であるかのように、自国民を、ましてや12歳の少女をレイプした米兵を自国警察が取り調べすらできないなど、ドイツやイタリアでは考えられない。
日本政府はこの事件を受けて、基地の外で犯罪を犯した兵士が基地内に逃げ込んだ後に拘束された場合をめぐり、米側と地位協定本文の改定ではなく、運用改善で合意した。それは殺人、強盗、強姦などの凶悪犯罪に限り、米側が身柄引き渡し要求について「好意的に」配慮するという内容だ。日本側が要求しない限り、身柄は引き渡されない。あくまで、米側が決定権を持ち、「好意的に」日本側の要求に応じるか否かを決めるというものである。不平等は是正されていない。
松元ら、沖縄の新聞記者が対峙せざるを得なかったのは、このような独立国とは思えない日米地位協定の内容であり、24時間住民がいないかのごとき沖縄の米軍の立ち振る舞い、それに唯々諾々と異議申し立てもしないで、新しい軍事基地建設を沖縄に押しつける自国政府のふがいなさであった。
松元は、2002年韓国に出張する。連載記事「軍事基地と住民」の取材のためだ。
10泊11日、その間、韓国国内でアメリカ軍を抱える地域の住民48人に面談、録音したテープ60時間、気候温暖の沖縄から極寒の韓国を訪れ、「はじめて寒さで歯がかみ合わない経験をしました」と、松元は笑い飛ばすが、気温はマイナス13度。
昼間は取材、夜は反基地闘争をになう韓国の市民グループからの歓迎の宴が連日連夜続き、酒豪の松元もさすがに取材は体力勝負と覚悟を決めたと、苦笑いをした。とはいえ、まんざら嫌いではなかったようだし、なにより、アメリカ軍相手の地位協定を韓国で徐々に韓国国民本位に改訂がすすむプロセスを肌身に感じた。日本は、敗戦、そして占領を経たとはいえ、遅々として改善のすすまない日本政府へのやりきれない思いを感じた韓国取材旅行であったという。
【日米地位協定の考え方・増補版をスクープ】
松元が編集委員になった2002年、先輩記者の前泊博盛とペアとなって、日米地位協定にターゲットを絞った取材を開始する。それはやがて、「検証 地位協定―日米不平等の源流」という連載記事に結実する。松元たちが秘密裏に入手した、日米地位協定の「解釈マニュアル」は徹頭徹尾、アメリカ政府寄りの解釈に充ち満ちていた。
2004年に正月から始まったキャンペーン記事は反響を呼んだ。沖縄県選出の国会議員が党派を超え、国政調査権を基に、永久機密指定された「裏解釈マニュアル」の「日米地位協定の考え方」の公開を求めたが、外務省は「米国との信頼関係を損なう」として拒んだ。それに対し、琉球新報は1月中旬、編集局総掛かりで13ページ全面ブチ抜き特集を組み、この永久機密文書を全文掲載した。さらに連日、解説記事をまじえ連載は9か月間に及んだ。この連載は、のちに、同名のタイトルで本として出版され、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞やJCJ(日本ジャーナリスト会議)賞大賞を受賞する。
外務省は機密漏えいの犯人探しに躍起になった。外務省内部でも総合外交政策局安全保障政策課の、それもごく一部しか知らない解釈マニュアルを入手した相手を守ることに、松元たちは細心の努力を払ったが、幸いにして松元たちの努力が功を奏して、いままでのところ機密文書の入手先は特定されていないという。
アメリカ軍はドイツ、イタリア、韓国など、およそ20万人が世界中に展開している。ドイツでは、はじめ1959年に結んだ協定を1983年に改訂し、低空飛行などの運用はドイツ国内法に従うこととなった。イタリアでも同様だ。韓国では「環境条項」が結ばれ、基地内へ各自治体が立ち入り検査を実施する「共同調査権」が確立しており、返還された米軍基地内から汚染がみつかれば、米軍に浄化する義務が定められている。こうした条項は、いずれも、日本政府との協定にはない。
【思い出す、沖縄密約スクープ】
沖縄とメディアの関係で真っ先に頭に浮かぶのは、西山太吉毎日新聞記者(当時)による、沖縄密約のスクープだ。国家(警視庁と東京地検)は、西山記者と彼に情報を提供した外務省事務官を国家公務員法違反(機密の漏洩)で起訴した。沖縄密約問題の本質は、本来アメリカ政府が支払うべき諸費用400万ドルを日本政府が肩代わりして支払う「密約」を交わし、国民にウソをついたことだ。民主制の世の中で、政府が税金を支払う国民にウソをいい、さらにはその政府のウソを暴いた新聞記者を逮捕し、裁きにかけることがあってはならないことだ。ましてや、検察は起訴状に「情を通じ」との文言を盛り込み、男女関係に論点をすりかえた。
西山記者は一審で、無罪の判決を受けたが、やがて二審で逆転有罪、最高裁はそれを追認した。沖縄密約の情報公開を求める裁判も、最高裁は国側に軍配を上げた。
民主主義は天から降っては来ない。
民主主義は闘って勝ちとらねば結実しない。民主主義にとって必要なのは、情報公開制度と公益通報制度。なによりも、そして何よりも主権者である市民を守る番犬として忠実に働くメディアの存在が必要だ。
たとえ刑務所に送られてもいい。主権者の知る権利に応えて、手に入れた情報を市民に伝えるのが、ジャーナリストの本務ではないのか。
沖縄から議論が離れるが、かつて高知県警の裏金疑惑を裏付けるデータを手に入れた新聞記者が、このデータを報道したら、明日から警察取材がやりにくくなると困ると悩み、先輩記者に相談したことがあったという。その時、先輩記者が後輩に諭した言葉はこうだ。
「確かに、お前がこの資料を手に入れた。しかし、この資料はお前のものではない。 読者のものではないのか。われわれ新聞記者は読者のために存在するのではないのか」と(高知新聞記者の高田昌幸の著書より)。
昨年の安倍親衛隊が主催する自民党会合で、作家百田尚樹の「沖縄の新聞なんぞ、つぶれてしまえ」「沖縄の新聞はくずだ」。さらには自民党国会議員の「経団連に言って、広告費をひきあげるぞ」発言など、権力者とそれにおもねるエセ文化人の本音を明らかした。
自民党の安倍親衛隊は誤解している。日本政府が進める辺野古への新基地建設に、翁長知事をはじめ沖縄県民が反対している理由は、沖縄タイムスや琉球新報など沖縄の新聞があおっているからではない。嘉手納基地の爆音訴訟の原告、あるいは米兵にレイプされた小学生など、米軍による沖縄への仕打ちがあまりにひどく、しかも日本政府が対米追従ばかりで、沖縄県民を露骨に差別している現実故に、県民が新聞記者を叱咤激励した、その反映だということを知らない。主客が転倒しているのだ。現実を直視せよといいたい。
しかし、だからこそというべきか、権力から蛇蝎のごとく嫌われるメディアは本来の市民の番犬として、しっかり権力監視の役目を果たしている、その勲章なのではないか。
メディアは誰のモノか、メディアは誰のために存在しているのか。インターネットが台頭し、新聞やテレビラジオは絶滅危惧種と揶揄される。しかし、権力としっかり闘う沖縄の新聞記者たち、その代表としての松元剛の仕事をつぶさに見るとき、メディアは読者のもの、視聴者のものという立ち位置はすっきりはっきりするのではないか。
琉球新報は「沖縄の自己決定権を問うキャンペーン連載」で、2015年度の石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞した。21世紀に入って始まったこの賞で、実に3回も受賞している。いま、この新聞は沖縄タイムスと並び日本の新聞の最先頭に位置しているといって過言ではないだろう。そしてそこには、嘉手納基地爆音訴訟の原告らが、そうした取材活動をすすめる記者たちを支える構図が見える。
松元はスコットランドの独立をめぐる住民投票にはイギリスに記者を送り、スペインのバスク地方の独立運動にも大きな関心を寄せる。「法の支配」を口にする一方で日本国憲法を閣議決定で勝手に解釈を替える安倍政権と、琉球新報が細かく点検する世界の民主主義の動きと、どちらが世界の大勢なのか、言をまたない。
改めて問いたい。レイプされた小学生に象徴される沖縄の近現代史を知るたび、日米地位協定に象徴される日本という国は、ほんとうに独立した主権国家なのか。沖縄はアメリカや本土の植民地なのか。
なにより日本は民主主義の国なのか。疑わざるを得ない。
にしむら・ひでき
1951年生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学経済学部卒。元毎日放送記者。日本ペンクラブ理事。近畿大学人権問題研究所教員。同志社大学社会学部講師。著書に『北朝鮮抑留~第十八富士山丸事件の真相』(岩波現代文庫)、『大阪で闘った朝鮮戦争~吹田・枚方事件の青春群像』(岩波書店)など。
連載
- シリーズ/抗う人⑭
言論弾圧に抗い、読者の知る権利に応える 沖縄の新聞記者~松元 剛ジャーナリスト/西村 秀樹
